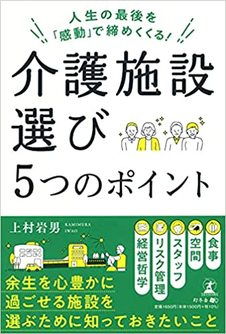ウィズコロナの時代、特に感染リスク対策が重要
ウイルスや細菌等によって引き起こされる感染症は、入居者先生の命や健康に脅威を与える大きなリスクのひとつです。
例えば、ノロウイルス感染症は季節毎に毎年のように発生します。飛沫でうつることもあり感染力は非常に強力です。おむつ交換などの際には、手袋をしていなければスタッフにも感染する恐れがあります。
なかでも、新型コロナウイルスは、現在、介護施設が最も警戒しているリスク要因といっても過言ではありません。
多くの施設では、厚生労働省の通達に従う形で、入居者先生と家族の面会には厳格な制限が設けられています。居室内や施設の内部での面会は避けてもらい、建物の入口などでドア越しに面会していただいたり、あるいはテレビ電話のシステムなどを使って話をしてもらったりしている施設運営業者は多いです。
さらに、「感染対策がしっかりとできているかどうか」を気に掛けている高齢者やその家族も増えています。実際、施設に対する問い合わせで「新型コロナウイルスへの対策は大丈夫でしょうか」と尋ねる人が、最近少なくありません。
感染対策は手洗いなどの基本を徹底することが重要
このように、ウィズコロナの時代の中で、感染リスク対策をしっかりと講じているのか否かが施設選びの基準として重要視される流れがあります。感染予防の方法は、コロナであれノロであれ基本は同じといってよいでしょう。
スタッフや入居者等の手洗いやうがいの励行、テーブルや椅子、手摺り、そしてドアノブなどのアルコール消毒を徹底することが何よりも大切になります。
コロナに関しては、これらに加えて、スタッフ等の施設関係者に対してはマスクの着用も求められることになります。意外と見落としがちになるのが共用のパソコンのキーボードやマウス、ピアノの鍵盤等です。前者についてはクラスターが発生した例が医療機関で確認されています。
こうした対策を万全に行うことで、入居者先生の命と健康を最大限に守ることが可能となるのです。さらに、入居の際の手続きに関しても、コロナ対策への配慮を十分に行うことが望ましいでしょう。
具体的に述べると、サービス付き高齢者向け住宅の場合、賃貸借契約を交わすことになります。その際に、宅地建物取引業法では重要事項説明書の内容を伝えることが義務づけられています。
この重要事項説明書の告知は原則的に対面で直接的に行うことになっているのですが、近時の法改正で賃貸借契約に関しては、電話やテレビ会議などのITを活用して行う「IT重説」が認められるようになりました。
重要事項説明書の説明が求められる場面において、こうしたリモートの仕組みを積極的に使うことで、感染症のリスクをさらに低減することが可能となると同時に、利用者側と施設運営側双方のコスト削減の効果も期待できます。
注目のセミナー情報
【国内不動産】2月14日(土)開催
融資の限界を迎えた不動産オーナー必見
“3億円の壁”を突破し、“資産10億円”を目指す!
アパックスホームが提案する「特別提携ローン」活用戦略