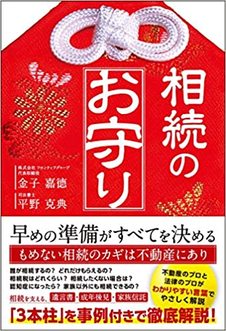遺言書を作成するときは、相続税の負担も考慮する
遺言は自分の意思通りに相続させるために、とても有効な方法です。しかし、気をつけなければならない点もあります。実際に自分が亡くなって相続が発生したとき、家族や相続人が困らないように、押さえておくべき点をお話しします。
まず、相続税についてです。相続税の税率は、最も低い取得価格1000万円以下でも10%です。決して安くはありません。現金であればその中から払えばいいわけですが、不動産であればその通りにはいきません。
例えば、「長男に評価額1億円の自宅、次男に預貯金1億円を相続させる」という遺言をしたとすると、長男は現金を受け取れないため、相続税のための資金を調達しなければならなくなります。そして、もし長男が相続税を納税できなければ、せっかく引き継いだ家を資金調達のために売ることになってしまいます。
不動産を相続させる人には、相続税の支払いに困らないかどうかまで考えておくべきです。ほかにも、相続登記のための登録免許税や司法書士への報酬、毎年課税される固定資産税なども発生します。こうした費用も支払えるくらいの現金も譲り渡すよう考慮しましょう。
遺言では、法定相続人以外の人に遺贈で財産を引き継がせることができます。ただし、配偶者や一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外に遺贈する場合、相続税は法定相続人の場合と比べて1.2倍です。それも計算に入れておきましょう。
遺言通りに遺産分割させるには、遺言執行者を決める
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、「遺言執行者」を指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために遺産を管理し、分割のための事務手続きを担う人です。遺言執行者がいなくても遺産の分割はできますが、執行者がいると手続きがスムーズになります。
例えば、遺言書通りに相続する場合でも、相続手続きは相続人全員の印鑑が必要になるケースも多いのですが、遺言執行者がいれば、原則として遺言執行者が単独で手続きを進められます。
さらに、遺言執行者が指定されていれば、トラブルへの対応もスムーズです。遺産である自宅を相続人のうちの1人が勝手に売ってしまったなど、遺言の執行を妨げる処分行為が行われたとしても、原則としてその行為は無効とされます。
ただし、例外として、善意の第三者に対抗できません。例えば、遺贈の事実を知らないで、その土地を購入した第三者がいたとします。遺贈を受けた者は登記をしていないと、法定相続分を超える持分については、その権利を主張できないことになります。
なお、遺言執行者は、未成年者と破産者以外なら誰でも構いません。相続人でもなれますが、もし慣れない手続きに不安があれば、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するといいでしょう。