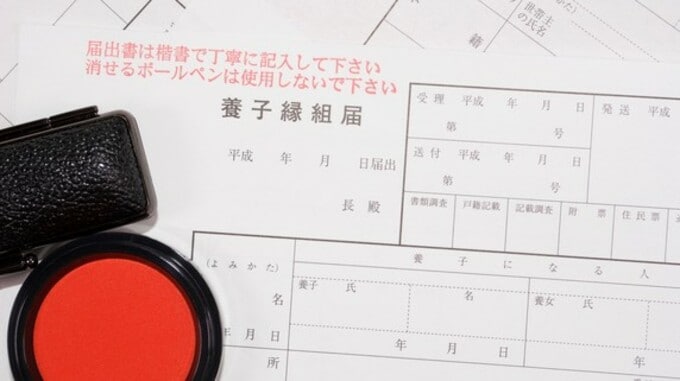「遺言×養子縁組」で不動産取得時の税金が安くなる
不動産を取得する場合に課される代表的な税金は、次の通りです。
① 登録免許税
② 不動産取得税(※所得税ではありません)
まず、①登録免許税とは、不動産の所有権移転の際に法務局でかかる税金で、固定資産税評価額に決まった税率を乗じます。遺贈(法定相続人以外の人が遺言によって不動産を取得する場合)では、生前贈与や売買と同じく、税率「1000分の20」となりますが、相続(実子や養子が法定相続人として不動産を取得する場合)では、税率「1000分の4」と軽減されます。税金が5分の1で済む、ということです。
次に、②不動産取得税とは、文字通り不動産を取得することにより課される税金で、不動産取得から数ヵ月後に市区町村から通知が来ることになります。遺贈で不動産を取得すると、生前贈与や売買と同じく課されますが、相続で不動産を取得すると、不動産取得税は課されません。
「遺言×養子縁組」で相続税が安くなる
代表的なところでは、相続税が減る(可能性が高い)という効果もあります。相続税の計算過程を見ていきますと、法定相続人が多ければ多いほど相続税が安くなるような仕組みになっています。
① 基礎控除額(=相続税の非課税枠)
② 生命保険金及び死亡退職金の非課税限度額
③ 相続税の総額の計算
たとえば、元々の法定相続人が3名だったところに、養子を1名増やすことで法定相続人は4名となりますので、①基礎控除額は4,800万円から5,400万円に増えますし、②生命保険金及び死亡退職金の非課税限度額も、1,500万円から2,000万円に増えます。相続税の負担を減少させる結果となります。
また、③相続税の総額を計算するに当たっては、法定相続分に応じた各取得金額に超過累進税率を乗じて計算されますので、法定相続人の数が増えれば増えるほど相続税の負担を減少させることとなります。
しかし、「相続税が減る(可能性が高い)」と前述した通り、結果的に相続税が増える場合もありえます。孫(存命中の子の子)を養子にした場合、いわゆる「孫養子」では、相続税の2割加算が適用されますので注意が必要です。通常通りに計算した場合の相続税に、2割が加算された相続税を納めることになります。法定相続人が増えることによる相続税の減額と、2割加算による相続税の増額とを、きちんと確認しておく必要があります。「孫養子」以外の養子であれば、実子と同じ扱いになるので2割加算の適用はありません。