\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
10年以上にわたって続いたグロース株相場
MSCI世界バリュー株指数と同グロース株指数のパフォーマンスを1974年12月末からの長期で計測すると、バリュー株のほうがパフォーマンスが高いことが分かる(図表1)。
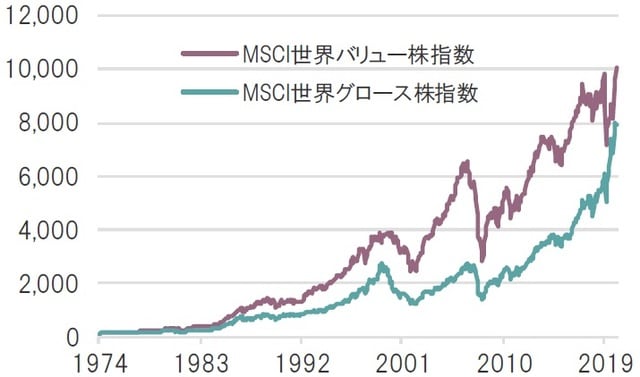
期間:1974年12月末~2021年2月末
出所:ブルームバーグのデータを基にピクテ投信投資顧問作成
しかし、この2つの指数の相対パフォーマンス(グロース株÷バリュー株)でみると、2006年12月末をボトム(底)に、近年では米10年国債利回りの急低下を受けて、グロース株のパフォーマンスが追い上げる状況が続いていた(図表2)。
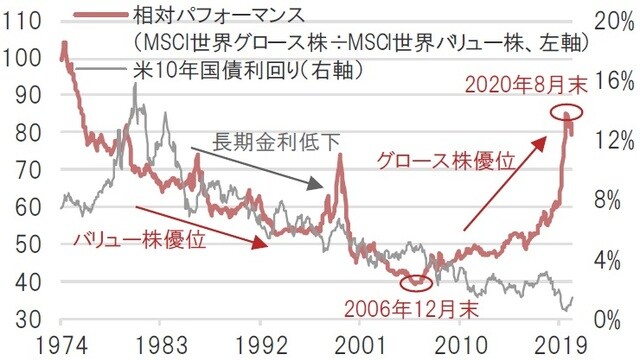
期間:1974年12月末~2021年2月末
出所:ブルームバーグのデータを基にピクテ投信投資顧問作成
この状況に変化が表れたのが2020年8月末以降だ。米10年国債利回りが「経済の正常化」や「追加景気対策」への期待感を背景に上昇に転じたことをきっかけに、足元ではバリュー株優位の展開へシフトしている(図表3)。

期間:2020年8月末~2021年3月19日
出所:ブルームバーグのデータを基にピクテ投信投資顧問作成
2021年3月のFOMCの結果を受けて、グロース株/バリュー株の相対パフォーマンスが大きく変動したのも、その背景には米10年国債利回りの変動がある。
「スタイル・ローテーション」よりも「スタイル分散」のほうが重要
グロース株優位の相場展開が10年以上も経過したことを考えれば、投資家のポートフォリオがグロース株中心に構築されていたとしても不思議ではないだろう。そのような中、米10年国債利回りの上昇をきっかけにバリュー株優位の展開へ急速にシフトしたことで、「スタイル・ローテーション(投資家がグロース株からバリュー株などへ投資スタイルを変化させること)」が巻き起こり、相場への影響が大きくなったことが推測される。
だが、「足元の」米10年国債利回りと相対パフォーマンスの連動性は2006年12月末以降に生じた現象であり、1981年9月末から2006年12月末(ITバブル期除く)までは、むしろ米10年国債利回りの低下とバリュー株優位の展開が並存していた。
つまり、短期的には米10年国債利回りと相対パフォーマンスの連動性が強いように思えても、いつ「デカップリング(連動性の低下や逆転現象)」を引き起こすか分からない。二者択一の「スタイル・ローテーション」よりも、「スタイル分散(グロース株とバリュー株に分散投資」のほうが、長期投資においてはより重要だろう。
※当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『グロース株とバリュー株「スタイル・ローテーション」よりも「スタイル分散」』を参照)。
(2021年3月22日)
田中 純平
ピクテ投信投資顧問株式会社
運用・商品本部 投資戦略部 ストラテジスト
日本経済の行方、米国株式市場、新NISA、オルタナティブ投資…
圧倒的知識で各専門家が解説!カメハメハ倶楽部の資産運用セミナー
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!
スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資
【2/18開催】
金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険
“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察
「これからの不動産投資」
【2/18開催】
認知症となった80代賃貸不動産オーナー
家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!
『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは































