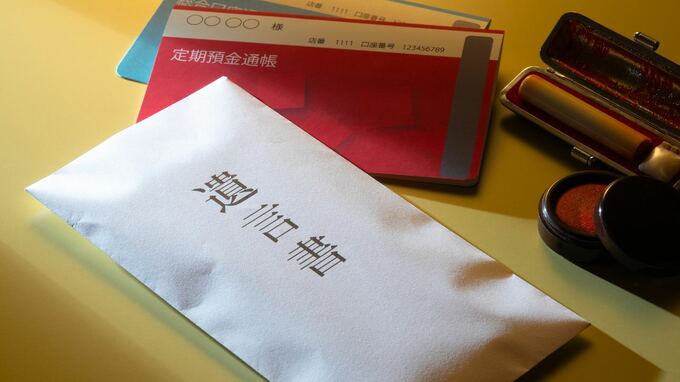兄が「遺産の一部分割」を申し立てる一方、祐人は…
祐人は、午後4時頃、鈴木法律事務所で打合せをしていた。
「話合いがつきそうなのか?」
「兄貴は、キウイ畑だけ先に売却して、平等に分けようって言って、こっちの話を聞こうとしないんだ。もう業者に連絡して、買い付け証明書を取り付けたらしい。しかも預金の減り方が異常だとか言って、僕たちが使い込んでいるんじゃないかとか疑いをかけてきているんだよ」
「双方、熱くなりすぎだな。この前のお兄さんの態度を見てて分かるよ。裁判所の調停を考えてみてもいいんじゃないか」
「裁判をやるなんて、親父が草場の陰で悲しむよ。親父は争いごとが嫌いだったから」
「裁判所って言ったって、裁判をやるわけじゃないんだぜ。家庭裁判所で、中立的な立場の調停委員が間に入って話合いをするんだよ。調停が成立すれば、調停調書を作成するし、調停調書は、確定した審判と同じ効力があるんだ。無理を主張しているお兄さんの状況を見ていると、調停を利用するのが一番いいと思うな」
「そんなもんか。お袋と相談してみるよ。そのときはお前に頼んでもいいか」
「もちろんだよ」
――兄・真人が開港家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをした数日後、鈴木弁護士のもとに祐人から電話が入った。
「兄貴に先手を取られたよ。家に帰ったら、俺とお袋に遺産分割調停の調停期日通知書が届いてたよ」
「調停は申立てをした方が有利になるということはないからな。それで、期日はいつなんだ?」
祐人は指定された期日を知らせた。
「その日なら俺は空いてるよ」
「よろしく頼む。どうすればいい?」
「手続代理委任状の用紙を送るから、お母さんとお前の署名押印をした上でそれを持ってきてくれ。俺の方から裁判所に提出する。裁判所から送られてきている書類も併せて持ってきてくれ。お前の意向を確認して提出することにする」
「分かった。明後日には持って行けると思う」
三男の妻・亜季に「亡き夫の介護のお礼」を望む愛子
「利彦。裁判所から手紙、来てたでしょ? 見た?」
「見たよ。おじいちゃんの遺産についての調停らしい。その日は授業ないから、出席しようと思っているんだ」
「話をよく聞くのよ」
「分かってるよ。期日が終わったら何をやったかを話すよ」
「私はお義母さんの様子を見てから仕事に行くわ」
亜季は、利彦を玄関で見送り、支度に取り掛かった。義母・愛子の自宅に着くと、愛子と義兄・祐人が居間に座って話をしていた。
「おはようございます」
2人の顔色から深刻な様子がうかがわれた。話題は調停のことなんだろう。
「利彦君のところにも調停の連絡が来たと思うけど…」
予感は当たった。
「利彦は出席するって言っています。ただ、全員で仲良く、納得して分けていただければいいと思っているのだけど…」
「今話していたのは、亜季さんのことなんだ」
「私の?」
「お袋が、親父の面倒をずっとみてくれた亜季さんに遺産を少しでも分けてあげられないかと話しているんだ。遺言書は無効であるとはいえ、遺言書には親父の感謝の言葉が書いてあったからね」
「お気持ちはうれしいけど、でも、私は相続人じゃないし…」
「それは分かってるよ。僕よりも友人の鈴木弁護士から説明を受けた方が早いから、今度話を一緒に聞きに行こうよ」
「はあ…」
鈴木弁護士の説明~特別寄与料とは?
その週の金曜日の午後、愛子と祐人と亜季の3人は、鈴木法律事務所にいた。
「祐人の言っていることは本当なんだ。亜季さんが信太郎さんに対し行った看護について、愛子さんからお礼をしたいという相談を受けたから、アドバイスをしたんですよ。寄与分的な意味のお礼をあげたらどうかってね」
「寄与分といっても。私は相続人ではないのですけど」
「確かに、亜季さんは相続人ではないけど、相続法が改正されて、特別寄与料という制度ができたんだ。特別寄与料という制度は、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策で、被相続人の親族が被相続人の療養看護等を無償で行った場合には、一定の要件の下で相続人に対して金銭請求をすることができるようになった」
鈴木弁護士は、特別寄与料の制度につき次のような説明をした。
*******************************
<改正法の解説>特別寄与料とは?
特別寄与料の制度とは、相続人ではない被相続人の親族が被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に、このような貢献をした者が、その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるとする制度(民1050条)です。
被相続人に対して療養看護等の貢献をした者が相続財産から分配を受けることを認める制度として、寄与分の制度があります。しかし、寄与分の制度は、相続人にのみに認められています。例えば、相続人の妻が被相続人(夫の父)の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合であっても、遺産分割手続において、妻が相続人でないことから、寄与分を主張したり、あるいは何らかの財産の分配を請求したりすることはできないという問題がありました。
裁判例(東京家審平成12年3月8日家月52巻8号35頁、東京高決平成22年9月13日家月63巻6号82頁等)は、このような問題に対して、夫の寄与分の中で妻の寄与行為を考慮することで解決を図ってきました。実務も、妻は相続人である夫の履行補助者として相続財産の維持に貢献したものと評価して運用してきました。
しかしながら、相続人である夫が被相続人よりも先に死亡した場合には、相続人の履行補助者とみる考え方によっても、相続人が存在しないため、妻の寄与行為を考慮することができませんでした。
そこで、改正法は、相続人ではない者(相続人の配偶者等)が被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合に、前記のような貢献をした者に対して、一定の財産を分け与えることが被相続人の推定的意思に合致する場合も多いと考えられるとして、相続人ではない被相続人の親族が、相続人に対して、その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるとする特別寄与料の制度(民1050条)を設け、前記貢献をした者が遺産の分配を受けることができないという不公平を解消させることとしました。
本件において、亜季さんの夫隼人さんは、被相続人の信太郎さんより先に死亡しているため、相続人ではない亜季さんの貢献は、亡隼人さんの履行補助者として評価することができず、亜季さんが相続財産の維持に貢献したとしても、相続財産の分配にあずかることができません。特別寄与料は、こうした相続人ではない被相続人の親族が被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者を保護しようとする制度なのです。
*******************************
亜季は、看護師だったし、遺産が欲しくて看護をしたわけではなかったので、鈴木の説明を聞いてもピンとこなかった。
「お金を請求するなんて…そんな気持ちにはなれないです」
「そういう方法もあるということだから。まあ調停が始まってからでも、法律の規定した期限内なら申立てはできますので」
「お父さんだって、遺言書に大変世話になったと記載して感謝していたんだから、遠慮なく請求してもらっていいのよ」
祐人もうなずいた。しかし、亜季は愛子の話に迷った。確かに、遺言書には財産を残してくれるような記載はあったけど…。
「皆さんのお気持ちはよく分かりました。少し考えさせてください」
「亜季さんの意思を最大限に尊重するよ。僕らに気を使わずに申し立ててもらっても構わないから」
祐人も亜季を後押した。
「調停期日は来月だから、それまで、俺の方で、もう一度遺産の範囲や評価額を確認しておくよ」
鈴木弁護士は、祐人らを事務所の玄関まで見送った。
【続く】
片岡 武
千葉法律事務所 弁護士(元東京家庭裁判所部総括判事)
細井 仁
静岡家庭裁判所次席書記官
飯野 治彦
横浜家庭裁判所次席家庭裁判所調査官
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】