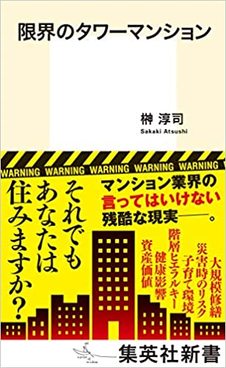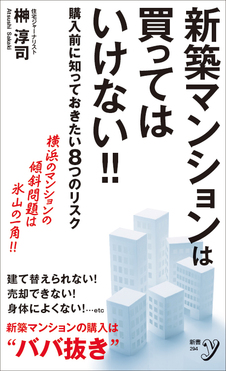雨漏りが放置された住戸には資産価値がなくなる
当然、そういうタワマンからは引っ越していく人が多くなる。
また、雨漏りが放置された住戸には資産価値がなくなる。
さらにいえば、区分所有者の中には必要な外壁の補修工事がなされないことを理由に管理費や修繕積立金の支払いを拒む人もいるかもしれない。
それはすなわち、廃墟への道ではないか。
このままでは2037年前後に複数のタワーマンションが廃墟化するかもしれない。それは、今の状況が続く限り、かなり確実性が高い未来である。
それを防ぐには、修繕積立金を値上げして管理組合の修繕積立金勘定に余裕を持たせるしかなさそうだ。
こうしてタワーマンションは、ますます維持管理コストが高い住まいになっていく。
しかし、これでもまだ、「うちのタワーマンションは大丈夫だろう」と高をくくっている人もいるだろう。そう安心もしていられない衝撃的なデータがある。2018年12月8日号の週刊東洋経済「マンション絶望未来」という特集の中で、みなとみらい、横浜、武蔵小杉、月島、勝どき、品川、豊洲の6エリアのタワーマンションの修繕積立金の推計値を算出しているのだが、先に紹介した国交省のガイドラインに示された修繕積立金の下限値さえも下回るタワマンが8割強であったという。
この章の冒頭でも示したように、何とか1回目の大規模修繕をクリアしたとしても、2回目、3回目は、そう簡単にはいかないかもしれない。ことによると、臨時徴収金をめぐって住民間の対立を招く可能性も高い。うまく合意形成できればいいが、規模が大きいほど、困難になることは間違いない。
このように大規模修繕の困難さや多額の費用負担を考えると、タワーマンションという住形態は果たして本当に効率的なのか、大きな疑問が生じてくる。むしろ、時間が経てば経つほど区分所有者に大きな負担を強いる時限爆弾のような住形態ではないだろうか。
デベロッパーは、そんなことなど一切考えていない。作って売って、儲かればいいのだ。売った後は基本的に区分所有者の責任。品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で、新築であれば、引き渡しから10年を過ぎると、すべての保証を免れる。大規模修繕工事を辞退することも可能だ。
このような住形態であるタワーマンションとは、購入した人を本当に幸せにするのだろうか。
榊 淳司
住宅ジャーナリスト
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】