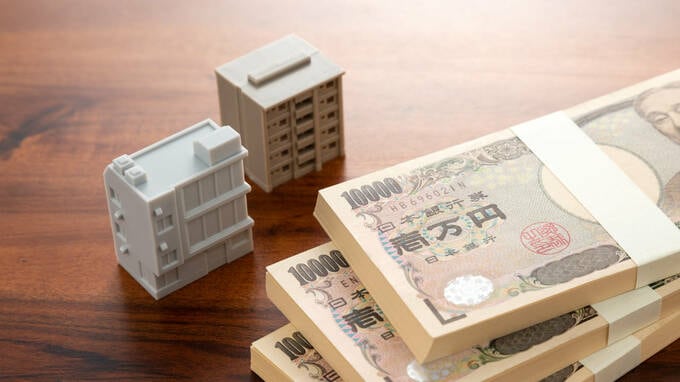遺産分割協議で寄与分を主張され、もめることが多い
本記事では、相続トラブルが起こった場合、一般的にどのような手段で解決が図られることになるか、また、その際にどのような問題が起こりうるのかを、争続の実態を踏まえつつ、確認していきます。
まず、相続財産をどのように分けるかを決めるために、相続人の間で「遺産分割協議」というものが行われることになります。
遺産分割協議では、相続財産の分割方法について相続人それぞれが好き勝手に主張することが少なくないので、話し合いがすんなりまとまるとは限りません。ことに、「寄与分」の主張をする者が現れた場合には、協議が紛糾し、大きくもめる可能性が高くなります。
相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に、特別の貢献をしたような人がいる場合、その人の「貢献度」に応じて相続分をプラスする仕組みが法律で設けられています。このプラスされる相続分を寄与分と言います。
たとえば、親が亡くなったような場合に、「一緒に暮らして面倒を見てきたのだから、自分には寄与分があるはずだ」などというような主張が、相続人の一人からなされることがよくあります。
このような主張がなされる背景には、「他の兄弟姉妹はみな家から出てしまい、私だけが親の世話をしてきた。だから、他の人よりも多く相続するのは当然だ」という思いがあるようです。
しかし、寄与分が認められるためには、前述のように特別な貢献が必要です。ただ世話をしていたという程度では十分ではなく、病床に付していた親を常時介護していたなどの事情が必要なのです。
しかも、仮に、「親は認知症だったので、朝から夜まで一日中介護をしていた」と主張できるような事情があったとしても、すんなりと寄与分が認められるわけではありません。ここが、往々にして争いの火種となるのです。
遺産分割協議で寄与分が認められるには相続人全員の同意が必要です。被相続人となる人がまだ健在のうちは、その面倒を見ている親族に対し、「苦労をかけるね」と、その労をねぎらっていたほかの親族も、いざ被相続人が亡くなり、遺産分割の段階になると、そうやすやすとは寄与分を認めないのが、世の常です。
その結果、寄与分を巡る争いは、ほとんどの場合、調停の場に持ち越されることになります。その際には、たとえば、「親はいつから認知症になったのか」「介護認定はいつ受けたのか」「どこの病院にかかっていたのか」など、介護にかかわる事実について、証拠となる資料を提出して一つひとつ具体的に事細かく証明することが求められます。
このように、寄与分は立証が容易ではないことから、認められることはなかなか難しいと思っておいたほうがよいでしょう。
寄与分の主張に対して「特別受益」の反論も
また、遺産分割協議で寄与分の主張がなされるケースでは、それに対する反論として、他の相続人から特別受益の存在が指摘されることも少なくありません。
相続人が被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けている場合、このような特別な受益のことを「特別受益」と言います。特別受益は、いわば“遺産の前渡し”と言えるので、遺産分割の際には、それに相当する額を差し引いて相続分が算出されることになります。
特別受益が問題となる場合、具体的には、「大学進学のときに学費を出してもらったじゃないか」「お前、確か、留学させてもらったときに留学費用を〇百万円もらっただろう」「姉さんは、結婚したときに家を建ててもらったでしょう」などという形で主張されることになるでしょう。

特別受益の存在や額は、寄与分に比べれば立証することが容易なので、認められる場合は多いでしょう。もっとも、特別受益分が認定される相続人は、結果的に、相続財産の取り分が減ることになるわけですから、納得できない思いを抱くかもしれません。
ことに、被相続人から生前に現金を譲り受け、購入した不動産が特別受益とみなされるようなケースでは、強い不満を持つ相続人が現れる可能性があります。
たとえば、バブル期に被相続人から1億円の生前贈与を受け、不動産(土地)を購入した相続人がいたとします。その後、その不動産が、地価が下落したために現在は3000万円の価値しかもたない場合であっても、特別受益とみなされたときは、原則として相続分から受け取った現金の1億円が引かれることになります。
その結果、仮に残された相続財産の総額が1億円であり、2人の相続人でそれを分けるという状況の場合には、生前贈与を受けている側は、現金の形で1億円をすでに得ていることになるので、相続財産からは受け取ることができないことになるのです。
特別受益は基本的に「相続開始時の価格」で計算される
先の例のように、生前贈与を現金で受け取り、土地を購入した場合、特別受益分を引かれてしまう相続人の立場からは、1億円の土地はすでに3000万円の価値しかないのですから、「特別受益を認めるにしても3000万円で評価すべきだ」と言いたくなるかもしれません。
ただ、この生前贈与が土地で行われていた場合は話は別です。特別受益の額はあくまでも相続開始時の評価額で算定されることになっているからです。
贈与時に比べ、贈与された物の価値が下がっているような場合、つまり、数十年前に生前贈与を受けたときに1億円だった土地が、今は3000万円以下になっているという場合でも、特別受益は相続開始時の価格で計算されます。
このような場合には、むしろ、他の相続人から、「1億円の土地をもらったのだから特別受益として1億円を引くべきだ」などと主張される可能性があるかもしれません。しかし、特別受益として引くことができるのは、3000万円のみなのです。
このように、不動産の生前贈与が特別受益とみなされる場合には、その評価額を巡って、相続人の間で、見解が対立することがあるかもしれませんが、贈与時に比べ価値が上昇している場合であれ、下落している場合であれ、相続開始時の価額を基準にすることが基本となります。
葬式費用の出所に関しても、もめることが多い
遺産分割の際に、葬式費用に関して相続人の間でもめごとになることがしばしばあります。そのようなトラブルが起きる原因の一端は、「葬式代は相続財産から工面しても問題ないだろう」という誤った思い込みにあります。
葬式費用は、基本的には、喪主が負担すべきものとみなされています。したがって、葬儀に必要な諸費用を、他の相続人のことわりなく、被相続人の預貯金から引き出すなどして支払うことは、法的には問題のある行為とも考えられるのです。
こういうと、「葬式費用は、相続財産から引けるのでは?」と思う人もいるでしょう。確かに、葬儀は被相続人を弔うために行うものであることから、何の疑問も持たないまま、被相続人の財産だった相続財産の中から葬式費用を出してしまうのも無理はないかもしれません。もちろん、相続財産から葬式費用を控除することはできます。
ただ、問題なのは、誰の断りもなく勝手に使うところにあるのです。
他の相続人の立場からすれば、自分に分配されるはずの相続財産を、承諾なく使われてしまうわけですから、やはり異を唱えたくなるでしょう。不満を持った相続人が葬式費用に使われた相続財産の返還を請求してくることは珍しくありません。
さらに、戒名料などは領収書が発行されないこともあるので、「実際には支払っていないのではないか」などと相続財産の横領まで疑われることもあります。このような葬式費用を巡るトラブルは、そもそも、相続人が、「相続財産から葬式費用を出してくれ」「生命保険金のうち〇〇万円は戒名料に充てるように」などと生前に意思を伝えていたり、あるいは遺言書の中にその旨を書き記してさえいれば、容易に防げるはずのものです。
しかし、遺言書が残されているような場合でも、なぜか葬式費用に関しては触れられていないことが多いのが現状です。