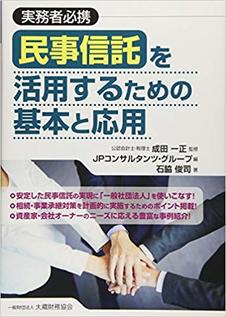\3月20日(金)-22日(日)限定配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処法
「個人受託者」は代替性の確保、継続性に問題あり
Q 個人が受託者の場合、何が問題となるのか?
A 個人が受託者の場合、死亡や能力喪失などの理由により受託者が信託事務を継続することできなくなるリスクがあります。信託事務が継続できなくなると、信託目的の実現が不可能となり、信託が機能しなくなります。
Point
□個人ゆえに継続性・代替性に問題がある
□個人には突然の死亡や事故のリスクがあり、それに対応できるよう後継受託者を確保することは難しい
個人(自然人)は、思わぬ事故等で突然死亡することがあります。また、事故、病気、高齢などの理由から、信託財産を管理する事務能力を喪失することも考えられます。
死亡や能力を喪失することがなくても、信託事務を担うことができなくなることもあります。例えば、父の財産を管理する信託について、受託者を長男とした場合、長男が現役世代であれば、主たる仕事を有しているでしょう。長男が会社員であれば、突然の転勤という事態も考えられます。遠方に転勤したからといって、すぐに受託者を変更することはなかなか困難です。
個人を受託者とする場合、第二受託者を信託契約に定め、死亡等の理由で個人受託者が不存在になることに備えます。しかし、それでも万全とは言えません。第二受託者として予定していた者が、受託者の就任を引き受けるか否かは、その時点での判断となります。当初は承諾していても、いざ、となったら引き受けてもらえないとのこともあり得ます。また、第二受託者が不運にも能力を喪失又は死亡していることもあります。個人から個人へのリレーを想定した場合、受託者不存在となることに対して万全な対策とは言い切れません。
個人が受託者となる場合、その個人受託者の代替性が確保できないという問題があります。
信託を設計する際、個人受託者のリスクを十分に考慮して信託を検討するのが、当然の実務です。しかし、民事信託において、受託者が個人である限りそのリスクを完全に排除することはできません。常に、個人受託者の代替性の課題を抱えながら信託は継続していかざるを得ないということが、民事信託における大きな問題点といえます。
<受託者の任務の終了事由>(信託法第56条第1項を抜粋)
1.受託者である個人の死亡
2.受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
3.受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く)が破産開始の決定を受けたこと
4.受託者の辞任(委託者及び受益者の同意を得て辞任するなど、信託法第57条の規定による)
5.受託者の解任(委託者及び受益者の合意による受託者の解任など、信託法第58条の規定による)
6.信託行為において定めた事由
法人を受託者とする民事信託を設計する方法
Q 個人受託者の問題点を解決するためにはどうしたらよいか?
A 法人を受託者とする民事信託を設計します。法人が受託者となれば、個人が突然に亡くなることなどで受託者が不存在となり、次の受託者へと交代しなければならないリスクを回避することができます。
Point
□法人が受託者となることで継続性を確保する
□法人受託者の場合、家族以外の他者の関与も可能となる
特定の個人は死亡等のリスクがありますが、法人は死亡のリスクはありません。一方、法人は倒産のリスクがあります。
法人を受託者とする場合、法人の倒産リスクを限定することができれば、受託者の継続性の問題はクリアすることができます。倒産リスクを排除するために、その信託の受託だけを目的とする一般社団法人を設立することを考えます。新設した一般社団法人は、引き受けた信託の信託事務だけを行うことで、ほぼ倒産リスクはなくなると考えます。
法人が受託者となる場合、信託業法の問題が生じます。信託業法第2条第1項には、「信託業とは、信託の引受けを行う営業をいう」とあり、同法第3条には、「信託業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない」との定めがあります。信託の引き受けを業とする、すなわち「営業する」とはどのような状況をいうのか?について議論があります。家族のための信託を1回だけ受託するのであれば、それは「反復・継続」して引き受けることとはならず営業にあたらない、という説があります。
たしかに、1回だけであれば、「反復・継続」しないので、信託業法に抵触しないと思われます。しかし、1回だけ信託を引き受け、それにより受託者法人が利益を得ることを目的とするならば、営利を目的とすることに抵触します。引き受けの回数の問題でもないように考えます。信託の引き受けにあたりその実態をふまえ、業にあたらない信託の受託者として法人を活用することが必要です。
受託者を法人とした場合、信託事務を担う者の選択肢と代替性に広がりがでます。個人を受託者とした場合、委託者の家族が受託者の候補者になりますが、法人を受託者とした場合、家族以外の者が信託事務を担当することも可能です。その者を財産管理の専門家とすることもできます。法人内の誰に業務を担わせるか? そしてその者をどのように監視するガバナンス体制を作るのか?これらは、法人内での担い手や機関の設計の問題となります。
現行の信託業に対する規制の対象は、信託の引受けの「営業」と規定され、反復継続性・収支相償性が要件と解されているが、この反復継続性の要件については、不特定多数の委託者・受益者との取引が行われ得るかという実質に則して判断されているところである。
現行の通常の信託については、特定少数の委託者から複数回信託の引受けを行う場合には、反復継続性があるとは考えず、信託業の対象とはしていないが、これは、反復継続性を不特定多数の委託者ひいては受益者との取引が行われ得るかという実質に則して判断していることによるもの。例えば、今後、事業会社が他の会社の事業を複数回受託する場合についても、不特定多数の委託者を予定していない場合には、信託業法の対象とはならないと考えられる。
株式会社等は民事信託の受託者としては不適切
Q 株式会社等が民事信託の受託者となれるのか?
A 会社法上の会社(株式会社、持分会社)は民事信託の受託者にはふさわしくありません。
Point
□株式会社は利益を追求する法人のため民事信託の受託者となることは難しい
会社法第5条には、「会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする」との定めがあります。また、商法第503条第1項には、「商人がその営業のためにする行為は、商行為とする」、同条第2項には、「商人の行為は、その営業のためにするものと推定する」との定めがあります。
すなわち、会社法上の会社である株式会社と合同会社は、営業のために商行為を行うため、営利を目的としない民事信託の受託者として信託事務を行っていくことに矛盾が生じます。特定の者の信託を1回だけ受託するとしても、筆者の実務では株式会社と合同会社が民事信託の受託者となることを避けるようにしてます。
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/12開催】弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方