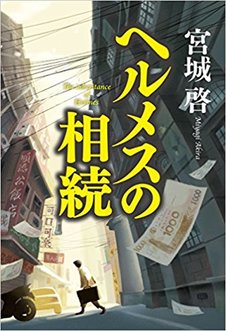盛りのついた猫の唸り声が耳についた。風が一段と増し、雨戸がガタガタと鳴りやまない。どうしようもない焦燥感が、定吉の胸を襲った。
額の汗を乱暴に拭い、落ち着きのない表情で真っ暗な空を見上げる。まだだろうか。もう終わってもいい頃じゃないか。
灯籠の灯が、今にも消えかかっていたちょうどその時だった。
「ギャー」
獣の叫び声だろうか。定吉は辺りを見回した。山ではない、家の中からだ。まずい。見つかったか。
夜陰に紛れて盗みに入り、山中に逃げ去ると聞いている。こんな田舎なら警察だっていないし、隣家だって遠く離れているから心配いらないと言っていたのに。
ウォーというけたたましい咆哮が、耳を貫いた。
廊下をドタドタ走る音。バタンという雨戸の倒れる音。それに混じり、絶叫が続けざまに母屋から響き渡る。
定吉の胸が張り裂けそうに高ぶった。麻の白シャツが、汗でべっとりと体に張り付く。顎の震えが収まらない。
きっと、家の中ではまずいことになっているんだ。乱闘になっているのかもしれない。
その瞬間、パチパチと何かが弾ける音が聞こえ、煙のくすぶる臭いがしだしたかと思うと、裏手から火の手が上がったのが見えた。海からの強風で見る見るうちに勢いが増し、炎が空に舞い上がる。いきり立つ炎は暗闇を真っ赤な地獄へと変え、屋敷のすべてを飲み込もうとしている。
全身が炎にあぶられ、定吉はとたんに目の前の惨状に恐れをなした。
いったいどうなっているんだ。なぜ火が上がっている。盗みだけじゃないのか。
「おい、逃げるぞ!」
連れの男の声がした。裏口から駆けて来たようだ。その背後に二人の人影。両方とも男だ。一方は片足を引きずっている。その男と目が合った。なんであいつがここに。
「おい、何やってんだ。急げ!」
連れの男は焦っていた。背後の二人は林の暗がりに消えようとしている。もう一人、跪(ひざまず)いて苦しそうに嘔吐している男の姿が見える。炎で照らされた彼らの全身が、血潮で真っ赤に染まっていた。
「どうしたんだ。奴ら、血だらけじゃないか」
定吉は腰が抜け、身動きできなかった。
「そんなことはどうでもいい。早く逃げるぞ!」
連れの男が定吉の腕を掴み上げる。
それを振りほどき、恐る恐る声を出した。
「殺(や)ったのか?」
男は舌打ちし、唾を吐き捨てる。
「おい、答えろよ」
その時、定吉の視線があるものを捉えた。
燃え盛る炎の中に何かがある。
定吉は立ち上がり、じっと見つめる。
声が出なかった。身動きできず、ただそれを見ていた。
人だ。崩れた建物から這い出たところで、力尽きているんだ。
髪も衣服も焼け焦げ、身体全体が真っ黒になっている。
「勝手にしろ」
男は定吉を置いてその場を去った。