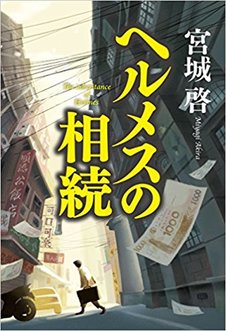あの事件後、東亜監査法人を辞め、財務コンサルティングの個人事務所を始めた。上司からは引き留められたが、もう大組織は懲り懲りだった。事務所の営業は細々としたもので、一人がやっと食っていける程度だ。タバコを吹かしながら暇な一日を過ごし、忘れた頃にやって来る下請け作業をやっつける日々。企業の財務分析、開示資料の作成。まともな仕事などめったにない。公認会計士といっても、この世には掃いて捨てるほどいるのだ。
これでもつい数年前は、億の年収を稼ぐ、浮かれた男だった。だが今はこの様だ。
とはいっても、またあの伏魔殿には戻れない。俺の精神は、そんなにタフじゃない。今の生活が性に合っていると、自分を慰めながら暮らすほかない。
岸は、デジタル時計の日付表示を見た。あと五日で月末。天の助けか。喉から出そうな手を口の奥で止め、乾いた声でアポイント時間を告げた。
岸の事務所は、高田馬場駅から早稲田通りを明治通り方面に数分行った先の、雑居ビルの三階にある。このエリアはエスニック料理の密集地と呼ばれているが、このビルも同様だ。上階のミャンマー料理店と下階のカンボジア料理店に挟まれ、東南アジア人にはたいそう人気の場所だったが、専門サービス業の事務所には人っ子一人寄りつかず、閑古鳥が鳴いていた。「これじゃあ、まるでタイだな」友人に言われ、改めて世界地図を見ると、確かに彼の言う通りの場所だった。
一週間ぶりにジャケットを羽織り、自宅を出る。落合駅に向かう途中、携帯で永友に電話したが、応答がなかった。本当に知り合いなのだろうか。
高田馬場駅で降り、事務所のビルの前に着くと、辺りをきょろきょろしている白人女性と目が合った。
「岸さんですね。レイラです」
ネイティブに近い日本語だ。年齢は二〇代後半。肩に少しかかるくらいの赤茶色のストレートヘア。真っ白なノースリーブからは盛り上がった胸部。真っ赤なショートパンツからは大腿部が露わに見える。背丈はそれほど高くない。日本人女性の平均よりもちょっと高めといったところか。肩から掛けたブランド物のトートバッグと、品のいい香水の香りから、まともな女の匂いがした。だがその一方で、何となく嫌な予感が漂っている。口ばかり達者で自己主張の強い白人女しか、今までに会ったためしがない。
岸の勘が的中したのは、三階の事務所に足を踏みいれた時だった。
「うわー、臭い! こんな臭いところで話なんかできないわ」
汚物でも見るような表情で口と鼻を手で覆い、事務所の奥の窓を勢いよく開けて、外に向かって深呼吸を始めた。
面倒な女だ。白人は自分たちが世界で一番偉いと思っている。そんな奴らを相手に、商売などしたくない。
「悪いが、ここは飲食店じゃない。分煙に気を遣う場所が好みなら、他を当たってくれ」
「何よ、その言い方」
挑むかのような態度で岸を睨みつけた。だがそれ以上は反論せず、事務椅子を窓の下に寄せると、ドカッと腰を下ろした。諦めないところを見ると、切羽詰まった状態なのだろう。
すべての交渉事において、その力関係は最初で決まる。下手(したて)に出るとそれがいつまでも尾を引く。こき使われ、値切られ、支払を無視される。だから最初が肝心だ。自分を大きく見せろ。有利な条件を引き出せ。相手の弱みを握れ。かつてのアメリカ人上司から教え込まれたやり方だ。奴らがよくやる手だ。
岸は応接用ソファーに腰を埋め、これ見よがしにタバコを取り出して火をつけた。彼女の目の奥が、驚きと憎しみが混ざった色に変わった。