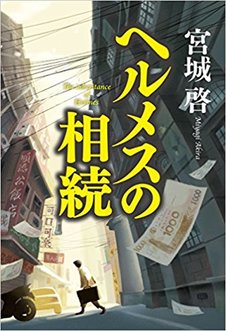平成二七年──盛夏
1
けだるい朝だった。岸一真(きしかずま)は、ラッキーストライクに火をつけ、目覚めたばかりのいがらっぽい気管に、最初の一服を流し込んだ。昨晩の酒のせいだ。まだ身体中に沁みわたってやがる。
重い身体を起こし、リビングの窓を開ける。ムッとする熱気が、今日一日のやる気を削ぐ。
嫌なものが目についた。ベランダの隅。相変わらず鳩の糞が溜まり、手が付けられない有様だった。見るんじゃなかった。
信号が変わったらしく、ふいに山手通りの車のエンジン音が耳につく。タバコの煙が混ざったため息を、排気ガスと騒音がばら撒かれた白い空に吹きかける。その瞬間、胃がムカつきを起こした。昨日は何を食べたっけ。考えるのも面倒だ。そんなことはどうでもいい。
窓を閉め、玄関から持ってきた新聞を広げた。今日も、総合電機メーカー西芝電機の不正経理の記事が躍っている。馬鹿な連中だが、馬鹿でない人間はこの世にいない。こんなことが延々と繰り返されるのは、むろん当たり前のことだ。
新聞のページを捲る。
もうすぐ始まる二〇一五年ラグビーW杯の、みすぼらしい記事を読んでいた時、携帯電話が着信を告げた。手に取ると未登録の電話番号が表示されている。どうしようか迷ったが、暇つぶしになるかもしれないと電話に出た。
「岸さんですか?」
聞き覚えのない声だ。流暢だが、何となくイントネーションが気になる。歳は若そうだ。昨晩行った歌舞伎町のスナックのホステスか。不法入国の中国人やフィリピン人をホステスとして働かせている、ちんけな店だった。だが、あそこでは名刺は渡していないはずだ。それに、名刺には携帯番号は書いていない。
岸は「そうだ」と答える代わりに「誰だ?」と言った。
「私、レイラといいます。岸さんですよね? 頼みたいことがあります」
女は焦っていた。早口だが、それでもはっきりとした口調だった。
「ちょっと待ってくれ。俺はあんたを知らない」
「永友さんから連絡がありませんでしたか?」
意外な名が出て、岸は意表を突かれた。永友といえば、永友武志しか知らない。監査法人勤務時代の上司で、次期CEOと目されている経営メンバーの大物。岸が最も信頼を寄せている、恩人と呼べる人物だ。
「東亜監査法人の永友さん?」
「ええ、そうです」
「まだ何も連絡は受けていないが」と言った後、朝起きて携帯の電源を入れた時、着信履歴の表示が一件あったことを思い出した。あれがそうだったのだろうか。
「とにかく会って話を聞いてください。お願いします。どこにでも行きます」
相当、浮足立っている声音だった。
「それは仕事なのか?」
「ええ、そうです。あなたに仕事を依頼したいと思っています。報酬はちゃんとお支払いします」
それを聞いて頭を過ったのは、月末までに支払わなければならない借金と、暴力団よりもたちの悪い、弁護士からの取り立てだった。