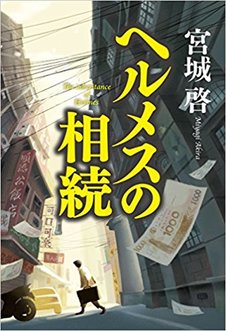2
喧噪の夏が、ようやく去ろうとしていた頃だった。
夕凪がいつしか強風に変わり、湿った風が裏山の竹藪をざわつかせている。
見張り役を任された定吉(さだきち)の気分は、最悪だった。
昼間なら見晴らしのいい海岸沿いの別荘地は、辺り一面、真っ黒な海と同化して、深い谷底に引きずり込まれるような恐怖感でいっぱいだった。不気味な風音が耳の中で鳴り響き、竹藪のカツーンという音が頭の中を貫く。そんな暗闇の中、灯籠の灯が頼りなく照らす玄関口を、息を殺してずっと見張っているのだから気が落ち着くわけがない。
もう小一時間は経っただろうか。いや、まだ三〇分ぐらいしか経っていないのかもしれない。気が焦り、何度も舌打ちをしながら、彼は自分の馬鹿さ加減を悔やんでいた。なぜこんなことを引き受けてしまったんだ。
定吉は、今までの己の薄幸を思い起こした。
満州から命からがら引き揚げてきた自分を待っていたのは、焼け野原となった東京と、許嫁(いいなずけ)である舞子の死の知らせだった。昨年三月の空襲で東京は火の海になり、舞子はその犠牲となったと聞かされた。
定吉にとって、荒涼とした満州の地で思うのは、内地に残した舞子のことだけだった。生きて帰りたい。死の淵を彷徨(さまよ)いながらも、そう強く念じて必死に生きた。
忘れようと思っても、ふと気付くと舞子との思い出が頭に浮かび、定吉の胸を締め付ける。
初めて舞子を見た時の胸の高鳴り。将来を誓い合った時の喜び。そして最後に会ったあの日のことは、決して忘れることができない。
あれは、お国のために戦地に赴く前日だった。蛎殻(かきがら)町の小さな神社で、人目を忍んで逢引したことが、昨日のことのように思い出される。鳥居の脇には、昨晩から降り積もった雪の間から、薄桃色の梅の花が一輪顔を出していた。
「あ、可愛い」
舞子が無邪気に喜び、顔を近づける。うなじが寒さに震えているようだった。
「こんなに寒いのに、梅って咲くんだね」
「紅冬至よ」
「ベニトウジ?」
「ええ、冬至の頃に咲く、早咲きの梅なの」
「冬に咲く梅か。それも雪の中で咲くなんて。可憐ですぐ散ってしまいそうだけど、我慢強いんだな」
真っ白な雪に浮かび上がる淡い桃色は、より一層映えて美しい。寒さに耐えながら、しっかりと咲いているその姿を見て、彼女は言った。
「私もこの花のように、辛抱して定さんの帰りを待っています」
あの時の言葉が、今でも頭から離れない。
「きっと戻ってくる」
その時、そう言って舞子を見つめ、手を握った。女中奉公でひび割れた指は、氷のように冷たかった。
「私、毎日定さんに陰膳をして、無事に帰ってこれるように、ここに御参りに来ます」
薄紅色の小さな唇から白い息が漏れている。透き通るような白い肌は寒さに凍え、今にも壊れてしまいそうなほど繊細に見えた。彼女は懐から白布を取り出し、定吉に差し出す。五銭硬貨が縫い付けられた千人針だった。定吉はそれを握りしめ、涙をこらえながら彼女の細い身体を抱きしめた。絶対帰ってくる。そう心に誓った。
しかし、待っているはずの彼女はもうこの世にいない。せめて亡骸(なきがら)だけでもと思うのだが、おびただしい数の行方不明者の中から、彼女を捜し出すことは不可能だった。
こんなことなら満州でくたばっていればよかったんだ。何のために戻ってきたのかわからない。やり場のない怒りと悔しさが彼を自暴自棄にさせ、仕事にもつかず、新宿の街で盗みやひったくりを重ねているところを、闇市を取り仕切るヤクザの目に留まった。
盗みに入るから見張りをやってくれと頼まれただけで、あんな大金をくれるわけがない。まずいことに巻き込まれなければいいがと思いながらも、生活がかかっているから仕方がないと割り切っていた。だが、こんな田舎くんだりまで遠出して、おまけにこんな闇夜にずっと見張り役なんて、話が違うじゃないか。それになんだか大掛かりなのも気にかかる。連れの男は裏口の見張りをやらされ、家に入った実行班が別にいるらしい。でも、そもそもこんな別荘に金なんかあるのだろうか。もう東京行きの最終列車は行ってしまったから帰りたくても帰れない。投げやりな気持ちになって、また玄関口に視線を運んだ。