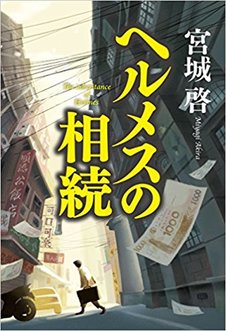定吉は思わずその者に駆け寄り、身体を引きずって何とか火元から遠ざけたが、すでに息がないようだった。死体など、何度目にしたかわからない。だが、内地に帰ってきてまで、こんなものを見るとは思わなかった。定吉の目に、戦場で逝った者たちの、無残な姿が浮かび上がる。両親や妻や子供を残して、はるか満州の地で犠牲となった多くの戦友が、今もなお、茫々たる大地にまみれ、風雨に晒されている。こいつにも親はいるだろう。妻や子がいるかもしれない。そう考えると、どうしようもなく虚しさが募る。またあの、辛く苦しい満州が頭を巡る。せめてこいつには成仏してもらいたい。定吉は手を合わせようと、横たわる遺体に近づき、その顔を見た。髪の毛が焼け縮れ、顔が煤で真っ黒だった。煙で息ができなかったのか、顎を突き出し、口を開けたまま固まっている。苦しみに喘ぐ顔だ。これ以上見ていられない。目を閉じ、合掌した。その目の裏に、真っ黒な顔が映り込む。どこかふっくらとした顔つき。女のようにも見えた。いや、女かもしれない。なぜか胸騒ぎがする。
目を開け、もう一度その顔を見た。何かが定吉の胸を突き刺した。まさか、そんなはずはない。
もっと近づき、恐る恐る凝視した。
そんな馬鹿な。なぜだ。なぜお前がここにいる。死んだはずのお前が、どうしてここにいるんだ。答えてくれ、舞子。どうしてここにお前がいるんだ。
頭が混乱し、自分の眼前で起こっていることがまったく理解できなかった。
これが夢であってほしいと念じた。きっと自分は幻を見ているのだ。
身体を横向きにし、顔を近づけて見た。自分の目に見えているものは間違いなく現実だった。死に物狂いで愛した女が、自分の目の前で焼け死んでいるなんて。
「舞子!」
定吉は泣き崩れ、拳を地面に思い切り叩きつけながら、自問した。
空襲で焼け死んだと聞かされたのに、いったいどういうことなんだ。あれだけの犠牲者の中、安否確認が取れなかったのはわかる。あの爆撃に晒されれば、命はまずないだろうと思うのも当然だ。空襲で死んだと、奉公先の知り合いが憶測で言ったのだとしたら、それも仕方のないことかもしれない。だが、舞子はここにいる。自分の目の前に、無残な姿で横たわっている。なぜこんなことが起きるんだ。
何とも言えないもどかしさと、様々な思いが頭の中で渦を巻き、破裂しそうなほど混乱した。
と、その時。霞む目に、何かが映った。なんだあれは。
目を擦り、顔を近づけて、それをじっと見つめる。
これは──