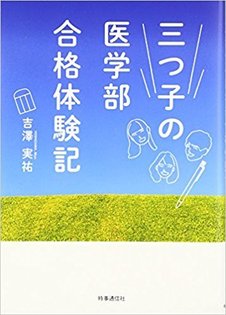「このクリニックを継ぎたい」
中学3年になると、逢香と大輝の中で「医師になりたい」という気持ちが芽生え始める。春子がことあるごとに医師の素晴らしさを語っていたこともあるが、ふたりにとって、父親の後ろ姿を見ていたことが大きかった。
敏行はただ診察をしているわけではなかった。患者さんが来れば、病気以外のさまざまな話をした。家族の話、趣味の話、嬉しかったこと、困ったこと、とにかくどんな話でも聞いた。生活習慣と病気は密接な関係があると考えていたからだ。病気を治すためには、あるいは予防するためには、患者の生活を知る必要があると思った。地域清掃があれば、積極的に参加した。そのため、いわゆる「お高くとまる」と思われたことがない。敏行は自身の活動を、「どぶ板選挙」をもじって、「どぶ板医療」と言う。
多くの書物を読み、気になれば講演会にも出かける。「うちの子が不登校になってしまったんだけど、先生、何とかしていただけませんか?」と相談され、真剣にカウンセリングを学んだこともあった。知識が豊富だということもあり、頼まれて学校のカウンセラーも引き受けていた。とにかく、地域のみんながあらゆることで頼りにする医師だったのだ。
逢香はどちらかといえばおばあちゃん子だ。その祖母がいつも、「病院に行っても、医者がちゃんと話を聞いてくれない」「何か質問をしても、バカにされる」と嘆いていた。その度に、「パパだったら、絶対にそんな思いはさせないはず」と思っていた。その思いが、中学3年にもなると、「私もパパみたいな医者になる」という強い決意に変わる。お年寄りや子どもが大好きな逢香らしい決心だった。
一方、大輝は「このクリニックを継ぎたい」と思っていた。インフルエンザや風邪はもちろん、心の悩みにまで向き合っている父親の姿に感銘を受け、いつか自分も何でも診られる医師になりたいと思ったのだ。
「県内で一番レベルが高い高校に行こう」
このご時世、生半可な勉強では医学部に合格できない。医学部に入るためには、偏差値が65以上必要だともいわれている。それがいかに大変なことか、ふたりは十分に自覚していた。だからこそ、「そのためには、県内で一番レベルが高い高校に行こう」と決めた。そこは県立高校だった。
医師になりたいと明確な将来像を見ていたふたりの陰で、舞香も密かに同じ高校を狙っていた。いつも逢香より成績がよかった舞香は、どんな模擬試験でもその高校の合格圏内にいる。担任も「舞香なら、余裕で合格するだろう」と思っていた。しかし、両親にも、担任にも「一番偏差値が高い高校を受験したい」とは言い出せなかったのだ。イギリス行きの時と同じように、「その成績で狙うの?」「無理でしょう」と言われやしないかとビクビクしていた。
いくら模擬試験で合格圏内にいても、「そのとき調子が良かっただけと言われたらどうしよう」「合格圏内といってもギリギリじゃないと思われやしないだろうか」と考えた。自分に自信がなかったのだ。両親が「県内トップの進学校を狙いなさい。舞ちゃんだったら合格するから」と言ってくれても、「うん」のひと言が言えなかった。
周囲からはいつも慎重だと言われる舞香。しかし、決して心が決まらずふらふらしているわけではなかった。実は、誰よりも先に決意し、人一倍熱い気持ちを持っていたのだ。しかし、それを言い出せない弱さがあった。今回も、逢香と大輝の希望に便乗する形で、狙っていた高校を第一希望にすることができた。