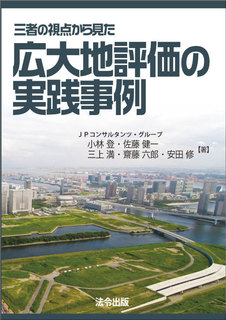前回に引き続き、共有持分・単独持分による「広大地評価」の差異について説明します。今回は、専門家の見解も併せて見ていきましょう。※本連載では、相続税対策を始めとするあらゆる資産税業務に精通したプロ集団、JPコンサルタンツ・グループによる著書、『三者の視点から見た広大地評価の実践事例』(法令出版)より一部を抜粋し、税理士、不動産鑑定士、元税務調査官の三者の視点から見た、広大地評価についての考え方・評価方法を事例をもとに解説していきます。
土地全体が共有の場合には、その土地全体が評価対象に
前回に引き続き、共有持分・単独持分による「広大地評価」の差異について説明します。今回は、専門家の見解も併せて見ていきましょう。
<評価担当者の見解>
広大地の評価は、土地に対して行う評価方法であり、土地全体が共有の場合には、その土地全体が評価対象となります。
各人が分筆登記を行い、それぞれが個別に取得した場合には、その取得した土地それぞれが一つの評価単位となります。また、一旦、共有登記で遺産分割を終了し、その後、必要に応じて共有物分割で各人が1,000㎡にしたとしても、広大地の評価にあたっては、5,000㎡を評価単位とします。
<不動産鑑定士の見解>
広大地として単一式により評価することは、鑑定理論では考えられないことです。共有持分であれば、全体の面積5,000㎡を基に広大地の評価を行い、各人に分筆登記をしていれば、各人のそれぞれの面積が、評価単位となります。
一人に帰属する面積が500㎡未満の場合は…
<元国税調査官の見解>
我が国の相続税法は、大陸法系に属し、その課税方式は「遺産課税方式」に法定相続分を加味させた「遺産取得者課税方式」を取っており、その法理論は三段構えとなっています。したがって、相続登記時において、未分割に基づく共有持分登記をした場合には、相続開始時の現状で判断します。
つまり、相続した土地面積が600㎡の場合は同面積で判断し、開発基準が500㎡の場合は(道路敷設が必要と判断)広大地に該当します。
なお、その後分割し一人に帰属する面積が500㎡未満となった時は、広大地に該当しないことになります。また、相続登記が遺産分割(共有持分登記を除く。)に基づく場合は、最初から各人の取得面積で判断することになります。
税理士法人JPコンサルタンツ
代表税理士
昭和46年東京国税局総務部・東京国税局管内税務署に勤務し、主として資産税関係事務を担当。平成8年神田署勤務を最後に退職、同年小林登税理士事務所開設。平成17年税理士法人トゥモロー・ジャパン設立。平成21年JPコンサルタンツ・グループ代表取締役に就任。平成24年待山会計事務所と経営統合を図り、組織再編された税理士法人JPコンサルタンツの代表税理士に就任する。年間100件を超す相続案件を手掛ける。
<主な著書>
『広大地の評価実務Q&A』(中央経済社)、『相続税・贈与税の実務土地評価』(大蔵財務協会)他多数。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載相続税対策のために知っておきたい「広大地」の評価事例
税理士法人JPコンサルタンツ 役員税理士
不動産鑑定士
平成10年7月、税理士登録。平成15年3月、不動産鑑定士登録。平成15年4月、税理士事務所開設。同年、有限会社アプレイザル・アルファ設立。平成17年10月、総合士業事務所の株式会社プライムを共同設立。平成18年3月、行政書士登録。平成26年4月、税理士法人JPコンサルタンツと税理士事務所の経営統合により、役員税理士に就任する。その専門性を活かし、鑑定評価及び相続税を中心とする資産税に力を注ぎ、多くの実績を有す。近年は税理士会・新聞社主催セミナー及び任意団体における研修会など、講演活動も精力的にこなす。
<主な著書>
『土地の税務評価と鑑定評価』(中央経済社/共著)、『広大地の評価税務Q&A』(中央経済社/共著)他多数。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載相続税対策のために知っておきたい「広大地」の評価事例