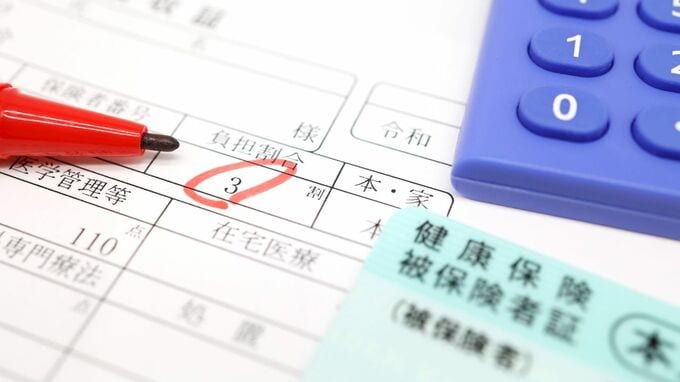後期高齢者医療制度が導入されるまで
そもそもなぜ、まるで高齢者いじめのような後期高齢者医療制度が誕生したのか。それを知るためには、わが国のこれまでの高齢者福祉政策を振り返ってみる必要があります。
戦後のわが国の高齢者対策は、1963年に制定・施行された老人福祉法からスタートしました。わが国が高度経済成長でめざましい発展を遂げていく過程で、日本社会の家族の在り方も急速に変化していきます。それまで、ごく普通に行われていた3世代同居という形が崩れ、若年人口が都市部に集中し、やがて核家族化していきます。
そうした社会環境の変化によって、それまではあまり一般的でなかった独居老人が増え、なかには介護を必要とする高齢者も存在するようになりました。かつては家庭内介護が当たり前でしたが、子ども世帯は地方から遠く離れた都会に暮らしているため、「要介護のお年寄りは社会全体で支えていこう」というコンセンサスが国民の間で生まれました。
その思いを法制化したのが老人福祉法であり、この法律の考え方に基づき、養護老人ホームや特別養護老人ホームなどの高齢者施設が整備されていくことになります。
老人福祉法第2条は、この法律の基本的理念を次のように定めています。
老人福祉法第2条【基本的理念】
老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経障されるものとする。験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。
今日運営されている後期高齢者医療制度が、この老人福祉法の精神に則のっとっているかどうかはさておき、少なくとも1963年の時点で、わが国の社会も法律も、高齢者をいたわる気持ちはあったようです。