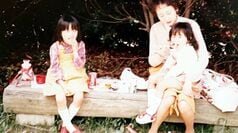Wikipediaの投稿に開示請求をする流れ
Wikipediaの投稿に対する開示請求は、どのような流れで進めればよいのでしょうか? ここでは、Wikipediaになされた投稿について開示請求をする一般的な流れを解説します。
投稿の証拠を保存する
Wikipediaに自身や自社を誹謗中傷する書き込みがなされたら、その場ですぐに投稿の証拠を保全します。開示請求を行うには、誹謗中傷など権利を侵害する内容の投稿がなされたことの証拠が必要となるためです。証拠がなければ、開示を受けることはできません。
投稿の証拠は、スクリーンショットで残すことが一般的です。Wikipediaの場合は、次の内容が載ったスクリーンショットを撮影しましょう。
・誹謗中傷が書き込まれたページのURL
スマートフォンではURLなどの表記が不完全となることがあるため、可能な限りパソコンで撮影するようにしてください。
弁護士へ相談する
投稿の証拠を残したら、できるだけ早期(可能であれば、その日中や翌日など)に弁護士へ相談します。相談の際はスクリーンショットを確認してもらい、不備があれば追加で証拠を残しましょう。
なお、Wikipediaでの誹謗中傷に関する開示請求には、法律のみならず手続きに関する知識や経験が必要です。そのため、弁護士の中でも、誹謗中傷問題に強い事務所を選んで相談することをおすすめします。
開示請求をする
一定の手続きにより、投稿にかかるIPアドレスなどを入手します。
アクセスプロバイダに開示請求する
次に、Wikipediaから入手したIPアドレスやタイムスタンプなどの情報をもとに、投稿者が接続に用いたプロバイダ(KDDIやNTTなど)に対して契約者情報の開示を求めます。
裁判手続によって行うことが一般的です。
開示請求が認められると、プロバイダの契約者の住所や氏名が判明します。
注目のセミナー情報
【国内不動産】4月26日(土)開催
【反響多数!第2回】確定申告後こそ見直し時!
リアルなシミュレーションが明かす、わずか5年で1,200万円のキャッシュを残す
「短期」減価償却不動産の節税戦略
【資産運用】5月10日(土)開催
金価格が上昇を続ける今がチャンス!
「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資