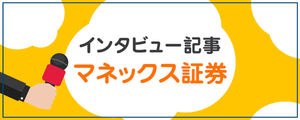※画像はイメージです/PIXTA
※画像はイメージです/PIXTA
【関連記事】
人一倍敏感な子ども「HSC」…特徴と周囲との上手な向き合い方【臨床心理士の監修】
不登校は年々増加している?
不登校の子どもの数は年々増加の傾向にあります。ここ最近ではコロナ禍が大きな原因ですが、コロナの流行以前からも不登校の数は増えていました。
不登校が増加している原因のひとつは、時代に合わない詰め込み学習や、多すぎるクラスの人数、先生の多忙などにより、学校が子どもにとって適応しにくい環境になってきていることです。
そのほか、現在普及しているインターネットは親世代の人たちの幼少期にはなかったため、子どもへのネットリテラシーの教育がまだ手探り状態であること、長引く不況で親御さんたちがお子さんにかけられる時間や心理的あるいは金銭的な余裕が少なくなり、家庭の中での子育て力が低下していることも、不登校の増加に影響していると考えられます。
また昔に比べると、不登校は悪いことではなく、無理に学校へ行かせなくてもよいというように社会的な認識も変化しています。
不登校の3つの原因とは
不登校の原因は大きく3つに分けられます。
不登校の原因①:学校の問題
友だちや先生との人間関係で不適応が生じている場合です。
不登校の原因②:家庭の問題
昼夜逆転など基本的な生活習慣が乱れていることや 、親子の信頼関係が揺らいでいる場合などが挙げられます。
不登校の原因③:子どもの問題
不安症や発達障害 など、お子さんが持っている特性に基づくものです。実際、発達障害の子どもは不登校になる割合が3~5倍ほど高くなり、不登校になったのでクリニックに行ってみたら発達障害がわかったというケースが多くあります。
不登校の子どもの心理状態
学校に対する不安や恐怖が原因で 、学校へ行けなくなるお子さんが多いです。その結果、社会や人との家族以外のつながりがなくなってしまって、孤立感や疎外感を感じる子どももいます。
一番よくないのが自己否定感です。「どうして学校に行かないの」など自分でも答えられない質問を投げかけられると、「みんなとは違う」といわれているような感じがして、自己肯定感や自尊心が下がります。学校へ行けないため 、集団生活の中での達成感や成功体験を得る機会が少なくなってしまい、それがさらに自己肯定感の低下につながるという悪循環に陥ってしまいます。「どうせ私なんて」という言葉が出てくると要注意です。
抑うつ状態になったり、ストレスによる身体症状が出ることもあります。
親が気をつけたい6つのポイント
不登校にならないように、あるいはすでにお子さんが不登校である場合は改善できるように、以下のことに気をつけてみてください。
①甘やかすことと寄り添うことを間違えない
子どもの言うことを何でも聞いて甘やかしてしまうと、学校へ行って自分の言うことを聞いてもらえない環境に置かれたときに、うまく適応できなくなってしまうことがあります。お子さんが自分で問題を解決する力が育つよう、寄り添ってあげましょう。
②子どもとかかわりを持つ
子どもとのかかわりが少ないと、親子の信頼関係がうまく構築できなことがあります。普段からの声掛けなど、意識してやってみてください。
③原因を多面的に考える
お子さんが学校に行きたくない理由として、たとえば「先生が嫌なことをいう」などと訴えると、親御さんとしてはつい、学校に問題があるのだろうと受け止めてしまいがちです。しかし、お子さんの訴えはひとつのきっかけであることが多く、学校へ行きたくない原因はほかにもある場合があります。不登校のおもな原因が、学校、家庭、本人であることを念頭に、いろいろな角度から原因を考えてみてください。
④子どもを自由にさせ過ぎない
子どもが自由過ぎると、親子関係が希薄になったり、子どもがなんでも好きなようしていいのだと思ってしてしまう可能性があります。適度なルールを作るなど、お子さんとコミュニケーションが取れるようにしましょう。
⑤子どもの間違った行動に対してははっきりだめだと言う
子どもをれないと、親子の立場が逆転して、親の言うことを聞かなくなってしまいます。子どもの間違った行動には、はっきりと間違いであることを伝えましょう。
⑥子どもへの対応に一貫性を持つ
子どもが同じことをしても怒ったり怒らなかったり、そのときそのときで対応が違うと、子どもは戸惑ってしまいます。一貫性を持った対応で、子どもとの信頼関係を築きましょう。