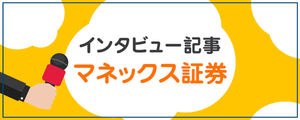※画像はイメージです/PIXTA
※画像はイメージです/PIXTA
【コペル育児ワールド】
今すぐ子育ての役に立つ「情報サイト」ほかの記事も読む>>>
(外部のサイトに遷移します)
HSCの4つの特徴【DOES】とは?
HSC(Highly Sensitive Child)とは、アメリカの心理学者であるエイレン・N・アーロン博士によって定義された概念で「非常に敏感な子ども」を意味します。
博士によると「DOES(ダズ)」と呼ばれる次の4つの特徴すべてに当てはまり、そのような子どもは5人に1人くらいの割合で存在すると言われています。ちなみに1つでも該当しないものがあれば、HSCではありません。
・D:Depth of processing(思考の深さ)
多様な観点から物事を考える。深く掘り下げて考えられる。
・O:Overstimulation(刺激の敏感さ)
小さなことが気になり、常に気が張っている。
・E:Emotional response and empathy(共感性の高さ)
他人の感情に影響を受けやすい。感情移入しやすい。
・S:Sensitivity to subtleties(感受性の鋭さ)
五感の神経が過敏で、強い刺激が苦手。環境変化に気付きやすい。
HSCは病気でも発達障害でもない
HSCは病気ではなく生まれ持った性質であり、幼少期の生育環境や体験によって引き起こされるものでもありません。原因の一つとしてよく言われるのが、脳の扁桃体という場所の働きが強すぎるということ。扁桃体は感情を司る部分で、そこが強すぎることで神経が過敏になったり、不安や怖さなどを感じやすくなると言われています。
HSCの一部の特徴は発達障害の子どもにもみられますが、HSCは発達障害ではありません。発達障害である自閉症スペクトラム(ASD)と注意欠陥・多動性障害(ADHD)の場合は、先ほどご紹介した4つの特徴の中の「E:共感性の高さ」に該当しないケースが多く、ここが発達障害とHSCを区別するための一つのポイントにもなります。
HSCの困りごとは周囲に分かりづらい
ここからはHSCの特性によって困りごとが起きやすい場面とそこで見られる様子についていくつかご紹介します。周囲が対応に困ることが多い発達障害に比べて、困りごとが自分の中だけで起こりやすいHSCは、周りの人から分かりにくいという特徴もあります。
■集団行動で疲労困憊
HSCの子は集団行動が得意ではありません。ところが苦手なのに人に合わせて頑張ろうと無理をしすぎて疲れて果ててしまうこともあります。
■他人の目が気になる
授業中に文字を書いたり計算をしたりする時、先生が背後からその様子を伺うことがあります。この時HSCの子の頭の中は、先生にどう見られているのか、もしかしたら間違っているのではないかと、気が気ではありません。背後の先生を意識するあまり、本領が発揮できないケースも多々あります。
■人混みでは頭がパンク寸前
街の雑踏だけではなく、学校や幼稚園、保育園などの人が多い場所は苦手。たくさんの声や情報が耳から流れ込み頭の中で処理が追いつかなくなる場合もあると言われています。
■自己紹介では涙も
人前で自己紹介をしたり意見を言うのが苦手な子が多く、過度の緊張で泣いてしまうケースがよく見られます。「泣き虫」というレッテルを貼られてしまったり、本人や周囲が困惑してしまう場合もあります。
■他人の怒鳴り声が恐怖
街で誰かが大きな声で怒鳴っていたり、喧嘩をしていると、過剰に驚いてしまうことも。学校や園では、別の子が先生から叱られていることを自分のことのように感じて、辛くなってしまう場合もあります。
■刺激の強い遊びは苦手
外遊びやテーマパークなど、一般的に子どもが好きとされている遊びが苦手な子が多いです。ただしHSCの中の一部のタイプには逆に刺激の強い遊びを好む子もいます。好きではあるけれど苦手であることに変わりはないため、テーマパークで絶叫マシンに乗った後にぐったり、ということにも。