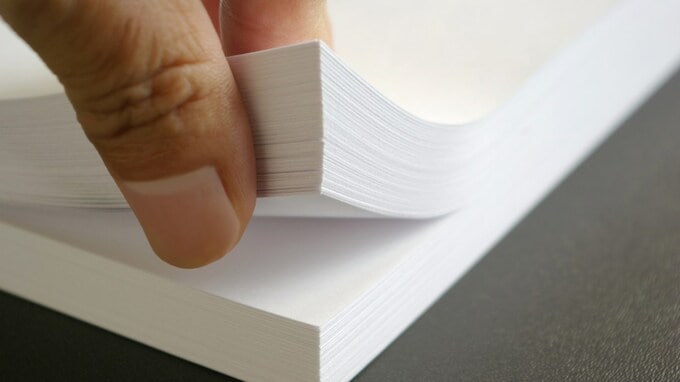関東大震災で店が全焼するも…6代目の妻・花子の手腕
6代目に代替わりするころの中庄は厳しい財政難に陥っていた。
6代目は、5代目の娘と結婚して中村家に入った。しかし妻が早逝し、その後、元小田原藩の上級家臣だった加藤家の三女・花子と再婚。6代目と花子は共に家業の復興に邁進(まいしん)し、日露戦争前後の好景気も追い風となって何とか財政難から抜け出すことに成功した。その間、長男にも恵まれる。
ところが、ようやく商売が上向いてきたという矢先に6代目は病に倒れ、42歳の若さで亡くなってしまう。残された花子は女手1つで采配を振るいつつ、長男を7代目・庄八とすべく熱心に教育したのである。
花子の手腕がもっとも発揮されたのは、1923年(大正12)の関東大震災のときだ。
関東大震災は、多くの家で炊事中だった昼時に大きな揺れが起こったこともあり、方々で火事が起こった。そこで花子は、瞬時に貴重品を土蔵に運び入れ、従業員に金銭を与え、荷車に重要書類などを積んで全員で避難する指示を出す。当時は大学生だった7代目・庄八も店の従業員も、みな無事だった。しかし店はすべて焼け落ち、無傷だったのは土蔵に運び入れた貴重品だけだったという。
そこから再建に向けて動き出すと、震災からわずか半月余りの9月下旬には仮ではありながらも営業所を開く。中庄があった地区では一番早い商いの再開となった。それを可能にしたのは、地方の得意先がこぞって支払いを早めてくれたことに加え、5代目の親戚が大きな農家を買い取って解体した木材を馬喰町に運び入れ、仮の建物を建ててくれたことだった。
創業以来、中庄では「信は万事の本と為す」の信条が守られてきた。周囲との信頼関係がすべてであるということだ。天災で店を失うという難事に際し、取引先がみな手を差し伸べてくれたあたりにも、平時からの信頼関係の強さが窺われる。
家庭紙と洋紙を扱う紙問屋へ…中庄の「転換点」
6代目の妻・花子は夫を失いながらも、天災に見舞われた中庄で采配を振るった。中庄の歴史は、養子や嫁など外部から迎え入れた人間に支えられてきたものといえる。
さらに時代を下り、昭和になるともう一人、キーパーソンが登場する。7代目の中学校時代からの盟友、服部(はっとり)清である。
第二次世界大戦前夜から戦中にかけては、統制経済や従業員の徴兵、徴用により、中庄の商売はかつてないほど縮小した。終戦時に残っていたのは7代目と女子社員だけだった。もともと役人だった服部は終戦の2年後、統制経済が解かれるなかで、少しずつ平常運転に戻りつつあった中庄に入社する。
時代が昭和になってもなお、中庄は、創業以来の「和紙問屋」としての伝統を守っていた。しかし紙の市場では、すでに機械漉(す)きの洋紙が主流となっていた。書籍でも雑誌でも使われている紙は洋紙であり、今後は印刷業界や出版業界と取引しなくては商売が立ち行かなくなってしまう。戦争が終わったことで見込まれる印刷・出版文化の復活により、洋紙を作る製紙会社も作られる用紙の種類も、戦前と比べると格段に増加するのは自明の理だった。
そうした見立てのもと、洋紙の取り扱いをより積極的に推進したのが当時専務の服部だった。中庄の歴史と伝統に、いわば新時代の風を吹き込んだわけである。8代目庄八は、大学卒業後大手製紙メーカーに勤務し、その後中庄に入社。服部の教えをもとに変化の時代への柔軟な対応で洋紙に対する設備投資にも積極的に取り組み、物流倉庫の建設や本社ビルの建て替えを実施。また、計算機と称される時代のコンピューターにも着目し、業界内ではいち早く活用し始め、新たな基礎を築き上げた。洋紙の扱いを推進したことが中庄の大きなターニングポイントだったと、現在の9代目・中村真一社長は見ている。
ちなみに「庄八」襲名は、戸籍までのすべてを変えるので、先代が亡くならない限りは行えない。8代目・中村庄八は相談役として在席しているため、中村真一社長は「庄八」を未だ襲名していないのである。
さて、なぜ服部の推進によって始まった洋紙の扱いが、中庄のターニングポイントになったといえるのか。かつて和紙を扱っていた紙問屋の商材は次第にトイレットペーパーなどの家庭紙に移り変わっていったが、中庄は和紙から家庭紙への転換を図ると同時に、洋紙の販売を始めたことで、両方を扱う紙問屋へと成長したからだ。
市場規模が小さい地方では家庭紙と洋紙を扱う紙問屋は珍しくないが、現在、都内では希少な存在である。1940年代に、和紙問屋のなかでいち早く洋紙の販売を始めたことが、今の中庄につながっているのだ。
かつてちり紙と呼ばれていたものが家庭紙へと移り変わり、取り扱い品目も変化して、家庭紙への切り替えと洋紙販売の開始、さらには高度経済成長の波に乗り、中庄は急速に事業規模を拡大していく。まさに順風満帆というなかで、まるで青天の霹靂(へきれき)のようにして起こったのがオイルショックだ。