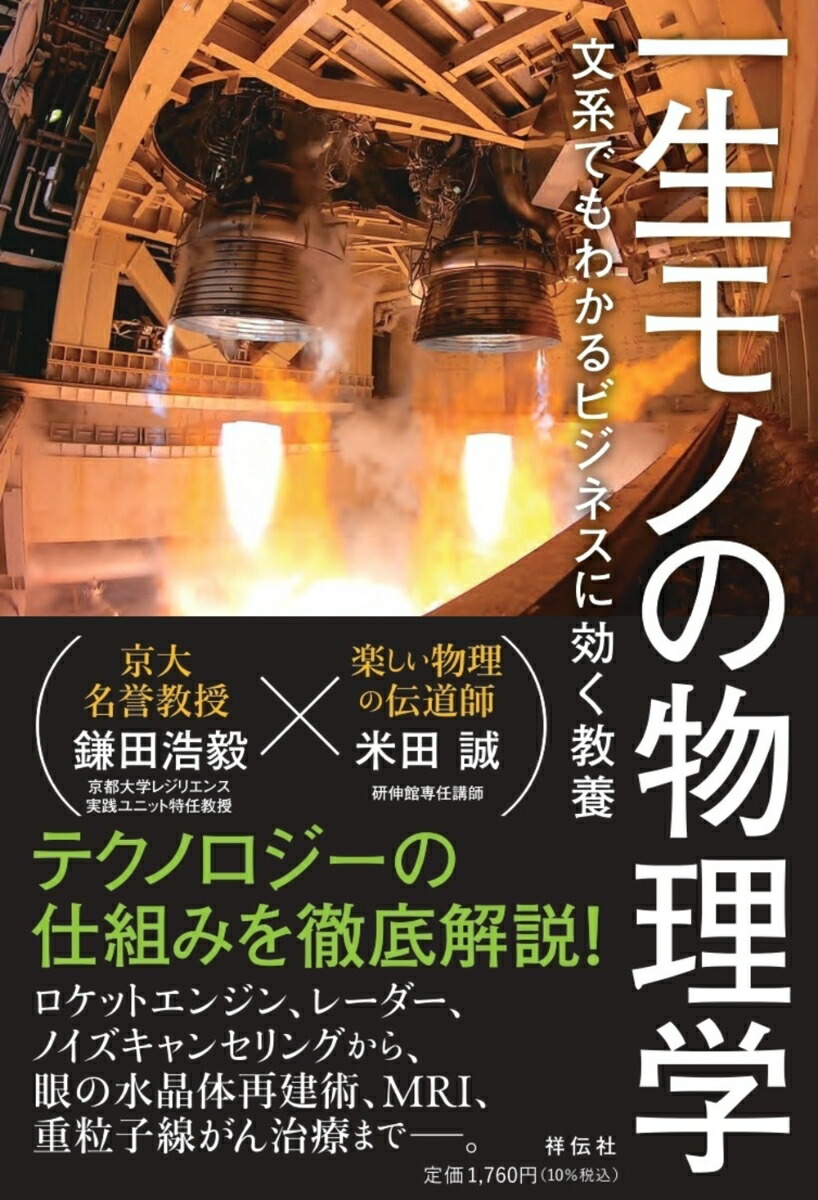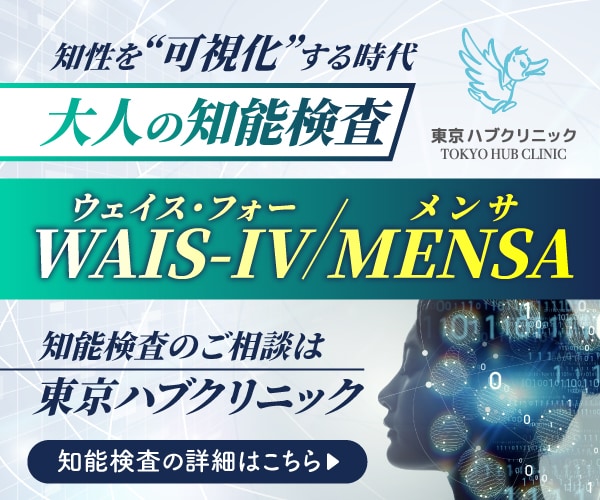白内障手術で使われる「多焦点眼内レンズ」。遠近両方にピントが合い、メガネやコンタクトから解放されるとたいへん便利な一方で、従来の単焦点レンズに比べ「高額すぎる」と敬遠されてしまうことも……今回は、そんな「多焦点眼内レンズ」の詳しい仕組みとその課題について、京都大学名誉教授の鎌田浩毅氏と、関西大手予備校「研伸館」講師の米田誠氏が、物理学の観点からわかりやすく解説します。
遠くを見る人に適した「屈折型多焦点眼内レンズ」
多焦点眼内レンズには、単焦点眼内レンズと同様に「光の屈折」を用いるものと、それとは別に、「光の回折」という現象を用いるものがあります。この2つは光への理解を深めるためにぴったりですから、順番に仕組みを解説していきましょう。
まずは、光の屈折を用いた多焦点眼内レンズです。
[図表1]に示すように、屈折型の多焦点眼内レンズはレンズを複数枚重ねたような形状をしています。そしてそれぞれの場所によって異なる角度で光を屈折させ、光を集めています。
まず、レンズの中央部。ここは少しだけ光を屈折させます。水晶体を薄くして遠くにピントを合わせるときと同じ状況を人工的に再現しているのです。次に、レンズの周縁部です。ここは大きく光を屈折させます。中央部とは逆に、水晶体を厚くして近くにピントを合わせる状況を再現しています。
つまり屈折型の多焦点眼内レンズは、ピントを合わせるためにいちいち形状を変化させる水晶体とは違い、初めから複数の角度で光を屈折させられる形にしているのです。
しかし、このレンズにも弱点があります。近くのものが見えづらくなるリスクがあるのです。
近くのものを見るときは、前述のようにレンズの周縁部を使うのですが、目の周りの筋力は加齢とともに落ちますから、瞳孔が開きにくくなります。その結果、レンズの周縁部を光が通過しにくくなってしまい、次第に近くのものにピントが合わなくなっていくのです。
このデメリットがあるため、屈折型の多焦点眼内レンズは、どちらかというと遠方を見ることを重視したい方で、かつ比較的若い患者さんに適した治療法とされています。
京都大学
名誉教授
1955年東京生まれ。東京大学理学部卒業。通産省主任研究官、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て、現在京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・同名誉教授。専門は火山学、地球科学、科学教育。「京大人気No.1教授」の「科学の伝道師」。
著書は『100年無敵の勉強法』(ちくまQブックス)、『理系的アタマの使い方』(PHP 文庫)、『新版 一生モノの勉強法』(ちくま文庫)、『火山噴火』(岩波新書)、『地球の歴史』(中公新書)、『一生モノの英語勉強法』(吉田明宏氏との共著、祥伝社新書)などのほか、研伸館との共著に『一生モノの受験活用術』(祥伝社新書)がある。
YouTube「京都大学オープンコースウェア」で『京都大学最終講義』動画を公開中。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「物理」で日常のみえかたが変わる…身近な医療技術を物理学の視点から徹底解説!
研伸館
専任講師
1977年生まれ。兵庫県西宮市出身。大阪大学大学院修了(修士[工学])。三菱重工業株式会社での設計業務を経て、現在関西の大学受験予備校「研伸館」にて物理の学習指導に携わる。東大・京大をはじめ、難関大学志望の高校生や灘中・灘高の学校準拠クラスを指導するなど、幅広いレベル・学年の講座を担当。イメージに頼らず、基礎から体系的に知識・論理的思考力を構築していく指導をモットーとする。
YouTube「研伸館オンライン」チャンネルにて、『物理のワンポイント講義』動画を現在公開中。鎌田浩毅・研伸館共著の『一生モノの受験活用術』(祥伝社新書)にて物理の記事を執筆。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載「物理」で日常のみえかたが変わる…身近な医療技術を物理学の視点から徹底解説!



![[図表1]屈折型の多焦点眼内レンズの形状および集光](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/7/6/600/img_76340dbcfebcfe0e767e8be594767bfc26191.jpg)