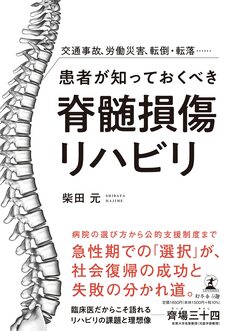【関連記事】「寝たきり」になる衝撃背景…全国に200万人以上いる「リハビリ難民」
リハビリテーションはどのように続いていくのか?
急性期(救命措置など、高度な医療ケアが必要な時期)を過ぎたあとのリハビリテーションは細かく分かれています。急性期病院で治療を終えたあとに移される病棟は、一般に亜急性期リハビリテーション病棟と呼ばれますが、これは正確には回復期リハビリテーション病棟と地域包括ケア病棟の二つで構成されています。
回復期リハビリテーション病棟は、2000年4月の診療報酬改定に伴って定義された病棟です。急性期病棟での治療後、疾患管理下にある脳卒中や大腿頚部骨折の患者、全身麻酔の状態で胸腹部回復術の手術を受けた患者に積極的にリハビリテーションを提供する、リハビリテーション専門病棟として位置づけられました。
地域包括ケア病棟は2014年に制定された病棟で、急性期医療後の在宅復帰に向けた医療を提供することを目的に設置されました。
厚生労働省はこのように病棟の機能を分けることで、高度急性期での検査と治療が終わったら連携先の亜急性期医療を担う病院に患者を直接転院させるという流れをもともと想定していたはずです。(高度)急性期病院は先進的な医療を提供するところであって、患者の不安定な状態は完結しているという前提のうえに連携パスは構築されています。そのため急性期後の亜急性期病院は無駄な検査などせずにリハビリテーションをしてさっさと退院させればよいという発想です。しかし、その連携はなかなかうまくいっていません。
理由は高度急性期(急性期)の病院のほとんどが診断群分類(DPC)に基づいて、入院日数に応じた一日あたりの定額医療費を包括的に算定するようになっているからです。
「病院の収益優先で転院させられる患者さん」も多数
DPCの診療報酬ルールでは、脳卒中発作で入院した患者を治療したら、それ以外の病気も見つかりたくさん検査や治療をしたとしても、診療報酬は一定額しか支払われません。
そこで急性期病院では主病名の検査や治療を中心に行ったあとで、命に直接の影響がない場合は、ほかの疾患の診療は最小限しか行わないことになります。それらは収益の見込みのない、病院の持ち出しになってしまうからです。
そうすると、急性期病院から患者を引き受けるリハビリテーション病棟では、思わぬ疾患を抱えた患者がやって来てリハビリテーションどころではなくなることがあります。脳卒中で急性期を脱した患者のリハビリテーションを担当するために紹介入院を引き受けたが、いざやって来た患者を診てみると心不全や糖尿病、腎臓病、認知症、関節リウマチまであって、それらの治療をしなければならないということになるのです。このようなケースは実に多くあり、時には未診断の癌が見つかることもあります。
また重症患者の場合、状態が十分に安定していなくても在院日数の関係で急性期病院からの転院を迫られることがあります。「これ以上入院させていると、入院算定日数を超えてしまう」とか、「包括払いの診療報酬では赤字になってしまう」という判断が急性期病院側に働くからです。
亜急性期病院では、リハビリテーションを目的に患者を引き受けるわけですが、実際のところ重症過ぎてリハビリテーションができる状況ではない、という場合も多々あります。
そこで、このような患者はまずは自院の一般病棟で受け入れて状態を今一度確かめ、安全かつ積極的にリハビリテーションができるかどうかを確認しながら、リハビリテーションを開始するタイミングをうかがっていきます。
大都市の医療連携、地方都市の医療連携は大きく異なる
ただ、こうした連携のちぐはぐさも東京都と、福岡県のような地方都市とでは様相が大きく異なります。施設基準や診療報酬が全国一律なのに、土地代や人件費は地方によって違うのです。
土地代や人件費が地方に比べて高い東京都市圏の急性期病院は、ほかの医療機関との連携によってリハビリテーションやその後の慢性期医療を提供する体制を整備する方針をとるケースが多いです。亜急性期以降の診療は診療報酬が極端に低くなるため、急性期病院では高単価の診療に集中したほうが、経営上のメリットが大きいからです。
一方、地方都市は都市圏と比較して病床過剰地域が多く土地代も人件費も安いため、医療再編での病床数削減を回避して収入を維持するべく、急性期病床を亜急性期病床、さらには長期療養病床に転換します。いわゆる医療福祉複合体として、急性期から慢性期、あるいは介護サービスまで同一組織内で提供する体制が増えています(垂直統合)。
しかし、どちらの連携の仕方も一長一短です。水平統合型では患者は複数の医療、福祉、介護施設を転々としなければならなくなるものの、その都度自分に見合った医療および施設を選択する機会をもつことができます。対する垂直統合の医療連携では、特定の急性期病院に運ばれた時点で、その人のその後の転院先は終点まで決まってしまう可能性が高くなります。
地域包括ケア病棟(病床)は、1日2~3単位(1単位20分)のリハビリテーションを提供するように定められていますが、リハビリテーション科専門医がいない施設もあります。また、医療療養病棟でもリハビリテーションを受けることが可能となっていますが、一部の例を除き、充実したリハビリテーション機能を整備している施設はほとんどありません。
加えて、リハビリテーション医療の質を考える際にいちばん大切なのは、その病院が「リハビリテーションマインド」をもっているかです。「質の高いリハビリテーションを提供します」とうたうのは簡単ですが、体現するのはやさしいことではありません。その施設が障害者の全人間的復権(人間らしく生きる権利の回復)に対して真剣に取り組んでいるかどうかで、リハビリテーションの質は大きく変わってきます。
「重症患者に施されるリハビリ」の実情
地域包括ケア病棟は患者が(高度)急性期病院での治療を終え、病状が安定したのち、在宅や施設への復帰に向けて治療の継続や支援を行うための病棟として位置づけられています。あるいは、地域で在宅療養中の患者が体調不良や基礎疾患の急性増悪をきたしたときなどに、緊急で受け入れる在宅療養支援機能としての役割もあります。
地域包括ケア病棟は、中小病院の機能の一部として設置されていることが多いです。受け入れるのは必ずしもリハビリテーションが必要な患者ばかりではありませんが、必要な人には一人平均2~3単位(1単位=20分)のリハビリテーションを提供することが義務づけられています。
そこで、回復期リハビリテーション病棟の対象外患者は、この病棟でリハビリテーションが行われることになります。ただ、リハビリテーションを含めて薬や検査費用はすべて包括医療となっているため、診療報酬はその都度加算される方式ではありません。従って、高額な薬・検査が必要な患者や、60日以内に自宅退院ができそうにない重症患者は敬遠されがちです。
また、リハビリテーションを一定以上提供しても、病院の収益としては変わりません。そのため「1日のリハビリテーションは多くて3単位までに抑えよう」というインセンティブが働いています。
3単位とは60分のことで、重度の障害をもっている方が機能回復、自宅復帰を目指すには、非常に少ない時間といえます。地域包括ケア病棟では、短期間で在宅復帰できる可能性が高い人たちにリハビリテーションを提供することになります。
また長期入院による医療費の無駄遣いを避けるため、地域包括ケア病棟には施設基準として入院日数が60日以内と定められています。さらに、回復の見込みがない患者を安易に入所させて入院を長引かせ医療費を浪費することがないように、また在宅復帰率を基準内におさえようと軽症の人ばかり入院させることがないように看護必要度といったものが設定されています。
在宅復帰率とは、入院した患者が退院して自宅や居住型介護施設に戻った割合のことです。ただ病棟を退院したことがスコアになるだけの指標であり、患者がどの程度改善したのかは問われていません。病棟には在宅復帰率を施設基準内に維持したいという希望がありますから、患者は期待した結果が得られないまま退院を迫られるというケースもままあります。どの程度機能を回復させた患者を退院させるかについては、施設のさじ加減にかかっている部分が大きいのが実状です。
柴田 元
医療法人かぶとやま会 理事長
久留米リハビリテーション病院 院長
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】