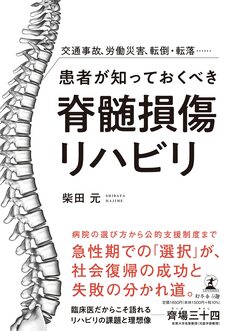事例:突然の交通事故で「寝たきり」になった山本さん
■突然の交通事故…救急病院に運ばれたまでは良かったが
山本祐司さん(仮名・43歳)は、取引先での重要なミーティングを終え最寄りの駅に向かっていました。仕事は順調で来年には昇進の話もありました。3歳になる息子もすくすくと成長しており、妻は元気に育児に励んでいました。息子が小学生になったら職場に復帰してダブルインカムでマイホームを建てようか、などと将来の夢も膨らんでいました。
途中、コンビニに立ち寄り飲み物を買おうとしたとき、それは起こりました。
山本さんがコンビニを出て駐車場を横切ろうとした瞬間、一台の乗用車が山本さんに突っ込んできたのです。ブレーキとアクセルの踏み間違いによる急加速が原因でした。山本さんは車ごとコンビニの窓ガラスに激突してガラスを突き破り、棚に背中を強く打ちつけ気を失いました。
山本さんが目を覚ましたのは、急性期病院のベッドでした。あのあと、救急病院に運ばれ緊急手術を受けてなんとか一命をとりとめ、ICU(集中治療室)で数日間経過観察となりました。その後、状態が安定した頃を見計らって、通常のベッドに移されたのです。目を覚ました山本さんは、自分が生きていることに安堵しました。しかし、そのすぐあとで声が出ないことに気づきました。気管切開が施され、喉に酸素吸入器のチューブが取り付けられていたのです。
そして、身体がまったく動かないことにも気づきました。腕が持ち上がらず、足を揺することすらできません。身を起こそうにも、胴体はぴくりともしませんでした。
それから、首も何かで固定され動かすことができません。尿を自分で排出することができないので膀胱までカテーテルを通し、直接体外まで導き出す処置が施されていたのです。腕にも計器がつながれており体温や血圧、脈拍が常時計測されていました。
■「寝たきり」のまま数ヵ月ごとに病院を転々とする生活へ
やがて気管切開の際に空いた穴も閉じて状態が安定し、寝たきりではあるものの話せるようになった頃、山本さんは回診に訪れた医師に尋ねました。
「先生、私はいつ頃退院できるのでしょうか?」
「あと数週間したら、ここを出てもらうことになると思いますよ」
ただしそれは、症状の回復を意味するものではありませんでした。
「山本さんは症状が落ちついたので、回復期リハビリテーション病棟に移ることになります」
急性期病院は緊急度の高い患者に対応する病院なので、状態がある程度落ちついている山本さんは、全身がチューブでつながれている状態でも退院する必要があるのでした。
「リハビリ病棟…ではそこで、本格的なリハビリを開始するのですね」
「いえ…」
医師は申し訳なさそうに首を振りました。
医師の説明によると、脊髄損傷とは背骨で守られた重要な中枢神経の損傷であり、その位置や程度によって四肢の運動や感覚の麻痺、膀胱・直腸機能の障害などのさまざまな症状が表れるとのことです。なかでも首に近い部分の中枢神経系である頚髄がやられてしまうと、重度障害を伴い首から下がまったく動かなくなってしまいます。中枢神経は一度損傷すると回復は期待できないとのことでした。
「そんな…私はどうなるのでしょう」
「詳しい話はソーシャルワーカーに聞いていただければと思います」
その後、山本さんは回復期リハビリテーション病棟に移ります。その病棟は自宅に近い場所にあり、「ご家族が会いに来やすいですよ」と医師に言われました。さらに医師は「うちの系列病院ですから、私も山本さんの情報は共有しています」とも言ってくれ、「それなら安心だろう」とも考えました。
ただ、寝たきりで回復の見込みなしということはその施設の医療従事者もよく知っているようで、山本さんに積極的なリハビリを施そうとする動きはありませんでした。やがて数ヵ月が経ち、山本さんはやはり系列の療養病棟に移りました。ここでも寝たきりのまま、ただ血圧や心拍数をチェックされ、食事と排せつの全介助を受ける毎日が続くのでした。意識は冴えているだけに、山本さんにとっては恥ずかしくつらいことでした。
人によっては誤嚥からの肺炎や、床ずれ(褥瘡〔じょくそう〕)が悪化して潰瘍になるケースのほか、骨が露出したり、感染症を起こしたりといったこともあり得ますが、山本さんは幸いそのようなことはありませんでした。
現在、山本さんは数ヵ月ごとに病院を移る生活をしています。家に帰り在宅医療でやっていきたいとも考えましたが、家族の負担を考えるとできない相談でした。
障害者支援施設や介護医療院などであれば長期の利用もできる可能性がありましたが、問い合わせるとどこもベッドに空きがなく、「数年待ちになる」という回答ばかりでした。
いずれ山本さんは居住型の介護施設に入ることができる可能性もあります。そこを終の住処にすることも不可能ではありません。また、事故の際に支払われた保険金が十分ありますから、経済的な心配はありません。
山本さんはずっと天井を仰ぎながら、居住型の施設に入所できる日を待っているのです。
本当は「頚髄損傷でも家に帰れる」
■山本さんは“なしくずし”で自宅復帰の機会を逃してしまっていた
頚髄損傷を受けた場合、多かれ少なかれ山本さんのような境遇に陥るパターンがほとんどです。疾患には急性期、亜急性期、維持期と段階があり、高度な医療ケアが必要な急性期を過ぎて状態が落ちついたら急性期病院を出て、回復期リハビリテーション病棟や療養病棟などのふさわしい施設に転院していくのが通常です。
徐々に病状が回復し、やがて元の日常生活に戻っていく、というのが理想とされています。例えば脳卒中で倒れたという場合、急性期病院に運ばれて救命措置を受けます。生命の危機を脱しても運動麻痺や言語障害といった後遺症がある場合が多く、状態が安定したら回復期リハビリテーション病棟に移って、そのための訓練を行うのです。リハビリテーションを繰り返し、もう大丈夫だろうと判断されたら自宅に戻り、日常生活を再開します。働いていた人なら、同時に職場へも復帰していく場合もあります。
しかし頚髄損傷の場合、このような経緯をたどることが非常に難しいのが日本の医療の現状です。頚髄損傷は重度の障害をもたらすことが多いため、救命後のリハビリが脳卒中や骨折などの場合とは比べものにならないほど大変なのです。とはいえ、それでも「なったら最後」で、一生寝たきりになることが確定するものでは決してありません。その意味で山本さんは、急性期以降のリハビリテーションの医療連携がうまくいかず、自宅に戻るチャンスを逃してしまったといえます。
■病院のサポートが十分なら、脊髄損傷でも自宅で生活できる
脊髄損傷は、高位(頚髄・胸髄)と下位(腰髄)脊髄損傷に分けられます。第3頚髄より上方の損傷では呼吸麻痺のため人工呼吸器が必要となってきます。損傷が頚髄にある場合を頚髄損傷といいます。損傷部位が高いほど後遺症も重くなります。
下位損傷の場合は、頚髄損傷と比べれば合併症も少なく上肢機能が保たれているため、両足が完全麻痺であっても上肢機能を鍛え上げることで、車椅子での自立した生活は可能となるし、その気になればパラリンピックに見られるような車椅子アスリートとして活躍することもできます。また、完全損傷か不全損傷かによっても大きく将来が変わります。
さらに比較的高齢者に多い中心性頚髄損傷というのがあって、主に上肢を支配する神経線維が損傷を受け、歩けるけれども手が使えないというタイプがあります。頚髄損傷については、Frankelの分類という指標を用いて、どの程度の回復が期待できるかある程度予想することが可能です。専門的な話は本連載の目的ではありませんのでこれ以上の説明は行いませんが、リハビリテーション科専門医はこれらの指標をもとに、将来の目標を設定し訓練計画を立て、コメディカルに指示を行い協働でリハビリテーションケアを実施していくことになります。本連載の全般に流れる文脈として、リハビリテーション科専門医のいないリハビリテーション病院は、コンパスもなく水先案内人もいない船のようなものではないかと思います。
リハビリテーションの目標設定のうえでは、年齢も重要です。20~40代ならば頚髄損傷で一時は寝たきりになっても、意欲的にリハビリに取り組めば家族の協力で自宅に戻ることは可能です。やり方によってはひとり暮らしも不可能ではありません。
60代、70代だと家族も高齢の場合が多く相当の支援が必要になりますが、やはり自宅に戻ることは可能です。この年齢だとつい周囲が「それなら施設に行かせよう」と考えてしまいがちなことが、実は問題です。
65才以上では無条件で介護保険が使えるため、それで施設に入ってもらったほうが経済的にも安心だし家族の負担も小さくて済むから、ついそのように話を進めてしまうというケースが多くあります。結果、可能性は十分にあったのに自宅に帰れず、施設で寝たきりということになってしまうのです。頚髄不全損傷であれば65歳以上でも十分に家庭復帰は可能です。完全損傷の場合は、やはり本人および家族の強い意志が必要です。
今の時代、目の動きやわずかな指の動きでパソコンを操作することも可能です。IoTが発達したおかげで、電動車椅子に乗って照明やエアコン、カーテンなどの操作も一人でできます。脊髄損傷になったら一生ベッドの上で寝たきり、という考え方は間違っているといえます。
つまり「病院のサポートが十分なら脊髄損傷でも自宅で生活できる」という正しい認識が広まっていないのです。
また、施設で寝たきりで過ごす人が多い理由は、大きく分けて二つ挙げられます。一つは、医療の効率化を目指すなかで病院の機能分化と連携が進んだ結果、脊髄損傷など一部の患者が医療施設の連携網から零れ落ちてしまっていることです。もう一つは急性期病院の医療従事者を筆頭に、「脊髄損傷といえば寝たきり」という思い込みの図式が確立されてしまっていることです。
柴田 元
医療法人かぶとやま会 理事長
久留米リハビリテーション病院 院長
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】