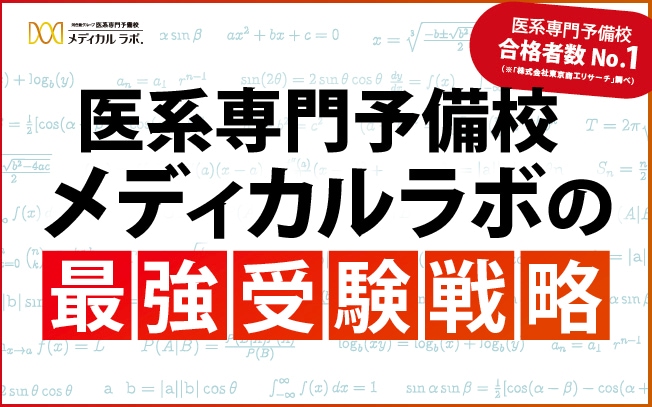あなたにオススメのセミナー
【関連記事】「ADHD」は6倍「学習障害」は5倍…「発達障害の子」10年で急増のワケ
新小1の保護者「ほかの子と違う」の不安
4月から小学校に入学する、新1年生。真新しいランドセルに、心を躍らせている……そんな様子をみてほっこりしている保護者も多いことでしょう。一方で「この子、他の子とちょっと違うけど、小学校にあがってやっていけるのかしら」と不安を感じている保護者もいるかもしれません。
文部科学省の調査によると、知的発育に遅れはないものの、学習面、または行動面で著しく困難を示すとされた児童・生徒の割合は、6.5%・そのうち、小学1年生は9.8%で、10人1人とされています。これらの子どもたちは、発達障害の可能性があり、特別な教育的支援を必要とする、とされているのです。
【学習面、または行動面で著しい 困難を示すとされた児童生徒の割合】
学習面、または行動面で著しい困難を示す:6.5%
学習面で著しい困難を示す:4.5%
行動面で著しい困難を示す:3.6%
学習面と行動面ともに著しい困難を示す:1.6%
小学校:7.7%
1年生:9.8
2年生:8.2
3年生:7.5
4年生:7.8
5年生:6.7
6年生:6.3
中学校:4.0%
1年生:4.8
2年生:4.1
3年生:3.2
出所:文部科学省『障害児通所支援の在り方に関する検討会』第1回資料より
発達障害。いまではよく聞かれるようになった言葉ですが、そうなったのはいまから20年ほどさかのぼった頃から。発達障害者支援法が制定された2004年あたりからでしょう。
同法では発達障害について、以下の通り示しています。
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの
発達障害支援法第2条1項
「その他」とは、厚生労働省の省令で定められている、吃音やトゥレット症候群、選択性緘黙が含まれるとされています。同法では、発達障害は「社会の問題」であり、早期発見と切れ目のない支援を行うと明記されています。