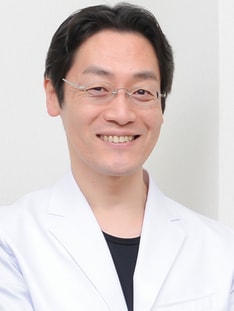薬物療法「もどき」が主流…精神医療の現実
精神科ユーザーが抱えるボトルネックのあり処は、実に多岐にわたります。なぜなら一人の人間には、脳機能の低下などの身体のレベル、不安にどの程度耐えられるかなどの感情のレベル、現実的な判断がどの程度できるかなどの認知のレベル、逆境でも自分をどの程度信じることができるかなどの信念のレベルなど、複数の層が重なり合っています。
そのうえ、それぞれに遺伝的要素、これまでの生い立ち、現在の生活習慣や対人関係などが影響を与えているからです。対人援助者はさまざまな側面から患者を注意深く観察し、ボトルネックがどこにあるのかを把握するよう努めなければならないのです。
あり得るボトルネックの一つが脳機能の低下です。それを解消する方法の一つが、薬物治療です。
しかし、Aさんの例も含めて、医師にだけ可能で、だからこそ、せめてそれだけはしっかりやってほしいと誰もが期待するはずの薬物治療という援助が不十分なケースも見られます。
Aさんの担当医は毎回の診察でAさんに「調子はどうですか」としか確認していませんでした。これでは、Aさんが自覚する一番つらい症状、つまり朝の起床時のしんどさだけを評価していることになります。確かに、その症状は頑固で改善するのに時間がかかる場合があります。
しかし、その裏で、Aさんの自覚は乏しいまま、食欲は徐々に改善しているかもしれません。それを担当医が問診して、仮に確認することができたなら、Aさんも、その担当医も、うつ病が徐々に改善していると気づくことができます。この瞬間、実は、Aさんの「なかなか治らない」という認知が「徐々に治ってきている部分がある」という認知に切り替わる、さりげない認知行動療法が実践されたことになるのです。
これはほんの一例ですが、薬物療法とは、単に「薬を処方するだけ」という介入ではありません。薬を内服した結果生じるさまざまな変化を題材に展開されるカウンセリングだといえます。
ですから、「合わないのではないか」「減らしたほうがいいのではないか」「減らすのが怖い」などの、服薬に関連する患者の訴えをしっかり取り入れることも必要となります。そこから、ほかのボトルネックを探すヒントが得られる場合が多いからです。
しかし、Aさんの担当医のような「薬を処方するだけ」という薬物療法「もどき」が主流となっていることが、精神医療の現実なのです。
こうした状況では、薬物療法という限られた対人援助さえも、完璧にできていると胸を張って言える医師は多くはないはずです。診断名が同じであればどの患者に対しても似たような治療になってしまうのは、薬物治療が診断名に紐付いた「薬を処方するだけ」のものになっているからなのです。
薬物治療だけでなく、患者への生活指導についても同様です。うつ病は、生活習慣を改善したり適度な運動をすることで症状の改善が期待できますが、だからといって、「生活リズムを整えましょう」「しっかり寝てくださいね」「適度な運動をしてくださいね」という一辺倒のアドバイスをするだけで終わってしまうのは、援助の本質を理解できていないと言わざるを得ません。
なにしろ、起き上がることすら難しい状態の患者も多くいるなかで、運動が心身に良い影響があると分かっていても、「適度な運動をしましょう」と医師に言われただけで、そのとおりに実践できる人はほとんどいないのです。
精神科医は患者の日々の行動を変えていくために、患者が普段どんな生活をしているかを把握し、いつ何をすべきかをより具体的に指導する必要があります。
※ 本記事で紹介されている事例は、個人が特定されないよう、実際の患者のケースを複数組み合わせています。
小椋 哲
医療法人瑞枝会クリニック 院長