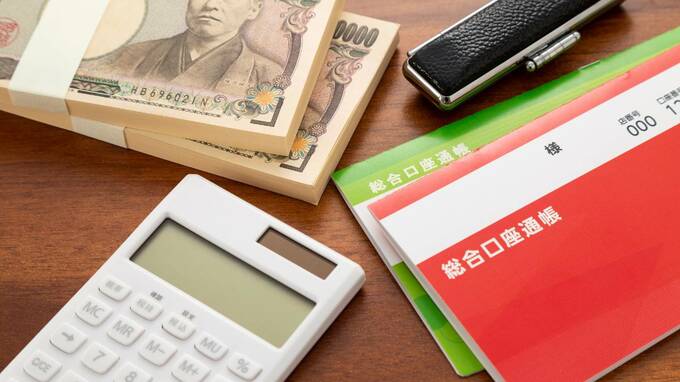大切な預金を子供に相続・贈与する場合、子供が無駄遣いしてしまうのではないか?と心配する人は多いです。今回は、「信託」を使ってこの不安を解消する方法を、税理士が事例を使って解説します。※本連載は、笹島修平氏の著書『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ 5訂版』(大蔵財務協会)より一部を抜粋・再編集したものです。
お金の使い道を制限して相続するには「信託」が有効
Q. 私は無駄遣いすることなく生活して若干の預金があります。この預金を子供に相続してあげたいと思います。しかし、この大切なお金は、子供達の教育や医療のために使ってほしいと思います。遊興費等に無駄遣いしてほしくないのですが、私が亡くなった後にそのように制約することはできないでしょうか。
A. 信託を活用すると、金銭の使用目的に一定の制約を付けて相続することが可能となります。具体的には、生前に親が子供に相続する予定の金銭を信託し、当初の受益者は親にします。
信託契約書において、受益者である親は自由に信託した金銭を使うことができるものとし、親が亡くなると次の受益者は子供に指定して子供が医療や教育のための金銭を必要とする場合に限り、受託者は信託財産から金銭を子供に支給する旨を定めます。
信託を活用すると「気持ち」を伝える相続が可能になる
自分が亡くなることを想像した時、親の気持ちは様々です。子供の将来を案じることも多いでしょう。「自分がずっと生きていられるならば、子供が壁にぶつかった時に色々と助言できるのに……。」「経済的にも支援できるのに……。」「色々な人脈を紹介できるのに……。」等々と、ずっと、配偶者や子供の力になってあげたいと望むのが親だと思います。預金を遺す親は、子供達が教育費や医療費を必要とした時に備えて預金を遺したいと望んだりします。
しかし、自分が亡くなったら、子供達が預金を相続して、場合によっては無駄遣いしてしまうかもしれません。「自分(親)が健在であれば、自分(親)がお金の管理をして、子供達にとって必要な時に支援してあげて、預金が生きた使われ方をするようにできるのに……。」
信託を活用すると、上記のような親の心配に応えることができます。
株式会社つむぎコンサルティング
代表取締役
株式会社つむぎコンサルティング公認会計士・税理士。昭和44年神奈川県生まれ。平成5年慶應義塾大学理工学部卒業。東京大学大学院理学部中退。平成6年太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)にて、監査業務に従事。平成11年公認会計士・税理士登録。株式会社タクトコンサルティング入社。平成13年~平成17年慶應義塾大学非常勤講師「戦略的税務会計特論」にて、企業組織再編・M&A・事業承継・相続等の教鞭を執る。平成19年中小企業庁「相続関連事業承継法制等検討委員会」委員。平成24年株式会社つむぎコンサルティング設立。
著書に、『資産税の盲点と判断基準 改訂版』(大蔵財務協会)、『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ 5訂版』(大蔵財務協会)などがある。
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載税理士が事例で解説!「信託」を活用した相続の基礎知識