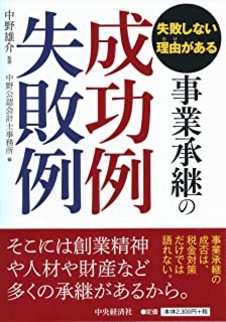弟のモチベーションが低下した背景にあるのは?
嵐山産業社長の清一と専務の順二が不仲になったのは、次のような原因が考えられます。
順二は嵐山興産の経営を任されてはいますが、清一が代表者であり、大株主でもあるため仕方ない一面があるものの、最終決裁は必ず清一を通す必要がありました。また、清一は金銭に細かい面があり、費用対効果を論理的に説明できない経費の支出は絶対に許しませんでした。
このような状況下で、表面的に会社内や取引先、得意先に対しては、順二が経営全般を任されているように見えます。しかし、順二にすれば現場で責任者として苦労だけさせられて、自分のやりたいことが自由にできないと思うようになっていきました。
清一は嵐山興産の社長の座はいずれ順二に譲るつもりでしたが、順二の素行の悪さや経営者としての資質に疑問を感じていたため、なかなか譲ることができずにいました。
また、嵐山産業の業績が悪かったため、グループ全体のバランスを考えていた清一は、嵐山興産が独自で受注した仕事を嵐山産業に回すこともありました。清一にとっては両社は一体かもしれませんが、順二にすれば、自分が受注してきた仕事も嵐山産業に吸い上げられ、自分の頑張りが数字に直結しないことに不満を募らせていました。
このような状況なので、嵐山興産は経費削減を実施しており、順二の役員報酬も低く抑えられていました。
嵐山産業との業務のバランスの調整や、経費削減に伴う順二の役員報酬の引下げ、さらには、清一から社長の座を譲られなかったことなどが積み重なり、順二のモチベーションも低下していったのでしょう。
嵐山産業の業績が良ければ、このような状況にはならなかったかもしれません。利益が出ていれば、嵐山興産の仕事を嵐山産業に回すこともなかったでしょう。また、順二自身もある程度の役員報酬を取ることでやりがいを感じて、嵐山産業・嵐山興産の業務に専念していたかもしれません。
業績は改善傾向にはあるものの、全盛期に比べれば売上は8割ほどに落ち込んでおり、手持余剰資金も少なく会社内の雰囲気も暗いものになっていました。
順二が新製品や新規事業を立ち上げようとしても、清一が失敗したときのリスクを警戒して、実行に移すことはありませんでした。順二の提案は、高額な設備投資が必要になるような新製品の開発や、全くの異分野への進出等、確かにリスクが高いものばかりでした。
会社の業績が良く、余剰資金を多額に抱えているような状況であれば、思い切った設備投資や異業種分野への進出を決断、実行できたかもしれません。
このような状況下で、清一、順二共にストレスが溜まり、お互いがやることに対して牽制し合うようになっていきました。
兄が弟に経営を任せなかった理由
清一は幼い頃から成績優秀で交友関係も広く、友人からの人望もありました。一方、順二は幼い頃から常に清一と比較され、成績も人並みだったため、清一に対してコンプレックスを持っていました。
清一は社長になってからも、取引先や業界関係者からの信頼も厚く、様々な地域活動にも参加しており、敏腕社長というイメージが社内外でも定着していました。そのような清一からすると、幼い頃から弟である順二は頼りない存在でした。
経営上の判断で順二に対して意見を求める場面もありましたが、的外れな回答をするようなこともあり、経営を任せることはできないでいました。
経営者は自分と同じ資質を後継者に求めがちです。しかし、優秀であればあるほど、同じ資質を持った人間はいないものです。
清一も順二と2人でよく語り、順二の素行の悪さの原因を取り除き、お互いに信頼を取り戻すべきでした。そのうえで順二に社長の座を譲り、何かあった時は清一がフォローできるような体制を取っていれば、不仲は回避できていたかもしれません。