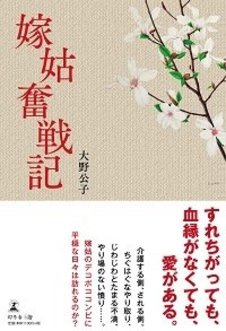癇に障るお見舞いと姑の不思議な言動
姉たちが来ると丁寧に礼を言い、話をする。普通と変わらない。しかし、二、三時間も居ると異常さが分かり、顔を見合わせている。
「これじゃやりきれないわねえ。介護する側が潰れないようにしなきゃ。何か手伝うことがあったら遠慮しないで言って」と言ってくれる。看病や介護する者にとって、現状を分かってくれ、愚痴を聞いてくれるのが最高の手伝いなのだ。相手にとっては迷惑なことだろうが、こちらはそれで元気を取り戻し、また介護が出来るのだ。
ひとめ見て、「こんな患者さんなら楽だ。親を看るのは当然と違うか」など言った見舞い客が帰った後は心穏やかならぬものがあり、見舞品を捨ててしまえと思ったほどだ。
その日の夜中におむつに手を突っ込み手がうんちまみれ、当直の看護婦さんと洗浄したり消毒したりシーツを替えたり大変だった。本人は夜中のことはからきし覚えていない。
私が翌日そのことを言うと、「うち、ちゃんとトイレに行ったで」と言う。「看護婦さん二人と三人で大変だったのに覚えてないの?」と言っても、そんなことするかいなと、おむつに手を突っ込む。「それ、そんなことするから手に付くのやないの、やめて」と言うと、突っ込んでへんでと言い張る。
無意識にするのだろう。これでは言っても仕方がない。困ったものだ。これがショックだったのかどうか分からないが、この日は日中もかなり混乱する。「今日はお祝いの膳やから全部食べなあかん」と今まで食べるのを嫌がった食事をぺロリと平らげる。
「何のお祝いなの?」と聞くと、「今日は成人式やろ」と言う。およそ冠婚葬祭、祝祭日には無関心、不参加を通して来た姑が入院してから異常なほど関心を持つのはどうしてなのか、不思議でならない。
本記事は幻冬舎ゴールドライフオンライン掲載の『嫁姑奮戦記』を再編集したものです。