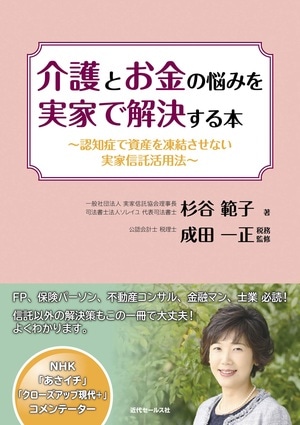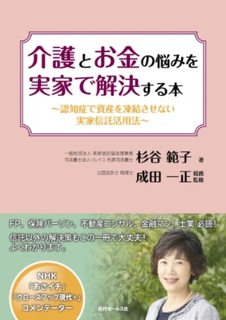認知症になっても間に合う「資産凍結」の回避手段は?
前回の記事『自宅も「空き家」と化す…親の認知症で、資産凍結という恐怖』では、資産凍結を回避する方法として「家族信託」を紹介しました。信託により、柔軟な形で親の資産を守ることが可能になります。本記事でも引き続き信託の理解を深めるために、人のライフステージを追って見てみます。

人には、「健常期」「能力減退期」「能力喪失期」「相続」「二次相続以降」と、5つのステージがあります。
ライフステージ(1)「健常期」
この時期は判断能力があり、財産管理を自分で行うことができます。また、将来を見据えて契約を結んだり、遺言を作成したりすることも可能です。ただ、残念ながら、元気なだけにこの期間に認知症や相続対策をしておこうと決意する人はあまり多くありません。
また、「遺言」は、亡くなる直前に遺す「辞世の句」という意味で使われることもあり、親に遺言を書いてもらうにはハードルが高いと感じている家族が多いようです。なお、契約を結べるのは成年に達してからですが、遺言は未成年者でも15歳になるとすることができます。
ライフステージ(2)「能力減退期」
この時期は、病気やケガ、高齢により判断能力が落ちてくる時期です。認知症の初期段階でもあり、昔のことはよく覚えているのに短期記憶が苦手になったり、何度も同じことを話したりするなど、多くは記憶の障害から始まるようです。ただ、認知症の診断が出てもあきらめてはいけません。契約の内容が理解できれば、間に合う可能性もあります。
なお、この時期はまだ判断はできるので、成年後見人を付けて代理をしてもらうことはできません。
法律行為が一切不可能に…万人が備えるべき期間
ライフステージ(3)「能力喪失期」
この時期は判断能力がなくなり死亡するまでの期間です。いわゆる、“ピンピンコロリ”でほとんどこの期間がない方もいるでしょうし、脳梗塞で倒れて10年以上寝たきりの方もいます。しかし、「誰も自分で『その期間』は選べない」ことに気づいてもらう必要があります。
この期間に入ると法律行為が一切できないので、もし、それらが必要なら成年後見人を付ける必要があります。「健常期」に自ら任意後見人を選んでおけばその人が後見人になれますが、何もしていなければ、家庭裁判所が選んだ後見人が付く「法定後見」になります。
自分ではこの「能力喪失期」が長くなるのか短くて済むのかが分からないので、この期間に備えた対策は万人がとるべきでしょう。
遺言・信託の併用で「二次相続以降の安心」を実現
ライフステージ(4)「相続」
本人が亡くなると成年後見は終了します。死亡後は相続人が本人として手続きなどを行います。遺言は健常期に作成しておきますが、亡くなるまでその効力は生じません。本人が亡くなってから「遺言執行者」が遺言の内容を実現することになります。
遺言については「まだ早い」「そのうち書くよ」などと、書かない理由をよく耳にします。しかし、能力を喪失したり亡くなってしまってからでは後の祭り。遺された相続人が困ってしまいます。「誰も自分では『いつ』自然死するかは選べない」ことに気づいてもらう必要があります。
筆者は実際に公正証書遺言を作成しました。遺言書の案を書いてみると、空の上から家族を見下ろしているような気持ちになりました。遺言は死後における財産の処分の方法を決めるものですが、「付言事項」といって法律以外のことも書くことができます。
その付言事項に家族への感謝の気持ちなどを著したら、家族への愛情が再認識できました。さらに、「死」と真正面から向き合ったことで、自分が今後、どのように生きるべきかを深く考えることができたように思えました。
家族には遺言を作成したことのみを伝えて、内容はあえて伝えていません。しかし公正証書にしたことで、自分の死後は必ず遺言を開いてもらえるという安心感があります。
2020年7月10日から、公正証書にしなくても自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるサービスが始まりました。生前に遺言書の存在を明らかにしておけば、遺族に必ず見つけてもらえますし、費用面や手続き面でのハードルも下がるので、この遺言預かりサービスの利用を促したいところです。
ライフステージ(5)「二次相続以降」
遺言では、本人が死亡したら財産を誰に相続させるかを決めることができますが、遺産を相続した人が死亡したら、次は誰に渡すかということまでは決められません。たとえば、1番目は妻に相続させて、妻が亡くなったら2番目には娘に相続させるという遺言を公証人は認めてくれません。自筆証書遺言で書き残したとしても、現在の判例のもとでは効力は生じません。
信託は健常期に契約を結ぶことで、財産の名義を変えて家族など信頼できる人に管理してもらえるので、能力減退期も能力喪失期もまったく影響を受けません。さらに、本人が亡くなった後に誰に財産を継がせるかだけでなく、その継がせた人が亡くなった後は誰にするか、さらにそれ以降も信託契約を継続することができるので、戦前の家督相続類似の承継が可能になります。
先祖代々の不動産や会社の株式など、血縁を中心に承継したいと考えている家族にとっては、信託を活用することでそれらが実現可能となります。
※ 実家信託は司法書士法人ソレイユが商標登録しています。
杉谷 範子
司法書士法人ソレイユ 代表
司法書士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】