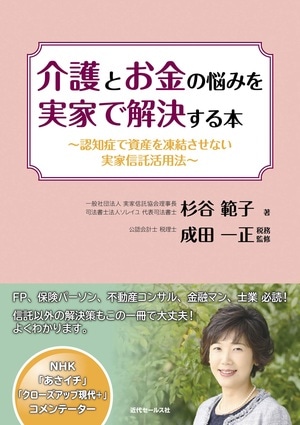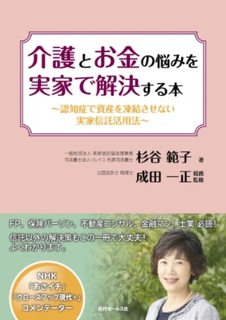「立て替えた親の介護費用」は戻ってこない可能性大
実家信託のメリットは、老人ホームの費用捻出のために実家を売却したいときに、すぐに対応できるということですが、お子さん自身、金銭に余裕があるため、親の財産を処分しなくても自分の金銭で賄えると思っている方もいます。
都心の一等地に住む長男Aさん(55歳・男性)には、2人の姉がいます。地方都市に住む両親が老人ホームでお世話になってもAさん自身、かなりの蓄えがあるため、実家を処分しなくても、Aさんがその費用を立て替えて、親の相続のときに精算してもらえばいいと考えています。

Aさんの場合も実家信託は必要でしょうか。答えはイエスです。
親の介護には親のお金を使うことが原則です。子どもが自分の金銭を使って親の面倒をみるとき、子どもは「親へ金銭を貸し付ける」とか「立て替える」という認識ではないでしょうか。貸付には、貸す人と借りる人の金銭消費貸借契約が必要ですが、親の判断能力がない状態で立て替えた場合、契約自体が成立しません。
ところで、民法では「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条第1項)」と規定しており、家族間での扶養義務を負わせています。つまり、『子どもが子どものお金を使って親の面倒をみるのは当たり前』ということです。
仮にAさんが親の療養介護に関わる費用を出したのちに、親が亡くなり遺産分割協議をしたとします。当然、Aさんは親の生前に立て替えた分を返してもらおうと申し出たら、姉2人から「Aさんは両親の病院代や施設代を肩代わりしていたけれど、それは立て替えではなく扶養義務の範囲内でしょう」と言われることも想定されます。
このように法律が全面に出ると、すでに払っていた療養看護費用分を相続で調整してもらえないおそれがあります。
介護費用だけではない…実家の「空き家化」という問題
たとえ相続人が調整してくれても、相続税を申告するときに債務として認めてもらえないおそれもあります。立て替えたことを証明するには、親子間でも「金銭消費貸借契約書」を作成して、確定日付を取ったり、公正証書にしておく必要があります。
しかし、親の判断能力がなくなってしまったから、立て替える必要性が出てきたのであって、立て替えのときに親と金銭消費貸借契約を結ぶことは不可能です。
また、実家信託の必要性はお金の問題だけではありません。お金の調達には心配なくても実家が空き家になってしまい、管理に手間がかかったり火災の心配もあります。そこで、実家の空き家化を防ぎ、親の財産から介護費用を拠出することは必要なため、「介護費や医療費を立て替えなくても済むように信託しておくよ」と父はAさんに信託することにしました。
<長男Aさんと両親へのアプローチトークの例>
「長男Aさんは、ご両親様に何かあっても、ご自身の蓄えで費用などを立て替えられるとおっしゃっていますが、実は、金銭消費貸借契約を結ばずにお子さんが親御さんのお世話の費用を出されるのは『持ち出し』になってしまい、『親子間での扶養義務』と言われてしまいます。
つまり、遺産分割や相続税の申告のときに、控除されないこともあるということです。
親御さんの医療費や介護費用は親御さんの財産を使うことで、これらの問題はなくなります。信託で早めに防衛されるとよいのではありませんか?」
※ 実家信託は司法書士法人ソレイユが商標登録しています。
杉谷 範子
司法書士法人ソレイユ 代表
司法書士
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】