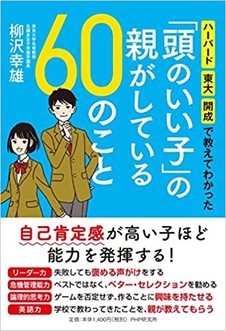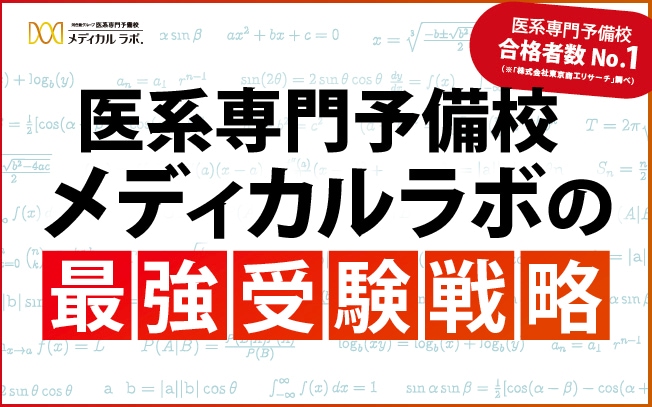最近よく聞く「アクティブ・ラーニング」とは?
昨今「アクティブ・ラーニング」という言葉をよく聞くようになりました。これも、新学習指導要領に盛り込まれている内容です。もともとは大学生に向けての知識や学問の伝達手段として重要視されていましたが、今は小学校、中学校、高校も、すでに実施しているところが多数です。
文部科学省によれば、アクティブ・ラーニングとは、「学びの量とともに、質や深まりが重要であり、子供たちが『どのように学ぶか』についても光を当てる必要があるとの認識のもと、『課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び』」(文部科学省ホームページより)と説明しています。
そして、「子供たちが『何を知っているか』だけではなく、『知っていることを使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか』ということであり、知識・技能、
思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力や人間性など情意・態度等に関わるもの
の全てを、いかに総合的に育んでいくか」(同前)に意義がある、とも述べています。
日本では、おもに一方向型の授業が行われてきたが…
日本では教師が知識を生徒たちに伝える一方向型の授業を中心に、学校教育が行われてきました。生徒は知識を教員から吸収する、つまり受け身(パッシブ)の教育スタイルが主でした。
しかし、アメリカでは自らテーマを決めて文献を探し、自分で情報を集める。そして自分なりの論理の構築をしていきます。その間には、仲間との討論などもある。つまり自分から積極的(アクティブ)に発信する教育スタイルが知識の定着に役に立つことが理解されるようになってきました。
そもそも教育は、一方的に授ける形から始まりました。というのも、教育は宗教から発生しているからです。教会のミサにしろ訓話にしろ、知識は常に権威でした。師が「こうですよ」と言ったことを、信者は受け入れるのです。師から信者集団への一方通行でした。
これはキリスト教だけでなく、中国でも論語は「子曰く」で始まっている。日本の寺子屋でも同じです。
しかし、この伝え方で生徒たちの頭の中に定着しているかというと、それほど定着していないということに気がついた。なぜ定着しないのか、定着させるにはどうしたらいいのか、と考えたときに、アクティブ・ラーニングが生まれたのです。
頭の中にある見聞の定着=とにかくアウトプット
頭の中にある見聞をどう定着させたらいいのかというと、とにかくアウトプットさせることが大事だと。自分から発信するときに、本人の中でもその概念が定着するのですから、とにかく表現させようということになりました。
一方的に授けられる師の話を聞く、これは受け身の学習です。受動態、つまり英語
で言うとパッシブな学習です。これの反対が能動態の学習。能動とは「アクティブ」
なので、アクティブ・ラーニングと呼ばれるわけです。
ただ、座学の場合であっても、「アクティブ」にすることはできます。生徒たちがそこで学んでいることについて、咀嚼したものを表明しないといけないという環境に常に置かれているのが、アクティブ・ラーニング。
先生が講義をしているのだけれども、いつ自分の意見を求められるかわからない。「こう聞かれたら、こう言おう」と常に考えながら身構えている状態を作る。そして生徒は、指名されたらすぐに答える。発言に慣れている子なら、時間配分までして発言する。そういう教室を作ることが、アクティブ・ラーニングです。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】