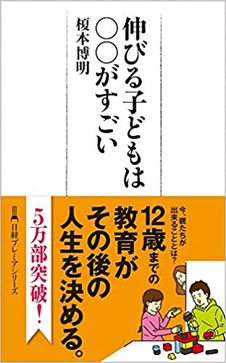「生徒が傷つかないように」…実力の差に蓋をする学校
子どもたちは、失敗することを通して、現実を生き抜く上で大事なことを学んでいくのである。それなのに、子どもを教育する立場にある大人たちがそこを見逃し、失敗を極力排除しようと過保護な環境をつくってしまっているように思われてならない。
運動会の徒競走で順位をつけなくなったことが話題になったのは、1990年代頃だったと思う。順位をつけないだけでなく、差がつかないように実力が同程度の子ども同士を走らせるようになっていた。
その頃、私は教育委員会関係の仕事をしており、このように足の速さ・遅さという現実に存在する実力の差に蓋をすることの問題点を指摘したものだった。大切なのは、実力の差に蓋をすることではなく、足が遅いからといってバカにしたり、引け目を感じたりしないように教育することではないかと。
その後、学芸会などでだれを主役にするかに気をつかったり、みんなが主役気分を味わえるような工夫をしたりするようになったのも、わが子をなぜ主役にしないのかと文句を言うクレーマー化した保護者への対応とも言われているが、要するに主役になれなかった子が傷つかないようにという配慮によるものだろう。
「ほめて育てる」とか「叱らない教育」といったキャッチフレーズも、1990年代あたりから急速に日本社会に浸透していったが、これも子どもたちを傷つけず、できるだけポジティブな気分にさせてあげようという時代の空気によるものと言える。
塾や学校で懇切ていねいな指導をするのも、子どもたちが失敗して傷つくのを防ぐためと言えるが、それが売り物になるのも、子どもたちを傷つけるのはよくない、できるだけ子どもたちが傷つかないようにすべきといった価値観が広く共有されているからに他ならない。
コーチングの手法を応用した、子どもを傷つけない子育ての仕方がマニュアル化されたりして、子育てをする親たちは、子どもを傷つけないような言葉づかいを心がけたり、子どもをひたすらほめてポジティブな気分にさせようと気をつかう。
失敗による挫折感を子どもたちに与えない教育法が推奨され、教師たちは、子どもたちが失敗しないように手取り足取り導き、また子どもたちがポジティブな気分になれるように事あるごとにほめまくる。

ここで改めて考えなければならないのは、子どもたちが傷つかないようにという配慮がほんとうに教育的なのだろうかということである。そもそも子どもたちが傷つかないようにといった配慮が強まってから、はたして子どもや若者の心はたくましくなっただろうか。嫌なことがあっても、思い通りにならないことがあっても、容易には傷つかず、前向きに頑張り続けられるようになっただろうか。むしろ逆に、傷つきやすい子どもや若者が増えたのではないだろうか。
失敗を過度に恐れる子や若者が目立ち、また「心が折れる」というセリフを耳にすることも多くなり、教育現場で傷つきやすい子どもや若者の対応に気をつかわなければならなくなっている現状をみると、傷つけないように配慮する子育てや教育は逆効果なのではないか。
子どもが傷つかないようにと大人たちが過保護な環境をつくり、子どもたちの失敗経験が奪われているせいで、失敗経験が乏しく、失敗に対する免疫がないため、いざ失敗すると大きな心の痛手を負う。立ち直れないほどの痛手を負う。そんなことが起こっているのではないだろうか。