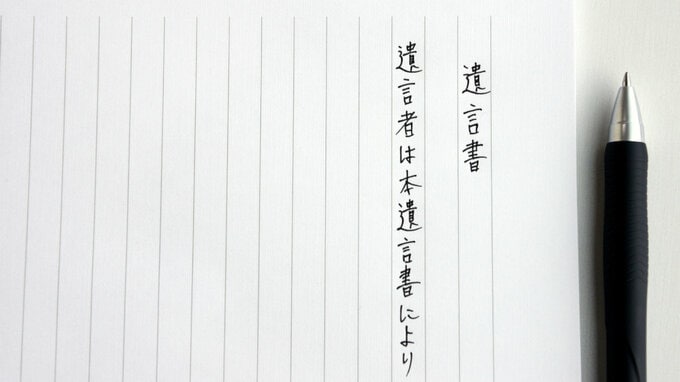遺書より「日頃のコミュニケーション」が大切
相続の本を開くと、ほとんどの本で「生前に遺言書を書いておくべき」「きちんとした遺言書があれば争族の大半は避けられる」といった趣旨のことが記されています。読み方によっては、「遺言書さえ書いておけば相続対策は万全」と思えてしまうかもしれません。しかし、それは危険な思い込みです。
私なりの意見を言わせていただくと、「遺言書はなくてもいいくらいだ」と考えています。なぜなら、遺言書があったことで、かえってトラブルになるケースも多いからです。死後に出てくる遺言書というのは、遺族にとってとても重い存在になります。
なぜなら、故人が〝最期に自分たちに遺したメッセージ〟として受け止められるからです。実際には、遺言書は亡くなるより以前に書かれたもので、場合によっては、死去の何年も前の元気な時代に書かれています。そこに書かれている言葉は、死を目前にした本人の言葉や気持ちではないかもしれないのに、あたかも〝死ぬ間際に伝えたかったこと〟かのように理解されてしまいがちです。そのことが、遺族の心を深く傷つける場合があります。
こんな例がありました。ある資産家の男性が亡くなりました。奥様はすでに他界されており、二人の娘さんがおられました。長女は都内の証券会社で働いていましたが、お母様が亡き後、お父様と同居するために仕事を辞めて家に戻り、家業を手伝っておられました。
二女は隣県に嫁ぎ、車で1時間ほどのところに住んでいます。男性は亡くなるまでの約2年間を自宅療養していましたが、その介護は長女と二女が分担しながら行っていました。平日の日中は長女が仕事に出てしまうため、介護サービスを頼んだり、二女が往復2時間をかけて通っていました。夜間や週末は長女が介護していました。
さて、男性が亡くなり、遺品整理をしているときに遺言書が出てきました。娘さんたちは二人で「お父さん、私たちに内緒でこんなものを遺していたのね。私たちのことが最後まで心配だったのかしら」などと言いながら、温かい気持ちで開いてみました。ところが……。
遺言書に書かれていたのは、家業と長女のことばかりでした。「会社の資産は長女に相続してほしい。自分に代わって会社を守っていってほしい。この自宅は長女にそのまま住んでもらいたい」など、最後まで読んでも二女の名前は一度も出てきませんでした。読んでいくうちに二女の顔色がみるみる変わり、硬く表情をこわばらせたまま押し黙ってしまいました。
長女は長女で、自分のことばかり書かれていることが申し訳なく、妹に何と言葉を掛けていいかわからずに、こちらも押し黙ってしまいました。二人とも、お父様を偲んでこぼれた涙が、すっかり乾いてしまいました。そうして皮肉なことに、遺言書が出てきたことで、姉妹の間に大きなわだかまりができてしまったのです。
遺言書では長女が自宅や会社関連の財産を受け継ぐことになっていましたが、財産はそれ以外にも預貯金や賃貸マンションなどいくつかあり、そちらを二女が相続すれば、額に多少の偏りはあるにせよ、それほど不公平な遺産分割でもありませんでした。
しかし、二女は自分の存在が遺言書で無視されていたことに強いショックを受け、遺言内容を素直には聞けなくなってしまいました。この段になって、長女から私に相談がきたのですが、私が二女に話を聞くと、「お父さんは結局、お姉ちゃんのことだけが大事で、私のことなんてどうでもよかったのよ。私だって病気の身体を抱えながら、父の介護を頑張ったのに。お姉ちゃんが悪いわけではないけど、どうしても釈然としない」と訴え、ポロポロと涙をこぼされました。
長女のほうも「妹の前で遺言書を読んだのは間違いだった。でも、まさか父があんな遺言書を残しているとは思わなくて。お父さんは、自分だけでは遺言書なんて書けないから、遺言書の書き方をアドバイスした弁護士に怒りを覚える」と妹に同情を示しながら、「それでも、妹に会社の財産が渡ってしまったら、この先やっていくのが難しくなる。どうにか妹には引き下がってほしい」と言います。
私も何とか話し合いで穏便に解決してさしあげたいと思いました。けれども、事はそんなにうまく進みませんでした。事態を聞きつけた二女の旦那さんが横から口出しをしてきたのです。二女に対して「お前は娘なんだから、もっと財産をもらえる権利がある。君のお姉さんは私立の大学に行ったり、留学させてもらったりで、たくさんお金をかけてもらっているじゃないか。それに比べて、君は短大しか出してもらっていない。だから、その分も多くもらっておかしくない」などと情報を吹き込み、二女を焚(た)きつけました。
二女の中で、父に愛されなかったという悲しみの気持ちが、次第に長女への嫉妬に変わり、やがて「姉にばかりいい思いはさせない」という恨みや憎しみへと変わっていきました。結局、私の手には負えないところまで関係がこじれてしまい、その後は信頼のおける弁護士の先生を紹介することくらいしか、私はお世話させていただくことができませんでした。
遺言書を過信して頼りすぎないこと
私が思うに、お父様は長女も二女も等しく愛しておられたと思います。きっと「そんなことは言わなくても伝わっている」「愛しているよ、ありがとうなんて、今さら改めて言わなくても」と思っておられたのでしょう。だから、あえて事務的なことしか遺言書にお書きにならなかったのだと推察します。
けれども、これは私が他人で、客観的な立場にいるからわかることで、当事者はそうはいきません。遺言書を受け取る側としては、「お父さんの最後の言葉だからこそ、私の名前を一度でも呼んでほしかった」と思うのは当然の気持ちです。下手に遺言書を残して遺族の気持ちを傷つけてしまうと、円満な相続どころか、生前の楽しかった思い出や美しい思い出までが、すべて台無しになってしまうこともあるのです。
大事なのは、遺言書を過信して頼りすぎないことです。私が「遺言書は不要」といった真意は、遺言書なんて書いても役に立たないという意味ではなく、「遺言書が不要なくらい、生前から家族に意思や気持ちを伝えておきましょう」という意味とご理解ください。
日頃から感謝の気持ちを伝えたり、自分の考えや意向を話したりしていれば、遺言書など本来は必要ないはずなのです。遺族の心にご主人の想いが届いていれば、その意を汲くんで〝万事よきように〟やってくれることでしょう。逆にいえば、遺族の心に届かなければ、いくら遺言書を書いても無視され、院長の希望通りには実行されない可能性が高いです。
生きているうちにやれるだけのことはやり、後は遺族を信じてお任せするというのが、死にゆく者の最もスマートな旅立ち方ではないでしょうか。奥様には、ご主人が思い残すことなく子らに想いを伝え、安心して旅立てるようにコミュニケーションの場をつくってあげていただけたらと思います。
たとえばの一例ですが、私自身が実践していることでいえば、月に一度は家族で食事会をするのを習慣化しています。息子たちは2人とも結婚していますが、お嫁さんや孫たちも一緒に全員で食事をし、お互いの近況報告をし合っています。民法上、お嫁さんやお婿さんには相続権はありませんが、実際の相続になるとその存在は無視できません。
先ほどの二女の旦那さんのように、マイナスの関わりをしてくるケースもないとは限りません。ですから、息子たちだけでなく、その家族も含めてコミュニケーションを密にしておくことが大事だと思っています。