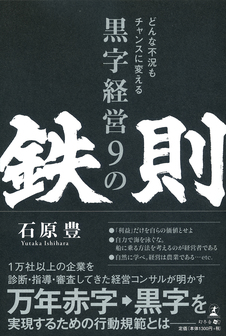他者を糾弾しがちで自らの非は省みない経営者
私は自宅に約300平方メートルの畑を持って季節の野菜作りに励んでいる。土を耕し、種を蒔き、芽吹いた草木を丹念に育てるこの贅沢な営みを続けていると、自然の恵みを感じずにはいられない。また、仕事でも、たとえば京都府京丹後市にある道の駅、丹後王国「食のみやこ」や京都府農業会議をはじめ、農水産業関係の企業や団体の税務顧問も数多く務めさせていただいている。こうした経緯で私は、昔から農業思考という独自の考察を深めてきた。これは農業に携わる人たちがどのような気構えや展望、覚悟を持って自然と対峙しているかを示したもので、その素晴らしさを商工業の世界に活かすことができれば、中小企業の経営はもっと良くなるとの確信がある。
現在は農業従事者が企業経営に学べといわれているが、私はその逆、中小企業経営者こそ、農業に学ぶべきなのだと思っている。たとえば稲作りは、まだ冬の厳しい寒さが残る3月に始まる。育いく苗びょうを経て、春を迎えた4月に田植えを行う。以降は稲の発育を促す管理を徹底し、実りの秋に収穫を迎える。シンプルな工程に思えるが、農業は天候との戦いだ。梅雨や夏の日照りをどうにか乗り越えたとしても、刈り取りを待つばかりの9月、大型台風に見舞われ、丹精込めて育てた稲が台無しになるリスクも覚悟しておかなければならない。すでに8割か9割まで進んできた今年の稲作投資は無駄になり、売上はゼロ。農業従事者の悲哀は筆舌に尽くし難い。まして近年は天候不順が著しく、稲作に限らず農作物全般が多大なダメージを被る例が増えている。さらに、農地が塩害に遭ったり、ビニールハウスが台風で破壊されたりするなど、経営の土台である農地に甚大な被害がもたらされる例も少なくない。そうなると投資が回収できないばかりか、新たに設備投資の負担まで重くのしかかってくる。
このように、天災による痛手はあまりにも大きいが、農業従事者は天に唾しても自分に返ってくるだけの空しさを知っているから、新たにプランを立てて種を蒔き、来年の実りを期待する。自責思考で対策を考えて愚直に実行に移すのみだ。このように農業とは、「他者に責任転嫁せず、自責思考で投資と回収のサイクルを回す経営」に他ならない。前回で触れた「灌漑用水」も、農業思考を象徴する事例の一つである。天の気まぐれに抗ったところで仕方がないと、潔く負けを認めて、自分たちができる対策に徹したのだ。自責思考=農業思考のなせる業である。
一方の商工業の世界はどうか。商工業でいう天災とはオイルショックやバブル経済崩壊、リーマン・ショック、急激な円高などを指すだろう。そうした有事の際、温室でぬくぬくと育った経営者は、やれ首相の指導力が弱いだの、やれ日銀の政策が間違っているだの、とかく他者を糾弾しがちで自らの非は省みない。農業のような厳しい自然との対峙を一度も経験したことがないのだろう。
昔ながらの育苗は厳しい作業だった。雪解け水が流れ込む季節に素足で田へ踏み込んで種もみを蒔いていく。まるで氷水に足を突っ込むような冷たさを、骨に刻み込んだことだろう。厳しい自然と対峙しなければ、本当の意味で危機意識を持つことはできない。氷水に丸裸でざぶんと飛び込み、あるいは焼け火ばしを握ってジュンと手を焼き、水の冷たさ、火の熱さを知って初めて競合と差し違えるほどの真剣勝負の経営ができるのだ。
どこか主体性に欠ける二代目、三代目
もっとも、昔の経営者は野心に溢れていた。戦後の混乱期から高度成長期にかけて裸一貫で会社を興した創業者たちである。ゼロからイチを生み出す賭けに人生を捧げ、塗炭の苦しみを味わい、結果に全責任を負う覚悟があった。だから当時の創業者は自責思考の人が多く、パイオニアとして日本経済の歴史に確かな爪痕を残しているのだ。
しかし、先代から会社を引き継いだ二代目、三代目はどうか。親が築いた土台に乗っかるかたちで経営をしているからなのか、どこか主体性に欠ける者が多い。もちろん優れた経営手腕を発揮している者もたくさんいるが、創業社長と比べると相対的に他責思考が多いように思えてならない。
私自身、かつて天災にすべてを奪われ、仕事の志を立てるために死力を尽くしてきた一人である。1953年9月、大型台風13号によって京都府丹波地方は未曾有の大洪水に見舞われた。その時、山林業を営んでいた我が家は、家屋や家財はもとより事業、田畑、その他一切を流失した。今日のごとくボランティアなし、社会保障なし・・・まさにないない尽くしのなか、当時高校2年生だった私は絶望の淵に立たされた。寒さと空腹に打ち震えながら迎えた冬の厳しさを、一生忘れないだろう。
長男だった私は、「300余年続いた家を再興し、身を立てねばならない」との志を胸に、19歳の春、家出同様に京都市内に出てきた。昼はバイトに精を出し、夜は経理学校で学ぶ日々。会社勤めや商工相談所勤務をしながら、やがて「俺は経営コンサルタントを目指して税理士の資格を取りたい。それで身を立てて家を興すのだ」と一念発起し、税理士国家試験に挑み始めた。
試験が行われる8月までに残る日数は半年足らず。最も得意な簿記論一科目に絞り、十何年ぶりの簿記教科書を引っ張り出して受験勉強を独学で始めた。朝6時、身支度を済ませたら朝食もとらずに職場に出向き、「これで遅刻はなし」と一心不乱に教科書に没頭した。帰宅後は、晩飯をかき込んで深夜まで机に向かい、4〜5時間の睡眠を取っては飛び起きて職場に向かう毎日だった。そうした生活が半年足らず続き、延べ600時間の勉強の末、簿記論の一部科目合格通知を手に取ることができた。これが税理士への記念すべき第一歩である。
翌年は1100時間かけて財務諸表論に合格。残り3科目は、あえて難しい直税3法に挑戦すべく法人税法と所得税法を選択した。2年かけて2科目とも合格し、相続税法を最後に苦節5年で税理士免許を取得したのだった。その後、会計事務所の立ち上げと同時に株式会社京都ビジネスコンサルタントセンターを設立。税理士という国家資格を武器とした経営コンサルとして立身すべく、経営の大海原に船出したのだ。
しかし、開業後の生活がこれまた凄まじかった。前職で受け取った退職金は38万円。デスクの購入や電話回線の開通といった諸々の経費を支払うと貯金は底を突き、開業資金はすべて借入で賄うしかなかった。妻には「1年間食わせる資金はないから、飢え死にする時は一緒に死んでくれ。もしヘソクリがあるなら、それで俺を1年間だけ養ってくれ」と宣言し、開業の日を迎えたのであった。
以降、半世紀、迷える中小企業の経営のサポートに人生を賭してきた。故郷を離れる際に誓った家の再興を成し遂げられたかどうかはわからないが、少なくとも農業従事者が自然に対峙するのと同等の厳しさで仕事に打ち込んできた自負がある。