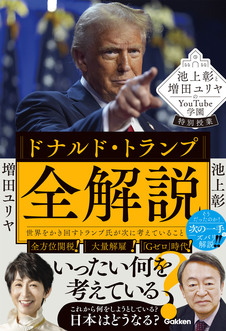タリフマン(関税男)には「元祖」がいた?〜「保護主義のナポレオン」と呼ばれた大統領〜
「私にとって辞書の中で最も美しい言葉は、タリフ(関税)だ」
そう述べるトランプは「タリフマン(関税男) 」とも呼ばれるが、実はアメリカには「元祖・タリフマン」が存在する。第25代大統領のウィリアム・マッキンリー (1897~1901年)だ。
トランプはマッキンリー大統領について「彼のリーダーシップのもと、アメリカは急速な経済成長と繁栄を享受した」「関税によってアメリカの製造業を保護し、国内生産を促進することでアメリカの工業化と世界進出を促した」などと絶賛している。
マッキンリー大統領が下院議員時代の1890年、下院歳入委員長として「マッキンリー関税法」を成立させた。この関税法によりアメリカが輸入する多くの製品の関税が引き上げられ、関税率はおよそ50%に達したといわれている。1896年には、関税によってアメリカに1億6,000万ドルの収入がもたらされ、国の歳入の最大の構成要素となったとの研究もある。
そうした成果から、マッキンリー大統領は「保護主義のナポレオン」と呼ばれるようになったという。
マッキンリー大統領は高い関税によってアメリカの製造業を保護しただけでなく、ハワイを併合し、スペインとの戦争でプエルトリコとグアムの割譲、フィリピンの金銭譲渡を認めさせている。また、マッキンリー大統領の後任であるセオドア・ルーズベルト大統領は、パナマをコロンビアから分離し、パナマ運河を建設している。パナマ運河も、トランプが現在、「アメリカの手に取り戻さなければならない」としている場所だ。
マッキンリーを絶賛するトランプ
マッキンリー大統領は、いわば帝国主義的な対外政策を取ってきたのだが、そうしたところもトランプにとっては「敬意を表すべき実績」なのかもしれない。アメリカの利益を第一に考え、他国に対して強権を振るう。関税を武器として使い、グリーンランドのようにアメリカにとって価値のある土地を「よこせ」と言ってはばからない。アメリカはあたかも100年以上前の価値観に戻ってしまったかのようだ。
トランプの「マッキンリー絶賛」はこれだけではない。就任初日の大統領令で、マッキンリー山からデナリ山に名前が変わっていた名称を、マッキンリー山へと戻している。もちろんマッキンリー大統領にちなんで名付けられたものだが、北米大陸最高峰の標高を誇ることから、「偉大な大統領」になぞらえたものだ。
マッキンリーへの思いは、トランプの就任演説にも表れている。
オバマ大統領時代のアメリカ政府が2015年にマッキンリー山をアラスカ先住民の呼び方であるデナリ山に改称することとしたのは、アラスカ州政府の40年にわたる要求に応じてのことだ。先住民にとって聖域とされてきたデナリ山は、先住民に敬意を表して元の名前で呼ばれるべきだとしたものだった。だがトランプは、こうした経緯も無視して「マッキンリー山」に戻したのである。
これはトランプのマッキンリー大統領への敬意だけにとどまらず、「オバマのやったことをすべて覆したい」とする執念もあるのかもしれない。
マッキンリー大統領は高い関税によって「強いアメリカ」を取り戻した。トランプもこれに倣いたいということのようだが、現在のアメリカには当時ほど守るべき製造業が存在せず、第二次産業である製造業はGDPの2割弱にとどまる。むしろ、全体の6割近くを情報、通信、金融などの第三次産業が占めている。
100年以上前のまったく産業構造が異なる状況を現在に当てはめ、マッキンリー大統領と同様に関税率を引き上げたことで同様の成果を上げられると考えるのは無理筋としか言いようがない。
池上彰
ジャーナリスト
増田ユリヤ
ジャーナリスト