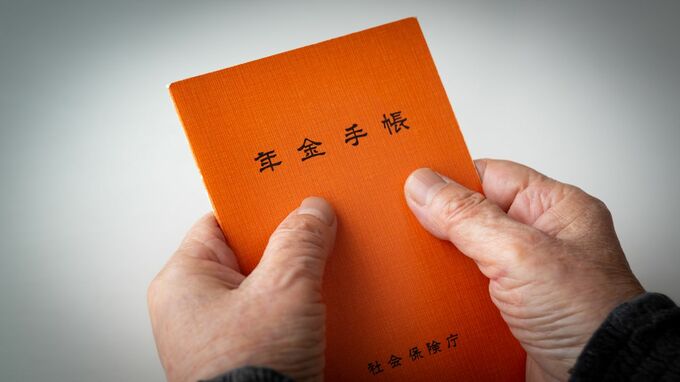老後のための要貯蓄額が約3,500万円に
所得代替率の2割近い削減は、老後生活に極めて大きな影響を与える。2024年におけるモデル年金額は月額23万483円だ(※1)。この17.6%は4万565円。年間で48.7万円だ。
だから、年間の不足額が、現状より48.7万円だけ増えることになる。30年間では、必要資金が約1,460万円だけ膨らむ。それまで老後生活のための貯蓄が2,000万円必要だと考えていたものが、3,460万円必要ということになる。
所得代替率がこのように低い水準に落ち込むのは、2057年度のことだ。だから、だいぶ遠い将来のことだと思われるかもしれない。しかし、就職氷河期の人々(団塊ジュニア世代)は、直接に影響を受ける。
実際には、もっと早い時点で影響が生じる可能性が高い。なぜなら、将来時点でこのような事態が予測されれば、それをいつまでも放置してよいとは思えないからだ。
これに対応するために、きわめて大きな制度改革が必要とされるだろう。例えば、支給開始年齢の引き上げが、避けられなくなるだろう。そうなれば、65歳からある時点までの年金を得られなくなる世代が出てくる。したがって、老後生活資金が、いま考えているより多く必要になる。
※1 日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」による。なお、本章の2で述べたように、「財政検証結果の概要」(給付水準の調整終了年度と最終的な所得代替率の見通し)には、「所得代替率に用いる年金額は、平成16年改正法附則第2条の規定に基づき前年度までの実質賃金上昇率をすべて反映したもの」と注記されており、具体的な数字として、「夫婦2人の基礎年金13.4万円と夫の厚生年金9.2万円」が示されている。この合計額は、22.6万円になる。
ゼロ成長ケースでは、老後のための要貯蓄額が5,000万円を超える!
しかも、これが最悪ケースであるわけではない。ケース④(ゼロ成長ケース)の場合には、国民年金の積立金が2059年度に枯渇し、それ以降は賦課方式に移行するため、厚生年金の所得代替率が、2060年度に36.7%に低下するのだ。
36.7%とは、2024年度の6割の水準だから、現状からの減少額は、モデル年金で言えば、月額9.2万円、年額111万円となり、30年間では3,319万円となる。したがって、これまで「2,000万円必要」と言われていた老後生活のための要貯蓄額は、5,000万円を超えてしまう! これでは、ほとんどの家計がお手上げだろう。
話はこれで終わりではない。ケース④よりさらに悪いケースも、考えられなくはない。円安のために日本は外国人労働者を惹きつける魅力を失っている。だから、外国人労働力が増えることを前提にした現在の財政検証は現実的でなくなっていると考えることもできる。
いますぐにも議論を始める必要
政府が公的年金制度について何らかの措置を取らなければならないのは、次の財政検証までの間に所得代替率が50%を切る事態になった場合だ。
だから、今回の財政検証によれば、どのケースであっても、いま直ちに政府が何らかの措置を取る必要はない。措置を取るのは、ずっと後のことであってもよい。
しかし、問題を放置すれば、取るべき措置は大きなものとなる。例えば、支給開始年齢の引上げには、長期間を要する。仮に65歳から70歳に引上げるとした場合、ある時点で一気に5年引上げるわけにはいかない。最低限、2年間で1年引上げるのが限度だ。
したがって、5年引上げるには、10年間が必要だ。だから、いますぐにでも議論を始め、準備を開始しなければならない。
野口悠紀雄
経済学者
一橋大学名誉教授
注目のセミナー情報
【資産運用】4月12日(土)開催
毎年8%以上の値上がり実績と実物資産の安心感
「アーガイル産ピンクダイヤモンド投資」の魅力
【資産運用】4月16日(水)開催
富裕層のための資産戦略・完全版!
「相続」「介護」対策まで徹底網羅
生涯キャッシュフローを最大化する方法
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】