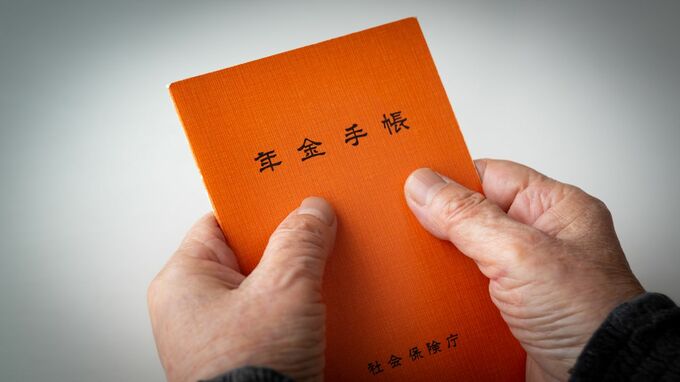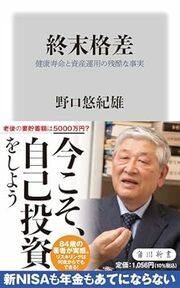蓋然性(確実性)が高いのは、過去30年投影ケース
2024年財政検証では、以下の4つのケースが想定されている。
①高成長実現ケース
②成長型経済移行・継続ケース
③過去30年投影ケース
④1人当たりゼロ成長ケース

そのうちのケース①(高成長実現ケース)とケース②(成長型経済移行・継続ケース)では、積立金枯渇や年金額の大きな低下などの深刻な問題は生じないとされている。そして、2019年財政検証に比べると所得代替率の見通しが好転している。
しかし、深刻な問題が生じないのは、ケース①と②に限ったことだ。そこでは、実質賃金の上昇率が、それぞれ2.0%と1.5%という非常に高い値に設定されているからだ。
ところが、日本の実質賃金は、長年にわたって減少傾向にある。こうした現状と比較すると、ケース①②は、非現実的だと言わざるをえない。
そこで、ケース③(過去30年投影ケース。出生中位、死亡中位、外国人入国超過数16.4万人)を見ることにしよう。この場合は実質GDP成長率がマイナス0.1%なので、日本経済が現在よりかなり悪化する見通しのような印象を受ける。
そして、実質GDPがマイナス成長を続けることは多分ないと考えられるかもしれない。しかし、今後の日本では、人口が減少することに注意しなければならない。そうした世界では、1人当たりGDPが増えてもGDP全体が減るのは、大いにあり得ることだ。
しかも、ケース③では、1人当たりGDPの伸び率は0.7%である。つまり、豊かさという点では、現在よりも状況は改善するのだ。だから、大いにあり得るケースだと考えることができよう。というより、これは、ケース①や②に比べて、蓋然性がずっと高いケースだと考えられる。
ケース③について、厚生年金の財政収支は、つぎのとおりだ。
収支差(保険料収入、運用収入、国庫負担の合計である「収入合計」と、基礎年金拠出金と報酬比例年金の計である「支出合計」の差)は、2024年度の13.9兆円から継続的に悪化し、2035年度に、8.8兆円と10兆円を割り込む。
そして、2080年度にマイナス3.9兆円と、マイナスに転じる。その後も、マイナス幅が拡大していく。2120年度における収支差は、マイナス20.4兆円だ。給付水準の調整は、比例年金では2026年度で終了するのだが、基礎年金では2057年度まで続く。
このため、厚生年金の所得代替率は、2024年度には61.2%であるものが、低下を続け、2030年度に59.9%と6割を下回り、2057年度からは50.4%となる。つまり、2024年度に比べて、82.4%の水準に落ち込む。