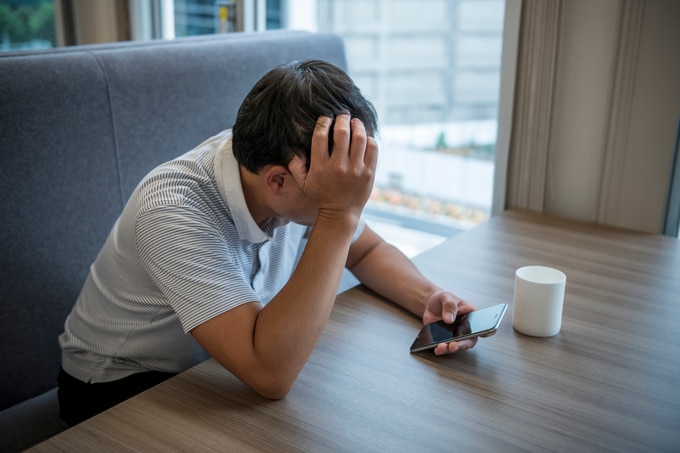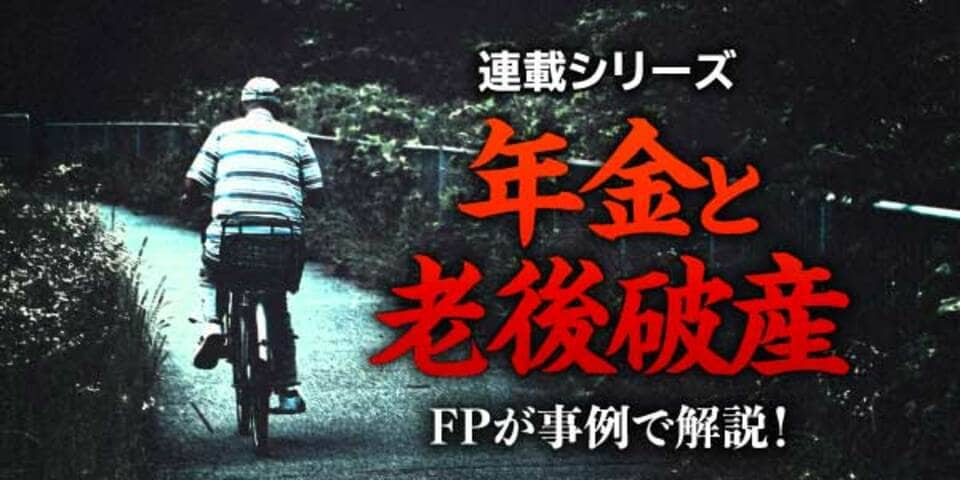2人なら将来の年金は月33万円のはずが…
遺族年金を受けられないことを知って、Tさんが思い出したのは、Nさんの生前一緒に確認した年金受給額です。もしお2人で長生きをされていれば、Tさんは約20万円、Nさんは約月13万円の年金を受け取れる見込みで、夫婦二人では年金が約33万円との試算だったそうです。
納得できないTさんは妻自身の年金があったはず、とさらに年金事務所で詳しく尋ねました。遺族年金には遺族にも要件があり、遺族が妻だった場合は55歳未満でも遺族厚生年金が受けられるが、夫の場合は年齢要件があるとのことでした。
もし反対の状況であれば、Nさんには65歳まで月約12万円遺族厚生年金が支給されただろうということです。また、もしTさんが55歳以上であっても遺族厚生年金の支給は60歳以降となり、65歳以降の遺族厚生年金については加入者本人の老齢厚生年金が優先されるため、受け取れないことが見込まれるとのことでした。
遺族年金の複雑さにTさんははがゆく、不条理を感じずにはいられませんでした。
遺族給付を受け取れる遺族の要件
遺族年金は、公的年金に加入している方が万が一の際、遺族を対象として支給されるものですが、支給には死亡した方だけではなく、遺族にも一定の要件があります。遺族の方に関する要件は以下のとおりです。
(遺族基礎年金の場合)
1.子のある配偶者(内縁を含む)
2.子
※子とは18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級または2級の状態にある方となります。
(遺族厚生年金の場合)
亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族
1.子のある配偶者
2.子
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母
※子・孫とは18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級または2級の状態にある方となります。
遺族厚生年金の受給が優先されるのは子とともに配偶者ですが、配偶者が夫である場合には55歳以上であるという年齢要件があり(父母・祖父母についても同様に55歳以上)、かつ支給は60歳からになります(遺族基礎年金をあわせて受給できる場合であれば、55歳から60歳までのあいだであっても遺族厚生年金を受給可能です)。
また、生計維持要件もあり、将来にわたって年収が850万円以上見込まれる方も支給の対象外となります。Tさんの場合にあてはめると、Nさんは厚生年金保険に加入しており、死亡した方に関する要件は満たしていましたが、お子様はいらっしゃらなかったため、Tさんに遺族基礎年金の支給はありませんでした。
一方TさんはNさんの配偶者であり、遺族厚生年金の支給の可能性が残されますが、54歳であり、わずか1年ですが年齢要件を満たしていないため、遺族厚生年金を受けられない、ということとなったのでした。