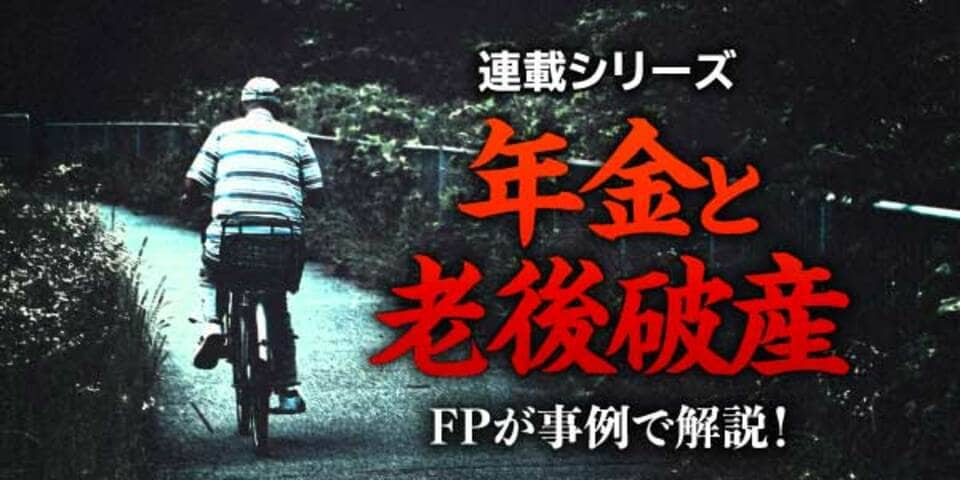70歳まで働いた場合の年金受給額
中野さんが65歳以降も勤務した場合の年収は大体400万円程度、70歳まで働いて年金の受給開始を遅らせた場合には、年金受給額は42%増えることになります。
すると、15万円受け取ることができる予定だった中野さんの年金額は、およそ21万円にまで増えることになるのです。
そして、65歳以降も勤務するため、公的年金の受給は65歳までの勤務の分よりも増えることになり、5年間で毎月約1万円を増額させることができます。
結果、70歳以降で受け取ることができる公的年金と、妻の年金の受給額を合わせると、31万円程度を受け取ることができ、毎月5万円程度は貯蓄に充てられそうです。つまり、5年間で貯蓄は300万円程度増やせる見込みになったのでした。この結果に、老後のお金の不安から少し解放され、中野さんは小躍りしました。
忘れてはいけない…「年金繰下げ受給」のデメリット
ただし、デメリットとして公的年金の受給額が増えることで税金、国民健康保険料が増えるという点があります。
公的年金は年間110万円まで非課税で受け取ることができます。そして、確定拠出年金や公的年金の受給額を合計した金額から110万円、もしくは所定の計算式で計算された控除額を差し引いた金額が雑所得として課税されることになります。
所得には所得税と住民税が課税され、さらに国民健康保険料も所得が上がると高くなります。仮に65歳から受け取っていた場合には、中野さんの場合、年間の受給額が約180万円ですから、所得は70万円となります。この場合、
所得税……約3,000円
住民税……約1万2,000円
国民健康保険料……約10万円
となります。合計すると、11万5,000円の負担となります。
しかし、70歳まで繰り下げして受け取った場合、
所得税……3万6,000円
住民税……7万9,000円
国民健康保険料……約19万5,000円
と、年間で合計31万円もの税金、国民健康保険料が課せられます。つまり、繰下げ受給をしない場合と比較して、年間19万5,000円程度負担が増えてしまう計算になるのです。
こういったデメリットもありますが、中野さんは、最終的に手元に残る金額を考えると公的年金を繰下げするほうがメリットが大きいと考えたため、繰下げすることに決めました。
公的年金は夫婦2人で生活するには十分なくらいに増額させることができ、貯蓄にも少しゆとりを持つこともできるようになりました。