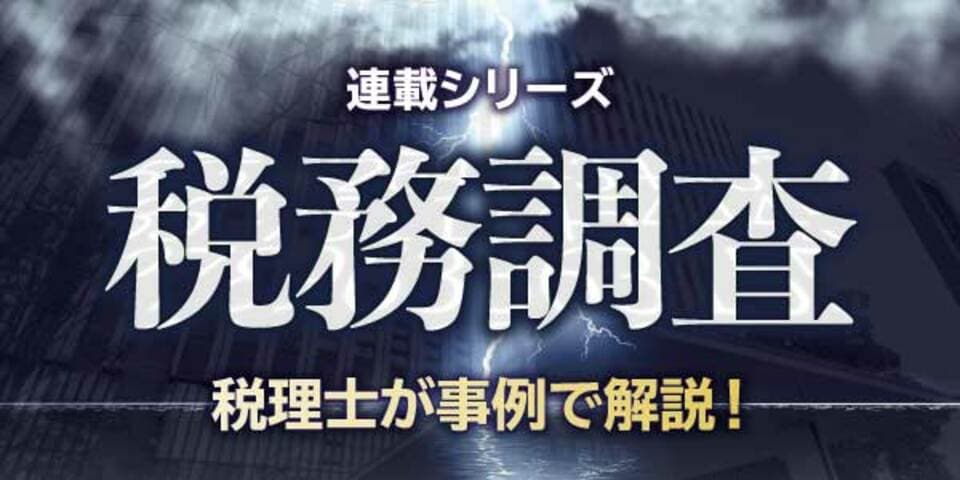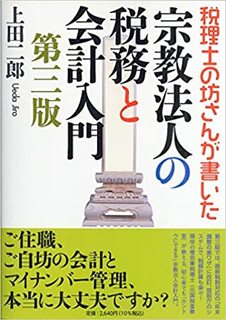元マルサの筆者が指摘する「不自然な課税処理」
また、この事件については、課税処理についても疑問を感じています。「揮毫料は志納金と考え、約20年前から申告していなかった」として、宗教法人でも住職個人でも申告していなかったことは、もちろん大問題です。
しかし一方で、住職は「揮毫料は……文化財を保護するために墨跡(禅宗の僧の書)などの購入に充て、個人的には使っていない」と話しています。一部の報道では、墨跡などは、承天閣美術館(相国寺の美術館)に収蔵していたとありました。
これらの報道が事実でしたら、揮毫料はすべて美術館の資産となっていたことになります。
つまり、本当は相国寺の収入であるが、経理上はお布施として処理(非課税)をしていたのではないでしょうか?
もし、住職が個人的な書家としての立場ではなく、相国寺派管長としての立場で揮毫の依頼を受けていたとしたら、揮毫料の帰属は宗教法人となる可能性があります。
20年間も申告していなかった揮毫料を、僅か3年の課税処理で終了しています。しかも過少申告加算税で調査を終了しているということは、うっかりミスだったということで、単なる申告漏れの問題です。
宗教法人の収入である揮毫料を相国寺の収益事業会計に入れず、お布施として非収益事業としていたなら単純なミスです。よって、揮毫料で買った墨跡などが美術館に所蔵されていたのではないか? 報道によれば、3年間で漏れていた金額は約2億円です。2億円もの申告漏れが「うっかりミス」で済むはずはありません。
以上のような観点から、かつて調査に携わった人間として、揮毫料を住職個人の収入とした課税処理に大きな疑問を感じざるを得ません。
これらの事実から見えてくる調査の実態は、揮毫料の帰属は本当は宗教法人の収入だったのではないか? ということです。
揮毫料がお布施と認定されることはありませんから、宗教法人で修正申告をしなければなりませんが、法人の過少申告加算税は5年間賦課されます。しかし、当時の所得税法では、過少申告加算税の賦課は3年間でした。
宗教法人で修正申告するよりも、住職個人で修正申告した方が納める税金が少なかったのではないか? そして、宗教法人による多額の修正申告ならマスコミへの公表は避けられません。このような理由から、住職個人の課税処理で終わらせることで、国税当局と住職側が合意したのではないでしょうか?
しかし、宗教法人に対する課税実務を知らない誰かがリークして、マスコミがそれに飛びつき、住職個人の顔までテレビ報道したのではないでしょうか?
想定の域をでませんが、大きな疑問の残る課税処理です。
上田 二郎
僧侶/税理士
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【2/25開催】
相続や離婚であなたの財産はどうなる?
預貯金、生命保険、株…各種財産の取り扱いと対応策
【2/26開催】
いま「米国プライベートクレジット」市場で何が起きている?
個人投資家が理解すべき“プライベートクレジット投資”の本質
【2/28-3/1開催】
弁護士の視点で解説する
不動産オーナーのための生成AI入門
~「トラブル相談を整理する道具」としての上手な使い方~