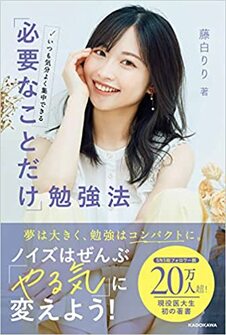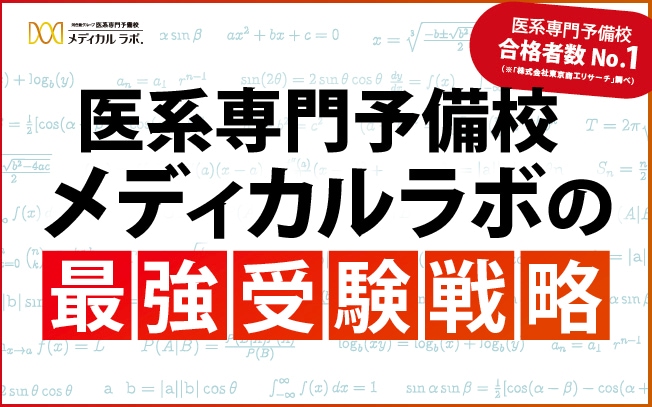参考書と授業のどちらを主軸に勉強するか?
独学で参考書学習を始めると、学校の授業との付き合い方に迷うことがあるかもしれません。
「参考書で勉強しているから授業を聞く必要がない」と感じることもあれば、「でも、先生に悪い印象を持たれたくはない」と思うこともありますよね。結論を言うと、教科・科目ごとに、勉強の軸を「参考書」と「授業」のどちらにおくかを決めるのが大事です。
志望校のレベルが学校の授業よりも上なら、参考書学習に重きをおく必要があります。その逆なら、学校の授業についていければ基本的には十分と判断できますが、授業についていけないのなら参考書学習は必要になってきます。
いずれにしろ、推薦入試を狙っている方は学校の授業をちゃんと聞いている姿勢を見せることは欠かせません。
大切なのは、授業時間を能動的に過ごすこと
学校の授業と参考書学習をどう両立するか、私の例を紹介しておくと、高2までは「学年で5番以内をキープする」を目標にしていたので、定期試験でそれなりの点をとるために合わない先生の授業以外は学校の授業に集中していました。
しかし、たとえば、自分がわかっている問題の解説をしている時間など、「意味がなさそう」「退屈だな」と感じるときは授業中に自分で問題演習をすることも多かったです。
長期休みの課題なども、受験に役立つと感じるものはやりましたが、意味がなさそうなものや簡単すぎるものは手を抜いていました(あまり大きな声では言えません)。
そして、少し早めですが高2の秋に受験勉強を始めてからは、二次試験で使う主要科目を中心に問題演習のいい授業も多かったですが、取捨選択を厳しくして参考書学習へシフトしていきました。
ただ、参考書学習をしていてわからない部分を学校の先生に聞く機会もあるかもしれないので、先生との関係性は良好に保っておいたほうがいいです。志望校のレベルや、クラスで自分がどの位置にいる必要があるかによって、授業へのコミット度は変わってきます。
大事なのは、受け身でなく能動的に時間を過ごすことです。私は、同じ授業時間を過ごしていてもライバル的存在のクラスメートより「充実した時間を過ごしたい」と、常に意識していました。