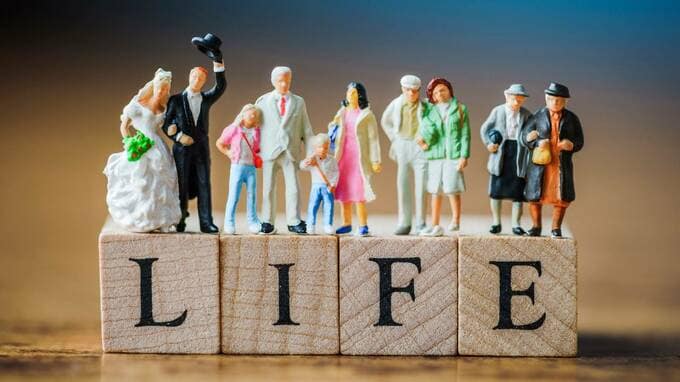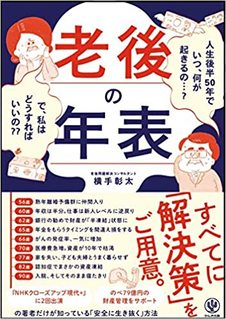相続トラブルを回避するには「遺言」が有効
こうした争いを回避するためには、遺言が有効です。ただし、認知症の疑いがある中での手続きは、かえって相続争いを招きかねません。
遺言の有効性を争う際には、「遺言無効確認訴訟」を行います。この裁判では、遺言した際に判断能力があったかどうかが焦点として争われます。
この「判断能力の有無」を証明することは容易ではありません。実際、筆者のお客様でも相続が発生してから遺言無効裁判で、解決するまで5年かかった方がいます。これは自筆遺言に限らず、公証役場で公証人の立ち合いのもとに作成したいわゆる公正証書遺言であっても争いになります。公証人も争いに巻き込まれることを嫌がるので、裁判に証人として出廷(しゅってい)しないこともあります。
筆者がお手伝いした案件でも、地方の公証役場で遺言の手続きをする際に、ビデオカメラで記録を残すことが条件のところがありました(ちなみにカメラ撮影は、法的義務にはなっていません)。トラブルに巻き込まれた時の説明資料として、この公証役場が独自に判断して決めたことです。
医師の診断書に加えて、本人の意思能力があった証拠をビデオカメラで残すことが、認知症の疑い、または認知症初期の段階では必要とされるケースが増えているのです。というのも、トラブルが多発しているから。
こうした相続争いのトラブルを防ぐためには、相続の専門家の協力を得ることが有効です。相続の専門家といえば、税理士や弁護士を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
ただ、税理士や弁護士だからといって、それだけで相続のエキスパートとは限らない点は注意が必要です。医師が内科や外科、眼科、耳鼻科など専門が分かれているのと同じで、弁護士や税理士の中でも得意とする分野、苦手とする分野があります。