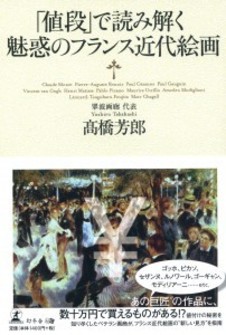フランスがモダン・アートの中心となった背景
世界の歴史を振り返ってみれば、多くの国が勃興して衰退し、栄枯盛衰を繰り返してきました。美術史の世界でも同様です。たとえば、日本で最も有名な名画は、1503〜1510年に描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』です。当時はルネサンス(再生)の時代で、西洋文化の古典であるギリシャ・ローマ美術をお手本にした人間賛歌の美術が栄えていました。

(画像はイメージです/PIXTA)
ギリシャと、それを受け継いだローマの美術は、現代における西洋美術の原点です。キリスト教の総本山ともいえるバチカンがイタリア半島にあることも含めて、イタリアは西洋文化の中心地であると考えられてきました。ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロといったルネサンスの三大巨匠がすべてイタリア人であるのも、ゆえのないことではないのです。
しかし、イタリアは政治や経済の中心地でなくなって久しく、美術もまた裕福なパトロンや貴族のいる他国で花開くようになります。
17世紀には、東インド会社を設立して日本との貿易も独占したオランダが、商業の中心地として黄金時代を迎えます。当時のオランダは、レンブラントとフェルメールという偉大な画家を生み出しました。また、地続きの隣国ベルギーにはルーベンスという巨匠もいました。
大航海時代に富を蓄えたのは、オランダばかりではありません。さきがけとなったスペインも、17世紀に黄金期を迎えていました。17世紀スペインの画家といえば、エル・グレコとベラスケスです。時代をちょっと下ればゴヤもいます。
18世紀には、絶対王政によって豊かになったフランスが、芸術の分野でも頭角を現し始めます。そして豊かになったフランスは、中産階級の勃興とともに、人権意識とフランス革命まで生み出しました。『アルプスを越えるナポレオン』のダヴィッド、『民衆を導く自由の女神』のドラクロワなどが活躍しました。
当時、ヨーロッパの激動の中心地となったフランス。そこでは、絵画をプロパガンダの手段として重視し、帝政を誇示するような作品を大量に作らせたナポレオンと、そのような国家からの押し付けに対して反発する若い芸術家とが対立し、美術を変革しようという意識が高まりました。18世紀から19世紀のフランスは、政治的にも文化的にも、熱気のある時代だったのです。
その結果、18世紀から20世紀にかけてのモダン・アート(近代美術)は、フランスを中心に発展することになります。ダヴィッドやアングルらの端正な新古典主義に対して、ドラクロワやジェリコーなどが民衆の側に立って、ロマン主義的な情熱にあふれる絵画を描き上げます。
その一方で、コローやミレーのように、目の前にある風景をそのまま描く写実主義の画家たちも現れました。また、コローやミレーが自然の風景を描いたのに対して、ドーミエやクールベは都市の猥雑な現実を写実主義で描こうとしました。
19世紀後半、フランス美術界に出現した「印象派」
そのような激動のフランス美術界に、19世紀後半に出現したのが、現在も世界中で愛され、根強い支持を集める印象派です。
初期印象派ともいえるマネやドガは、ドーミエやクールベの流れを受けて、きれいなものだけを描くという従来の絵画の約束事にとらわれず、決してきれいごとだけではない〝目の前の現実〞をそのまま描こうとしました。そのために、印象派は当時の画壇(美術界)から大声で非難と拒絶を受けたのです。
マネやドガに続いて、技法の面でも革命を起こしたのが、モネとルノワールでした。印象派の中心人物であるモネとルノワールは、それまでは光の当て方に注意を払って室内で丁寧に描かれていた絵画に対して、屋外の太陽の光の移ろいや乱反射をそのまま写し取ろうとしました。その技法は当初、軽薄な若者によるサブカルチャーと評価されました。しかし印象派の作品は、画家本人たちが亡くなる頃には、国立美術館に収蔵されるような権威となっていきます。
人類史上全体を俯瞰すると、権威が確立された後にはいつも、反権威による揺り戻しが起こるものです。印象派にとって、その反権威たる存在はポスト印象派でした。印象派が光の移ろいを捉えようとするあまり、対象物そのものが持つ輪郭や実体性を軽視して、しばしば抽象絵画のようになってしまったのに対して、セザンヌやゴーギャンやゴッホといったポスト印象派の画家たちは、モノの形態や存在感を重視しました。
しかし、印象派のすべてが否定されたわけではありません。19世紀に写真が一般に普及していく中で、写真のような写実的な絵画や肖像画に対する需要はだんだんと少なくなり、現実を写した絵画はそのアイデンティティを模索することになります。
そうして生まれた答えが、絵画は現実をそのまま模写するのではなく、画家の目で見て解釈した現実を表現するべき、という考え方でした。画家が現実を解釈するということは、いきおい画家個人の内面を描写することにもなります。
このようにして、世の中に初めて芸術家(アーティスト)が誕生したのです。
「職人」的な存在だった、かつての画家・彫刻家
絵を描く人や彫刻を作る人は、昔から数多くいました。しかし、彼らは芸術家というよりも、職人というべき存在でした。――では、近代に現れた「芸術家」と「職人」との違いは何なのでしょうか。大きく異なっているのは、「制作目的」です。仮に、両者の成果物が結果的に似通ったものになったとしても、その背景にあるものが大きく違うのです。
芸術家とは内なる欲求に突き動かされて表現をするものですが、職人は他者からの注文を受けて、それに応えるために制作を行います。もちろん、100%の芸術家とか、100%の職人といったものは存在しません。どのような芸術家にも、職人的に他人の需要に応えようとする部分はありますし、職人だって、発注者からの注文が曖昧な点に関しては自らの好むような表現で補おうとするものです。
しかし、その人が主に芸術家として表現をしているのか、それとも主に職人として制作をしているのかで、アイデンティティや生き方に差が出てきます。たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロといったルネサンスの三大巨匠は、基本的には職人でした。彼らの作品はすべて、貴族やパトロンの依頼を受けて制作されたもので、相手の注文や好みに応える形で修正もされています。
また、美術に興味がない素人に、ダ・ヴィンチとミケランジェロの絵を見せて、どれを誰が描いたか当てさせようとしても、恐らく正解は得られないでしょう。愛好家であればすぐにわかる違いも、門外漢には同じようなものに見えるはずです。なぜならば、どちらもルネサンス様式という枠組みの中で描かれているからです。それは、パトロンが職人に対して要請する様式でもありました。
これに対して、20世紀の画家――たとえばゴッホとピカソの絵を見比べてみれば、美術に興味がない人でも、その違いはすぐにわかるはずです。どの絵にも、ゴッホらしさやピカソらしさが厳然と存在するからです。例外はいくつか存在するものの、ゴッホやピカソは、基本的に誰かの注文で絵を描いていたわけではありません。ゴッホは生前ほとんど評価されなかった画家であったため、その絵のすべてが、誰に頼まれたわけでもなく、ゴッホ自身の内なる欲求に突き動かされて描かれたものです。
ピカソはゴッホと違って人気画家でしたが、「あれを描いてくれ、これを描いてくれ」といった注文に応じることはありませんでした。たとえ何らかの注文を受けて絵を描いたとしても、飾る場所や抽象的なテーマが与えられるくらいで、その中身はまったくのオリジナルでした。ですから、しばしば発注者との間で「こんなものがほしかったわけではない」といった諍いが起きたそうです。たとえば、ピカソが若くして亡くなった友人のギヨーム・アポリネールのために制作したモニュメントは、遺族らによって拒否され、受け取ってもらえませんでした。
画家が自らのために描き、それが商品となる世界へ
このように、芸術家は己の心の赴くままに表現をし、職人は依頼主の望みにかなうように制作をします。そして、近代以前には、ほとんどの画家が職人的性質を強く持っており、自らを芸術家とは認識していませんでした。なぜならば、自分の好き勝手に絵を描く芸術家には需要がなかったからです。
そもそも絵に対してどのような需要があったかといえば、壁画や、壁に飾るインテリア、書籍の挿絵、皿やコップなどの陶磁器の絵付けなど、建築物や工芸品などの添え物としての役割です。絵画を単体で鑑賞するというのは、貴族の趣味であり、肖像画というものも、もっぱら王侯貴族のナルシシズムを満足させるための装飾品でした。自分の内面を表現するような芸術家という概念が存在しなかった時代には、画家は、もっぱら職人として生きるしか道がありませんでした。
もちろん、その時代にも、内的欲求から暇な時間があれば絵を描かずにはいられない画家も大勢いたことでしょう。しかし、彼らにとって絵を描くことは「仕事」であり、あくまでも職人に徹していたのです。ルーベンスやベラスケス、ゴヤは、宮廷画家という肩書で仕事をしていました。
しかし、19世紀からのフランス近代絵画の発展は、画家に自由に絵を描く喜びを与えました。印象派から始まる近代絵画の革命は、画家が自分のために絵を描いて、なおかつそれが商品として成立する世界を切り拓いたのです。現在、芸術家が芸術家として生きていけるのも、すべては19世紀フランスにおける近代絵画(モダン・アート)の誕生に端を発しています。
ですから、フランス近代絵画は現代におけるモダン・アートの源流であると同時に、フランス革命を背景として、私たちが個人としての尊厳を持って生きることをも教えてくれるものなのです。