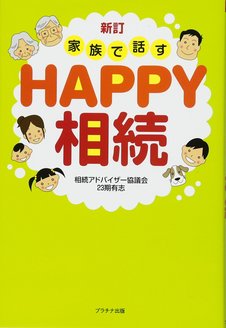取引時価と税法時価は、およそ倍近く乖離することも
不動産は「一物四価」といわれ、地価公示・地価調査による価格(以下「公示価格等」という)、相続税路線価、固定資産税路線価、実勢価格(「売買取引価格」ともいい、以下「取引時価」という)が存在し、価格水準が異なりますが、それぞれの価格は目的があって定められていることを認識しておくことが重要です。
すなわち、公示価格等は取引する際の指標とするための価格、相続税路線価は相続税課税のための価格、固定資産税路線価は固定資産税課税のための価格、取引時価は個々の当事者がそれぞれの自由意思で決定した売買価格であるということです。
相続の場面において、特に問題となるのは個別性の強い不動産の場合です。これらの不動産は、取引時価と相続税路線価を基礎にして評価された価格(以下「税法時価」という)との間に大きな差が生じる可能性が高いからです。それでは、取引時価については、多数の売り手と買い手が存在する取引市場において、適正水準で取引された価格であることを前提として、「取引時価」と「税法時価」との間に大きな差が生じてくる典型例を、以下に例示していくことにします。
①戸建開発用地における税法時価
税法時価を計算するためには、「財産評価基本通達」というルールに基づいて相続する不動産を評価することになっており、そのうち24―4(広大地の評価)という規定がありました(平成29年末まで適用)。この規定により、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものの価額は、原則として」その広大地が路線価地域に所在する場合には、以下の算式により計算した金額によって評価することになっていました。
その広大地の面する路線の路線価×広大地補正率×地積
また、広大地補正率は0.6−0.05×広大地の地積÷1000m2で求めます。
算式自体は簡潔明瞭で、広大地に該当すれば、非常に大きい節税効果が期待できました。
たとえば、広大地補正率は、地積が1000m2の場合0.55となり、2000m2の場合0.50と半分になり、5000m2の場合には0.35にもなります(0.35が下限)。
しかし、一方で、広大地に該当するかどうかについては、要件をすべて満たす必要があり、この広大地に該当するかどうかを的確に判断するには、相続税法というよりも、むしろ不動産に関する横断的な知識や総合的な経験が必要でした。
また、これらの要件をしゃくし定規に当てはめることが正しいとはいえないケースもあり、さらには、節税効果がかなり高い一方で、税務署から否認された場合の追徴課税リスクも大きいことから、税理士の相続税申告業務の現場に混乱をもたらす一因ともなってしまっていました。
②戸建開発用地における取引時価
広大地の規定によれば、取引時価と税法時価は、およそ倍近く乖離することもありえるのです。税法時価では公示価格等よりも、もともと2割下げられており、その単価に対して、さらに大きな広大地補正率を乗じるために、かなり低い価格となってしまうのです。地積が大きくなるほど、乖離は大きくなる傾向がありました。
この規定は、平成29年末で廃止され、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されます。平成30年1月1日以後の相続、遺贈または贈与により取得した土地の評価から適用されます。改正後は、間口・奥行・不整形など形状が個別的に考慮されるほか、広大地補正率の替わりに規模格差補正率が採用されることになります。
なお、改正により現行規定に比べて、取引時価との格差がかなり縮小されます。資産総額が大きいほど、また、広大地に該当する規模が大きいほど、節税効果は圧縮されてしまいます。ただし、評価額の水準が引き上げられた分、取引時価との比較で、場合によっては、いわゆるグレーゾーンがこれまでよりも広がった土地もあります。地主さんによっては、今後、時価評価の検討など、専門家とのより綿密な連携が必要となるでしょう。
現金を不動産に変える節税は、本当に有効か
①収益不動産における税法時価
税法時価においては、土地と建物は別物であり、それぞれの合計がその不動産の価格であるという考え方をします。土地・建物いずれも自己所有であることを前提とすると、土地は貸家建付地といい、「自用地とした場合の価額−自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」という算式で求められます。
建物については、「固定資産税評価額−固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合」という算式で求められます。これは建物に賃借人がいる場合には、所有者としては自己利用に制約があるので、その賃借人の権利相当分を考慮するという考え方に基づきます。そして、これらの方法により求められた土地と建物の合計額が収益不動産の税法時価となります。
②収益不動産における取引時価
一方、取引時価においては、土地と建物を一体として、その不動産がどの程度の収益力があるかで価格が決定されます。これを算式で示すと、「(総収益−総費用)÷還元利回り=収益価格」となります。総収益は、年額支払家賃と敷金等の一時金の運用益などから構成されます。総費用は、総収益を得るために必要な費用の合計額であり、土地および建物の固定資産税等、維持管理費、建物修繕費などの合計額です。還元利回りは、不動産から生み出される純収益(=総収益−総費用)から不動産価格を求めるときに使用される利回りです。
家賃収入が低くなることは、総収益が低くなることであり、当然に収益価格も低くなります。すなわち、不動産の価値が下がることであり、自然な結論です。
一方、税法時価においては、収益性という取引市場において重要な観点は考慮されず、あくまで借家権という権利が考慮されるのみです。しかも、賃貸割合が低くなると、収益性は低くなるにもかかわらず、借家人による制約が少なくなり、自用地としての価値に近づくという考え方により、控除できる額が少なくなるため、空室が多いほど、価値が上昇するという現実的ではない結果が導き出されてしまうのです。
簡単に言えば、取引時価は評価時点における現実的な将来性を反映した時価、税法時価は評価時点における(借家人がいなくなるほど価値が上がるという)非現実的な将来性を反映した時価といえるでしょう。
建物が新築あるいは築年数が浅い場合は、固定資産税評価額が現実の建築費の半分程度となるため、現金から収益性建物への資産組み換えにより節税効果は大きいですが、地方都市で立地条件が劣る場所にあり、築年数もかなり経過しているなどの収益力が低いアパート等は、取引時価は低いにもかかわらず、高い税法時価で課税されてしまうという、不良資産特有の課税上の難点を抱えることになります。
なお、人口減少時代において、賃貸需要も自然減少しているにもかかわらず、近年では、政府の低金利政策やハウスメーカーの営業攻勢などを背景に、相続税対策の名のもとでアパート建設に拍車がかかっているところもあります。特に地方都市の郊外では、物件の過剰供給により、築浅にもかかわらず、家賃の下落や空室率の上昇が発生するなどの問題も生じてきています。相続人に遺産を残すつもりが、“負”動産として遺恨を残すことになっている現状も出てきています。
これらのほか、不整形地、無道路地(再建築不可の土地も含む)、急傾斜地、市街地山林、別荘地・リゾートマンション、底地など、税法時価が取引時価よりも高くなることが多いケースは数多く存在します。このような不動産は、高い税法時価で課税されることを回避するため、事前の相続対策として、換金処分あるいは不動産の組み換えに早期に取りかかること等をお勧めします。
不動産の時価を巡る「争続」を避けるためには?
<まとめ>
現実の市場で決まる価格は、当然ながら売買を前提とした取引時価です。相続税評価額や固定資産税評価額では決してありません。ところが、たとえば、遺産分割協議の場面において、すべての相続人が同じ情報や知識を持っていないために、知らないうちに不公平あるいは不均等な分割がなされている、すなわち不動産について取引時価と離れた税法時価をベースに分割がなされているケースがあります。
実際に売買が行われる前の段階では、取引時価に代わるものとして、不動産鑑定士による鑑定評価などを活用して、中立公平な立場の専門家による証明を得ることで、適正時価の把握に努めることはたいへん有意義です。
現代は情報化社会であり、取引相場の情報は簡単に手に入ります。一部の相続人が、その他の相続人は知る由もないだろうと利己的な相続を押し進めても、不動産の時価について、たとえば遺留分減殺請求(相続人が必ず受け取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利の請求)などで争われ、その後の人間関係が修復不可能なことになっては、お互いに不幸です。いったん、疑心暗鬼になると、なかなかその気持ちはぬぐえないものです。ひょっとしたら、それを発端として次世代までに大きな遺恨を残す結果となることもありえます。
節税も大事ですが、相続を「争族」にしないことがもっと重要です。相続人同士で譲り合う気持ちと被相続人への感謝の気持ちが必要不可欠です。