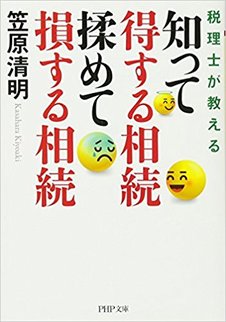評価額5000万円の土地に適用できると考えていたが…
A子さんが相続するのは、預貯金以外には実家の古い家と土地だけ。でも、その土地はずいぶん昔に入手したもので、当時はそのあたりも思いのほか安く買えたらしく、55坪ほどとけっこうな広さでした。
そのため、土地の評価額は5000万円で、預貯金の700万円と合わせると、5700万円がA子さんに残されたことになりました。
A子さんは、平成27年から相続税の制度が改正され、相続人が子ども1人の場合は、相続額が3600万円を超えると相続税が発生することを調べて知りました(基礎控除額=3000万円+〈600万円×法定相続人の数〉)。
しかし、相続するのが自宅の場合は、実家を相続し、自分の家族が居住すれば「小規模宅地等の評価減」という特例を受けることが可能になって、土地の評価を8割減らせるというのも合わせて知りました。
そこで、この特例を受ければ、うちの場合は相続税を払う必要はない、と信じていたのです。
元気な親が老人ホームで生活・死亡した場合は適用外に
ところがここで、思わぬことが起こりました。Aさんの自宅が「小規模宅地等の評価減」の特例を受けられないとわかったのです。
というのも、亡くなった人が老人ホームに入っているとき、要介護認定または要支援認定を受けていれば、この特例を受けられるのですが、A子さんのお母さんは亡くなる直前まで人一倍元気でしたから、こうした認定とは無縁でした。
そのため、誰も住んでいなかった実家は、まるまる評価額どおりになりました。相続額は3600万円の枠を超え、思ってもみなかった相続税を支払うことになってしまったのです。
もしもA子さんのお母さんが平成26年以前に亡くなっていたら、当時の相続税の基礎控除額は、子ども1人が相続する場合6000万円(基礎控除額=5000万円+〈1000万円×法定相続人の数〉)でしたから、「小規模宅地等の評価減」の特例を使わなくても、A子さんのケースなら相続税は支払う必要がありませんでした。
しかし平成27年以降に亡くなった場合は課税ベースが大幅に広がって、それまで相続税に縁のなかった一般庶民でも、相続税の対象になるケースが増えています。