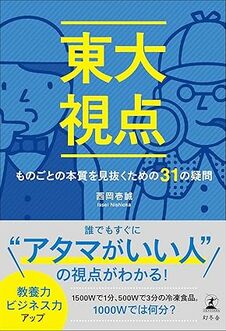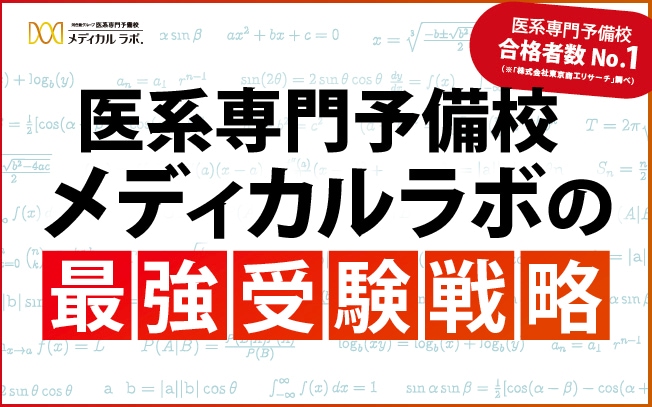「因果関係」と「相関関係」は違う!
原因があって、それによって結果が生じるという関係を「因果関係」といいます。例えばあるお店の、日ごとの来店者数を調べてみると、雨が降っている日は来店者数がかなり少なくなっていることがわかったとします。このとき、「雨が降る」ことと「そのお店の来店者数が少なくなる」ことに因果関係があると言えます。
一方で、「Aが増えるにつれ、Bが増えている」というように、2つの値の間に関連性があるような関係を「相関関係」といいます。「Aが増えるにつれ、Bが増えている」という関係を正の相関関係、反対に「Aが増えるにつれ、Bが減っている」という関係を負の相関関係といい、いずれにせよ「どちらかの値が増減するとき、連動してもう一方も増減している」という関係を表すのが相関関係です。
現象として関連しているだけで相関関係が認められるので、必ずしもそこに「Aが増えた“から”、Bが増えている」などという「因果関係」があるとは限りません。しかし人は、「Aが増えるにつれ、Bが増えている」というデータを見て、「Aが増えた“から”、Bが増えている」のだという勘違いをしてしまうことがあるのです。
因果関係と相関関係の誤認を注意する格言に、「アイスが売れると水難事故が増える」というものがあります。確かに、アイスの売り上げと水難事故の件数の推移をそれぞれグラフにして並べると、アイスの売り上げが多い時期は水難事故が増えていることがわかります。これはつまり、「アイスの売り上げ」と「水難事故の件数」に相関関係があることを意味します。では、ここに「アイスが売れる“から”水難事故が増える」という因果関係があるのでしょうか?
普通に考えたらそんなことはないとわかりますよね。「アイスの売り上げ」と「水難事故の件数」の増加には、どちらにも共通して「夏は気温が高い」という原因があります。
そこから「暑いから涼しさを求める人が増える→アイスの販売数が増える」「暑いから涼しさを求める人が増える→水遊びをする人が増える→水難事故が増える」という結果が生じており、ここには因果関係がありますが、結果同士の「アイスの売り上げ」と「水難事故の件数」の間には因果関係はありません。
しかし、私たちは「Aが増えるにつれ、Bが増えている」という情報だけを見て、そこに因果関係があるはずだ!と思い込んでしまう傾向にあるのです。
本来、因果関係の推定というのはとても難しく、慎重に判断されなければなりません。これが理科の実験であれば、あるひとつの条件だけを変えてそれ以外はすべて同じ条件で対照実験を行うなどの方法で、「本当にその要素が原因として結果に作用しているのか」を判断することができるかもしれません。
しかし、社会現象など対照実験を行うのが難しい現象に対しては、その要素と結果の間に因果関係が成立しているかどうかを調べるのは非常に困難です。まったく関係がなかったり、アイスと水難事故の例のように同じ原因から生じた結果同士であったりと、見かけ上の相関関係があってもそこに因果関係がないことも多いです。
「アイスの売り上げが多い日は水難事故が多いから、水難事故を減らすためにアイスの販売を禁止しろ」と言われても困ってしまいますよね。ですから、相関関係がある事柄同士について、安易に因果関係の存在を推定するのは危険なのです。
Point
・本来、因果関係を推定することは難しい作業
・単なる相関関係かもしれないので、安易に因果関係だと決めつけるのは危険
西岡 壱誠
株式会社カルぺ・ディエム
代表
注目のセミナー情報
【国内不動産】2月14日(土)開催
融資の限界を迎えた不動産オーナー必見
“3億円の壁”を突破し、“資産10億円”を目指す!
アパックスホームが提案する「特別提携ローン」活用戦略
【国内不動産】2月18日(水)開催
東京23区で利回り5.3%以上を目指す
建売ではなく“建築主になる”新築一棟マンション投資とは
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】