
『資産形成ゴールドオンライン』は複数の企業と提携して情報を提供しており、当サイトを経由して申込みがあった場合、各企業から報酬が発生することがあります。しかし、提携の有無などが本ページ内のサービスの評価や掲載順位に関して影響を及ぼすことはありません(提携会社一覧)。
米国ETF「SCHD」に間接的に投資できる投資信託が2024年9月に楽天証券、12月にSBI証券から販売され、「分配金の受け取り」と「値上がり益」の両方が期待できるファンドとして人気を集めています。
そこで本記事では、
「SCHDの投資信託を買うなら、SBI証券と楽天証券のどっちがおすすめ?」
「『SBI・SCHD』と『楽天SCHD』は何が違うの?」
「現在保有しているSCHDは買い直したほうがいいの?」
のような疑問を持っている方に向けて、「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の違いを徹底比較します。
先に結論を伝えると、現時点では、SBI証券で購入できる「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」のほうが、①信託報酬、②投信保有ポイントの2点でおすすめです。
ただし、楽天SCHDも2025年5月23日から信託報酬が引き下げられたため、現時点ではほとんど差がありません。
解説していきます。
\ 「SBI・SCHD」が買えるのはSBI証券だけ/
■おことわり
「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」の愛称は「S・米国高配当株式100」ですが、本記事では通称で「SBI・SCHD」と表記しています。
なお、「楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」の愛称は「楽天SCHD」なので、そのまま「楽天SCHD」と表記します。
〈目次〉
はじめに:「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の比較表

早速、「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」のスペックを比較表で紹介します。なお、基準価額(投資信託の価格のこと)と純資産総額は、2026年1月8日時点の数字です。
■「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の違い
| 略称 | SBI・SCHD | 楽天SCHD |
| ファンド名 |
SBI・S・ |
楽天・シュワブ・ |
| 投資対象 |
シュワブ・米国配当株式ETF(ティッカー:SCHD) |
|
| 基準価額 | 10,323円 | 11,052円 |
| 純資産総額 |
1,646.13億円 |
1,826.10億円 |
| 信託報酬 (年率) |
0.1227% (税込) |
0.1238% (税込) |
| 投信保有ポイント の付与率 |
年率0.022% (投信マイレージ) |
なし |
| 分配金コース の変更の可否 (「再投資型」⇔「受取型」) |
課税口座:可 NISA口座:可 |
課税口座:可 NISA口座:可 |
|
決算日 (分配月) |
3、6、9、12月の各28日 ※2025年9月より変更 |
2、5、8、11月の各25日 |
|
分配金 (1万口あたり) |
1回目:62円(2025年6月) 2回目:85円(2025年9月) 3回目:90円(2025年12月) |
1回目:85円(2025年2月) 2回目:70円(2025年5月) 3回目:80円(2025年8月) 4回目:85円(2025年11月) |
| 分配金の方針 | 利益の範囲内で 堅実に分配 |
収益調整金を一部取り崩し、 利益に上乗せして積極配当 |
|
設定日 (運用開始日) |
2024年12月20日 | 2024年9月27日 |
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント | 楽天投信投資顧問 |
| 購入できる証券会社 | SBI証券 | 楽天証券 |
楽天SCHDのほうがSBI・SCHDより2ヵ月早く運用が始まったので、基準価額と純資産総額だけでは一概に比較できません。
比較するのは、背景が赤色(「信託報酬」「投信保有ポイント」「分配金の方針」)の3項目です。
\国内(証券単体)最多の1,300万口座(2025年11月時点)/
1. 「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の主な違い…3項目で比較

比較するのは、次の3項目です。
比較ポイント①:信託報酬

現在の信託報酬(投資信託の運用や管理にかかるコスト)は、楽天SCHDが0.1238%(年率)である一方、SBI・SCHDは0.1227%(年率)となっており、SBI・SCHDのほうが0.0011%安くなっています。
■「信託報酬」の違い
| SBI・SCHD | 楽天SCHD | |
| 信託報酬 (年率) |
0.1227% (税込) |
0.1238% (税込) |
販売開始当初は信託報酬の差が0.0682%ありましたが、2025年5月にどちらも引き下げられ、現在は0.0011%まで縮まりました。
わずかな差で気にならないレベルかもしれませんが、信託報酬は投資信託の保有残高に対してかかります。そのため、基準価額が上昇すると残高の増加とともに支払う信託報酬の額も増えてきます。
コストは1円でも安いほうがいいという方は、SBI・SCHDを選んだほうがコストを最小化できます。
比較ポイント②:投信保有ポイント

投信保有ポイントは、投資信託の平均保有残高に対して毎月付与されるポイントのことです。
SBI証券は「投信マイレージ」という名称でサービスを提供しており、SBI・SCHDのポイント付与率は0.022%(年率)となっています。
一方、楽天証券にも「投信残高ポイントプログラム」がありますが、対象銘柄は楽天・プラスシリーズの6銘柄のみ。楽天SCHDは対象外となっており、楽天証券で楽天SCHDを買う場合は投信保有ポイントはつきません。
では、SBI証券でSBI・SCHDを月3万円、月5万円、月10万円で最大20年間運用したときにトータルで獲得できる投信保有ポイントを試算してみましょう。
■SBI・SCHDで獲得できる「投信保有ポイント」の累計
| 毎月の 積立額 |
5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
|
SBI・SCHD ポイント付与率 :0.022% |
3万円 | 1,281 | 5,082 | 11,402 | 20,243 | |
| 5万円 | 2,235 | 8,470 | 19,005 | 33,740 | ||
| 10万円 | 4,270 | 16,940 | 38,010 | 67,480 | ||
ご覧のように、付与される投信保有ポイントの数は、運用期間が長くなるにつれて着実に増えてきます。
また、SBI・SCHDの保有コストにあたる信託報酬は0.1227%(年率)なので、獲得できる投信保有ポイントを考慮すると、実質的なコストは0.1007%(=0.1227%-0.022%)までダウンします。
そのため、証券会社や貯まるポイントにこだわりがなく、どちらのSCHDに投資しようか迷っている方は、SBI証券でSBI・SCHDを買ったほうがポイント付与分だけお得に運用できます。
同じ指数に連動するように設計された投資信託なので、運用リターンはほぼ同じになります。SBI・SCHDが+1.5%の際に楽天SCHDが+2.5%になるような差は生じません。
【補足】楽天SCHDは楽天証券の「資産形成ポイント」の対象
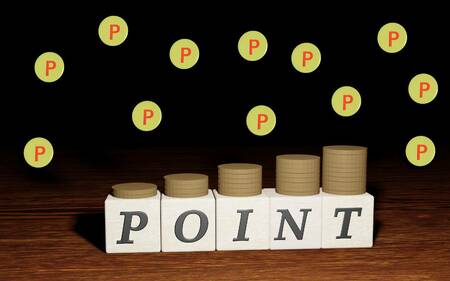
楽天証券には、投信残高ポイントプログラムとは別に「資産形成ポイント(ハッピープログラム)」という仕組みがあり、こちらは楽天SCHDも対象です。
ただし、この資産形成ポイントは、毎月末時点の投資信託の残高が初めて一定の金額に到達した場合のみ所定の楽天ポイントが付与される仕組みで、投信保有ポイントとは厳密には異なります。
楽天証券の「資産形成ポイント(ハッピープログラム)」

さらに、資産形成ポイントは、たとえ保有残高が2,000万円に達したとしても、獲得できるポイントの累計は2,090Pにとどまります。
そのため、毎月ポイントが付与されるSBI証券の投信マイレージのほうが優位性があります。
今後、楽天SCHDも「投信残高ポイントプログラム」の対象銘柄に追加されることに期待しましょう。
比較ポイント③:分配金の方針

楽天SCHDの2回目の分配金は70円(2025年5月)となり、同時期のSBI・SCHDの初回分配金62円(2025年6月)より多くなりました。
ただし、分配金の内訳を見ると、楽天SCHDは収益調整金(過去の積立金のようなもの)の一部を取り崩して積極的に分配金を支払っていた一方、SBI・SCHDは利益の範囲内で分配金を支払っていることが判明しました。
分配金が出ると投資信託の基準価額はその分だけ下がるのが一般的なので、SBI・SCHDは基準価額の下落を最小限に抑えながら堅実な運用を目指す方針だとわかります。
初回分配金の額だけで判断するのは早計すぎますが、少しでも多くの分配金(インカムゲイン)を受け取りたい方は楽天SCHD、基準価額の上昇によるキャピタルゲインの恩恵を受けながら安定して分配金を受け取りたい方はSBI・SCHDのほうが向いているといえます。
■「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の使い分け方の目安
- SBI・SCHD:キャピタルゲイン重視
- 楽天SCHD:インカムゲイン重視
\ 貯められるポイントの選択肢は5種類/
2.「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の決算日の違いを活用した投資戦略の例

「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の主な違いを解説しましたが、その他にも分配金を受け取れる決算日(分配月)が異なります。
■「決算日(分配月)」の違い
| SBI・SCHD | 楽天SCHD | |
| 決算日 (分配月) |
3、6、9、12月 の各28日 |
2、5、8、11月 の各25日 |
そして、この分配金を受け取れる月の違いを上手く利用して「SBI・SCHD」と「楽天SCHD」の両方に投資すると、1年のうち8ヵ月は分配金を受け取ることができます。
さらに、2025年5月29日はSCHDに投資する国内3本目の投資信託「Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型」(運用会社は日興アセットマネジメント)も設定されました。
分配月が1月・4月・7月・10月であることから、3本のファンドに投資することで、次のように分配金を毎月受け取る仕組みを作ることもできます。
【参考①】「決算日」の違いを利用した分配金の受け取り
| 銘柄 | |
| 1月 |
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 |
| 2月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 3月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 4月 |
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 |
| 5月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 6月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 7月 |
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 |
| 8月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 9月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 10月 |
Tracers DJ USディビデンド100(米国高配当株式)年4回分配型 |
| 11月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 12月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
SCHDだけに投資するのはリスクが高いと感じるなら、次のように1月・4月・7月・10月に分配金が出る「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」を買うといった選択肢も考えられます。
【参考②】「決算日」の違いを利用した分配金の受け取り
| 銘柄 | |
| 1月 |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
| 2月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 3月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 4月 |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
| 5月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 6月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 7月 |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
| 8月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 9月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
| 10月 |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) |
| 11月 |
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) |
| 12月 |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) |
SBI証券は、SBI・SCHDのような年4回決算型の高配当ファンドが充実しており、複数を組み合わせることにより、自分に合ったポートフォリオを作ることができます。

また、楽天証券では「日本版SCHD」ともいえる新ファンド「楽天・シュワブ・高配当株式・日本ファンド(四半期決算型)」を2025年2月7日に設定。分配金を、3月・6月・9月・12月の年4回受け取ることができます(楽天SCHDは、2月・5月・8月・11月の年4回)。
近年は、高配当に注目した年4回決算型の投資信託が増えてきたため、決算日の違いを上手く利用することで、分配金を毎月受け取る「自分年金」を作ることも可能です。
本記事を参考にして、投資戦略を広げるヒントにしてください。
\ 高配当投信の商品ラインナップが充実/


