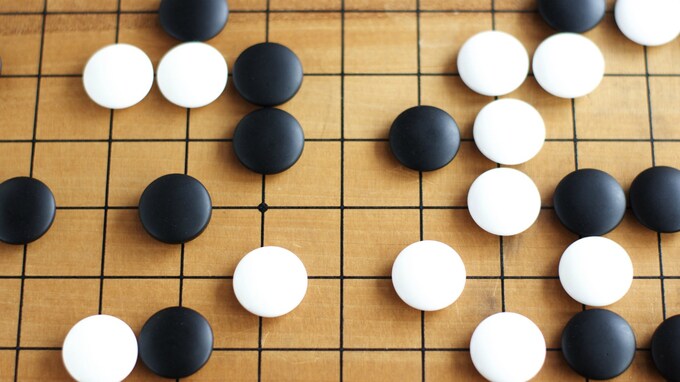「韓国の棋士」として唯一、手に入れた出場権
一九八九年九月五日、午前九時三十分。私はシンガポールにあるホテルのベッドの上に、ぼんやりと腰を下ろしていた。
朝食に熱いスープとパンを少しとったが、何の味もしなかった。シンガポールに到着したとたん引いてしまった風邪のせいだろうか。体中がこわばっていた。もうすぐ最後の決勝戦が始まる。口の中は乾き、心はじりじりと焦っていた。応氏杯(おうしはい)の決勝5番勝負の最終局。私は目をつぶり、呼吸を整えた。深く息を吐くと、これまでの数カ月間のことが、走馬灯のように脳裏に浮かんできた。
韓国の棋士として唯一、手に入れた出場権。最後の一手まで予断を許さなかった小林光一との準々決勝と、林海峰(りんかいほう)との準決勝。中国で過ごした地獄のような十日間。そして奇跡のような勝利を生んだ、数日前の第四局まで……。
応氏杯は台湾の富豪である応昌期(おうしょうき)が、私財を投じて立ち上げた世界プロ囲碁選手権大会だ。私が決勝に進出した一九八九年が、第一回の大会だった。同じころ日本でも、初の世界大会である富士通杯が始まったが、応氏杯はその意味が少し異なっていた。
四年ごとに開かれる「囲碁のオリンピック」であり、賞金はなんと四十万ドルだったからだ。史上最大規模の賞金が誰の手中に渡るか、世界の関心が集まった。実は応氏杯は、初めから中国人が中国の囲碁のために作った大会だった。
「脇役」だったはずの私が、決勝戦に進出
中国は囲碁の宗主国としての自負心がとても強かったが、いつも日本の囲碁の陰にあった。ところが一九八四年に始まった日中スーパー囲碁で、異変が起こった。中国の聶衛平(じょうえいへい)が、日本の超一流棋士を相手に、第一回から三回までの大会で、なんと十一連勝を記録したのだ。この勢いに乗った中国は、応氏杯でどの国が囲碁の最強国かを明らかにしようとした。
鼻高々な日本碁界を打ち負かし、世界最高の囲碁強国として君臨しようとしたのだ。参加した棋士の顔ぶれを見ても、中国人が半数を占めており、残りの三分の二が日本人で、韓国人は私と趙治勲(ちょうちくん)九段だけだった。しかし趙治勲九段は日本棋院所属だから、実際に招待された韓国の棋士は私一人だけだった。
私は日本と中国との決闘に招かれた、ある意味で脇役だった。来たければ来い、来たくなければ来なくとも良いと言わんばかりに渡された、みすぼらしい招待状だった。気分は良くなかった。しかし、行かないわけにはいかなかった。たとえ壮絶に敗退しようとも、とにかく出かけて、何かを学ぶべき時だった。
ところが、誰にも予想できなかったことが起こった。頭数をそろえるための脇役だったはずの私が、決勝戦に進出したのだ!人々の関心は、日本か中国かではなく、中国か韓国かに移っていった。中国は主催国としての自尊心をかけて、必ず勝たなければならなかった。韓国は囲碁の辺境の地というイメージを払拭して、世界の囲碁界の中心に立てる絶好のチャンスだった。
決勝は五局のうち三勝した方が勝ちだ。準決勝戦が終わってから五カ月という時を経て始まった対局だった。決勝戦を数週間後に控えたころ、突然、主催者側から知らせがあった。決勝五番勝負は、すべて中国で執り行うというのだ。考えられないことだった。片方の懐で五局の対局すべてを行うというのは、もう一方にとっては「負けろ」と言われたも同然だった。
韓国側は強く抗議した。結局、主催者側が一歩譲り、中国で三局、そして第三国で二局を行うことで合意した。
殺伐とした空気の中、行われた対局
しかし、その条件すらも、私にはとても不利だということを、中国に出掛けてから悟った。その当時の韓国は中国を「中共」と呼んでおり、なんともやっかいな相手だった。韓国と中国には国交もなく、飛行機の直行便が飛んでいるはずもなかった。私はまず香港に出掛けてビザを取り、そこから飛行機や船、汽車など、あらゆる交通手段を動員して、二日がかりでようやく杭州に到着した。
ホテルに着いて荷を解いた時には、すっかりくたびれ切っていた。加えて私を緊張させたのは、中国の雰囲気だった。初めて空港に降り立った時、すでに殺伐とした空気を感じた。滑走路にはミグ戦闘機の編隊がずらりと並んでおり、至るところに公安が配置されていた。ホテルは広くて快適だったが、その重苦しいムードはどうにもならなかった。散歩や外出などしようものなら、まるで影のように公安が私の跡をつけて来た。午後六時にもなれば、漆黒のような闇と恐ろしいほどの静寂が辺りを包んだ。息が詰まった。対局に対する重圧感より、環境が与える圧迫感が私を苦しめた。
そんな中で初めての対局が行われ、幸いにも私は勝つことができた。私がうまく打ったというよりも、聶衛平のコンディションがひどすぎたのだ。彼は中国人の期待を一身に集め、極度の重圧感に苦しんでいた。しかも心臓の弱い人だから、対局中に緊急事態が発生してはいけないと、酸素マスクを常備していた。
何日か置きに続いた第二局と第三局は、聶衛平の勝利だった。息詰まるような中国の雰囲気が、私の首を絞め上げるかのようだった。滞在が一週間を過ぎたころ、私は一刻も早く中国を脱出しなければ、精神が分裂するのではないかとまで思った。実力の違いではない。その重圧感に耐え切れずに、続けざまに二局負けてしまったのだ。
聶衛平の二勝に、中国全土がお祭り騒ぎだった。私は静かに立ち去る準備をした。ところが中国は、最後の日まで私をたやすく解放してはくれなかった。中国から香港に出ようとした時、書類の問題で足止めを食らってしまったのだ。
私はこのまま中国に捕らわれてしまうのではないかと、不安にかられた。千辛万苦の末、やっと香港行きの船に乗った。ようやく脳に新鮮な酸素が行き渡るような気がした。
ああ、もう大丈夫だ!
【後編】へ続く