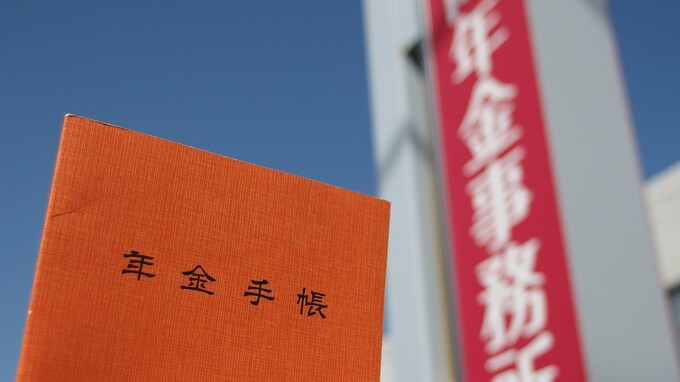遺族厚生年金を「1円も受け取れない」ワケ
夫が死亡した場合、65歳以降の妻への遺族厚生年金は「夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」(ア)あるいは「夫の報酬比例部分の4分の3の3分の2と妻自身の老齢厚生年金の2分の1の合計」(イ)、いずれか高いほうの金額で計算されます。
Bさんは個人事業主になってから厚生年金には加入していませんでしたので、報酬比例部分は60万円程度でした。そのため、遺族厚生年金は
- アで計算……60万円×4分の3=45万円
- イで計算……60万円×4分の3×3分の2+120万円×2分の1=90万円
となります。したがって、金額の高いイの90万円を遺族厚生年金の額とみなします。
しかし、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は、遺族厚生年金とあわせて受給できるルールがあるものの、実際に受給できる遺族厚生年金は「アあるいはイの遺族厚生年金の額から、妻の老齢厚生年金の額を差し引いた額」です。
Bさん死亡による遺族厚生年金は90万円ですが、ここからAさんの老齢厚生年金120万円を引くとマイナスになってしまいます。この場合、Bさんが亡くなっても遺族厚生年金がまったく支給されないことになります。
つまり、Bさん死亡後もAさんが受給できるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金のみ……Aさんは年金事務所でこの事実を知り、思わず絶句してしまいました。
遺族厚生年金が出なくても「繰下げはできない」
そんな……遺族厚生年金がもらえないなんて……動揺を隠せないAさんでしたが、ここで疑問が残ります。
Aさん「遺族厚生年金がもらえないのに、なんで繰下げ受給ができないんですか? 先ほどは『遺族厚生年金の受給権が発生するから繰下げ受給ができない』という説明でした。でも遺族厚生年金がもらえないなら、繰下げできるんじゃないんですか?」
しかし、職員は申し訳なさそうに「Aさんの場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金、いずれも繰下げ受給ができません」と告げます。
どうやら、66歳になる前に遺族厚生年金の受給権が発生すると、そもそも老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げ受給できないことになっているということでした。
たとえ、遺族厚生年金の実際の支給額が0円だったとしても、「受給権そのものがある場合」にこのルールが適用されてしまうのです。
Aさんは結局、繰下げずに老齢年金を65歳から受給するしか方法がなく、事前に立てていた「老後の資金計画」が大きく崩れてしまいました。