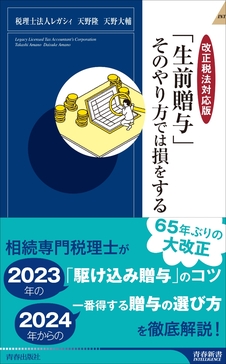住宅取得等資金贈与(2023年12月末まで)
18歳以上の子が、親や祖父母からマイホームの購入やリフォームのための資金を贈与された場合、最大1000万円まで贈与税が非課税になるという特例です。非課税の限度額は、住宅の品質やリフォームの内容によって変わります。
ただし、贈与を受ける人の所得が2000万円以下という条件があります。あくまでも住宅資金の援助という前提なので、子どもに資金力がある場合には適用されないのです。2021年の年末までという期限が設定されていましたが、この制度は人気があるので、2023年12月まで延長されています。
個人的な意見ですが、延長の背景には景気を浮揚させたいという判断もあるのかもしれません。住宅を建てたりリフォームをしたりすると、それをきっかけに電化製品、家具、室内用品なども新しく購入することが多いので、住宅業界にとどまらず、幅広い業界に経済効果をもたらすことにつながります。単に制度自体に人気があるだけでなく、そんなことが背景にあるのではないでしょうか。
夫婦間での居住用不動産の贈与
結婚して20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産を贈与する場合、2000万円まで贈与税が非課税になるという特例です。「おしどり贈与」とも呼ばれています。
もっとも、配偶者に先立たれた場合は、相続財産の法定相続分もしくは1億6000万円のうち多いほうの金額までは課税されないという配偶者の税額軽減の制度があります。また、亡くなった方の自宅の土地については「小規模宅地の評価減」という制度もあります。通常はそうした制度で十分なのであまり活用されていません。
「どうしても生きているうちに贈与してほしい!」と配偶者に迫られたときに活用する制度といえるでしょう。
使用貸借──親の土地に子どもがタダで住んでいる場合
親の土地に子どもが家を建てるという話はよくあります。その場合、地代も権利金も払わないでいる状態を使用貸借といいます。この場合は贈与にならず、贈与税はかかりません。
相手が他人の場合はタダで貸すことはないので、国税庁はちょっと甘いのではないかという意見もあります。しかし、使用貸借の場合、親が亡くなって相続財産を計算する際に、土地評価額が100%計上されるというデメリットがあります。もし、子どもが地代や権利金を払って借りていれば、借地権価格が控除されて評価額が安くなるのですが、使用貸借では全額が算入されてしまうのです。
つまり、贈与税はかからないけれども、その分は相続税で埋め合わせするという発想です。いわば、贈与税と相続税が一体化されているわけであり、将来の税制改正の先取りといえるかもしれません。